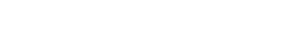後篇第十六章 念珠
(本文)
問う。念仏せんには必ず念珠(ねんじゅ)を持たずとも苦しかるまじく候うか。
答う。必ず念珠を持つべきなり。世間の唄(うた)を唄い、舞(まい)を舞うすらその拍子(ひょうし)に従うなり。念珠を博士(はかせ)にて舌と手とを動かすなり。ただし無明(むみょう)を断ぜざらんものは妄念(もうねん)起こるべし。世間の客と主(あるじ)とのごとし。念珠を手にとる時は妄念の数をとらんとは約束せず。念仏の数とらんとて、念仏の主をすえつる上は、念仏は主、妄念は客なり。さればとて、心の妄念を許されたるは過分(かぶん)の恩なり。それにあまさえ口に様々の雑言(ぞうごん)をして念珠を繰りこしなどすること、由々(ゆゆ)しき僻事(ひがごと)なり。
(現代語訳)
問い。念仏するには必ずしも数珠を持たなくても、差しつかえないでしょうか。
答え。必ず数珠を持つべきです。世間で、歌を歌い、舞を舞う時でさえその拍子に従います。〔まして念仏するには〕数珠をたよりにして舌と手とを動かす〔べきな〕のです。
ただし、無知の煩悩を断っていたい者には、迷いの心が起こるに違いありません。〔迷いの心と念仏との関係は、〕世間でいう客人と主人の関係のようなものです。数珠を繰るときは、「迷いの心の数を数えよう」と誓いはしません。「念仏の数を数えよう」と念仏を主人と決めた以上は、念仏が主人であり、迷いの心は客人に過ぎません。
とはいえ、心の迷いを許されていることは〔阿弥陀仏からの〕過分の恩であります。それなのに、あろうことか様々な悪口を言いながら数珠を繰るなどは大変な過ちであります。
『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊
(解説)
今回の御法語は問答形式になっておりまして、どなたかが法然上人にお尋ねになり、それに法然上人がお答えになるという形です。
質問の内容は、「お念仏を称えるのに、必ずしも数珠を持たなくてもよろしいですか」ということです。
教義的には、阿弥陀さまは「南無阿弥陀仏と称える者を極楽に迎え取る」と言って下さったわけであって、別に「数珠を持って念仏を称える者を」と限定されてはいないですから、「必ずしも数珠は持たなくてもいいですよ」となるはずです。
ところが法然上人のお答えはそうではありません。
「必ず念珠を持つべきなり」つまり「必ず数珠を持たないといけない」とおっしゃるのです。
このお答えを、どうしてかなあと思って考えました。
数珠というのは、お念仏を数える道具です。
「南無阿弥陀仏」と一遍称える毎に、一つ数珠の珠をを繰っていきます。
「必ず念珠を持つべきなり。世間の唄を唄い、舞を舞うすらその拍子にしたごうなり。念珠をはかせにて舌と手とを動かすなり」
「必ず念珠を持つべきですよ。世間の唄を唄ったり、舞を舞うのでもその拍子というものがあるんだ。数珠を博士にして…」
博士というのは邦楽の音符のことです。
「舌と手とを動かすなり」。
お念仏を称えて数珠を繰ってリズムをとるのです。
リズムをとってお念仏を称えますと称えやすくなるのです。
「但し無明を断ぜざらん者は妄念起こるべし。世間の客と主とのごとし」
但しお念仏を称えていても、悟りを開いていない人(私達のことですね)には、余計なことが次から次に浮かんできます。
お念仏に集中しようにも、「ああお腹減ってきたなあ。今日の晩ご飯何にしよう。そういえば、親戚の聡子ちゃんどうしてるんやろ。あの子頭よかったなあ。息子さんもいい大学行ったって言うてたわ。お医者さんになるって。そうや、明日病院行く日や。忘れてたわ」などというように。
心ここにあらずです。
法然上人は「世間の客と主とのごとし」だとおっしゃるのですが、ちょっと意味がわかりにくいと思います。
読み進めると分かってきますので、そのまま進みます。
「数珠を手に取るときは妄念の数を数えているんじゃないんだ。お念仏を数えているんだ。ということは、数珠を繰っている時は念仏が主、妄念が客なんだ」ということなのです。
「しかし、心の妄念をお許し下さっているのは身に余るご恩なんですよ」
これについてエピソードがあります。
ある時法然上人の元に明遍僧都という方が訪ねて来られました。
明遍僧都は非常に有名な高野山の修行者です。
その明遍僧都が戸を開けるや否や、「法然上人に聞きたいことがあります。私はお念仏を一所懸命称えておるけれども、どうしても心が散り乱れる。これでは往生できませんか?」という質問であります。
明遍僧都ほどの修行者であっても心が散り乱れるというのです。
法然上人は「いやいや。妄念が起こるのは誰にでもあることです。私達には目や耳や鼻がある。それと同じように妄念も生まれもって備わっているんですよ。妄念を無くせということは、目や耳や鼻を取れと言われているようなもので、私達には相当に難しいことですよ。しかし、阿弥陀さまは極楽への往生を願い、念仏を称える者は目や耳や鼻が付いた、そのまますくい取って下さいます。だから妄念があるなら妄念があるまま、阿弥陀さまはお救い下さるのです。何も心配はいりませんよ」とお答えになったのです。
明遍僧都は「そうですか!これで安心しました!」と喜んで帰られたとお伝記には記されています。
この逸話で妄念については語り尽くしたと思います。
本当に身に余るご恩ですね。
ただし、最後に少し釘を刺されています。
「身に余るご恩をいただいておきながら、その上口にいらんことをベラベラ喋って、形だけ信仰深そうに数珠を繰っているようではいけませんよ」とおっしゃっています。
我々は「妄念があっても救ってもらえる」と言われると、何をしてもOKだと勘違いしてしまいます。
大事なことは、何はともあれ往生を願って阿弥陀さまにお任せしてお念仏をお称えすることです。
そうする者は、妄念があっても救う、と言って下さっているのです。
それに甘えて、「もう救われた」と思って念仏も称えずに、形だけ信仰深そうに数珠を繰って、ベラベラ余計なことばかりしゃべっていたらいけませんよ、ということなのです。当たり前のことですが、やりそうですよね。
法然上人は私たちのことをよく分かって下さってるのです。
つまりは、「念仏を中心にしていきなさいよ」ということです。
数珠を持つ時は、お念仏を数える時です。
ですから数珠を持つ時は、お念仏が中心です。
「数珠なんて別に持たなくてもいい」と言いますと、結局お念仏も称えないようになりがちです。
しっかりと数珠を持ってお念仏を称え、その数を数えて、またそれを励みにしてお念仏を称えていくことは大切です。
後篇第十五章 日課
(本文)
毎日の所作に、六万十万の数遍(すへん)を念珠(ねんじゅ)を繰りて申し候(そうら)わんと二万三万を念珠を確かに一つずつ申し候わんといずれかよく候べき。答う。凡夫(ぼんぶ)のならい、二万三万をあつとも、如法にはかないがたからん。ただ数遍の多からんにはすぐべからず。名号を相続せんためなり。必ずしも数を要とするにはあらず、ただ常に念仏せんがためなり。数を定めぬは懈怠(けだい)の因縁なれば、数遍を勧むるにて候。
(現代語訳)
〔問い〕毎日の勤めにおいて、六万遍、十万遍の念仏を、数珠を〔おおまかに〕繰って称えるのと、二万遍、三万遍の念仏を数珠で確実に一つずつ称えるのとでは、どちらがよいのでしょうか。
答え。凡夫の常として、二万遍、三万遍を〔日課に〕割り当てたとしても、仏の教えに適うことは難しいでしょう。とにかく念仏の数が多いのに越したことはありません。名号を称え続けるためです。必ずしも数そのものが重要なのではありません。ただ常に念仏するためです。念仏の数を定めないのは怠け心のもとになるので、数を決めた念仏をお勧めするのです。
(解説)
今回のご法語は問答形式になっていまして、どなたかが質問され、それに法然上人がお答えになっておられます。
「毎日お念仏を称えるのに、6万、10万という数を荒っぽく称えるのと、2万、3万という数をしっかり数珠を繰ってお念仏を数えながら称えるのとどちらがよろしいですか?」という質問です。
我々が聞きそうな質問なのかもしれません。
ただ、2万、3万と6万、10万とを比べてるのですから、相当な念仏者です。
かなり高レベルの話だといえます。
そもそも数珠というものは、お念仏を数える道具なのです。
2万、3万のお念仏を丁寧に数珠を繰って称えるのと、雑に6万、10万を称えるのとどちらが良いですか?ということなのです。
普通の感覚から言いますと、「6万、10万っていう数を雑に称えるよりも、多少減っても2万、3万なんやから、それを丁寧に称える方が良いのでは?」と思いませんか?
しかし答えは反対なのです。
「私達凡夫というのは、たとえ2万、3万であってもきっちりと身と心を整えて称えることなんかできないでしょう。だから数が多い方が良いのですよ」という理屈です。
そして「それは数が多い方がお念仏が続くからだ」とも書かれています。
相続といいますのは、継続することです。
多ければ多いほど、間無くお念仏を称えることができるのですから、多く称えなさいよ、ということです。
「必ずしも数多ければいいというものではありませんが、常に念仏をするだめには多い方がお念仏を続けることができるでしょう。
数を定めないのは怠けの原因になるから、数を定めることを勧めているのですよ」と書かれています。
数を数えるってことは非常に励みになります。
よく万歩計を持って歩いている人がいるでしょう。
「今日は5千歩歩いた、明日はもっと歩こう」と。
それと同じように、お念仏も「今日は千遍称えた、明日は2千遍称えよう」となります。お念仏は称えれば称えるほど、また称えたくなるものです。
今回の御法語には「日課念仏」という題がついています。
日課ですから、一日何遍称えるということを定めるのです。
数を定めないと、体調や気分によって称えない日が出てきて、しまいには全く称えなくなってしまうのが私達の常です。
ですから仏さまの前で「私は一日千遍称えます」という風に誓うのです。
五重相伝や授戒会を受けた方は毎日何遍称えるということをすでに誓います。
たとえば1日に3百遍としますと、称える時間はあっという間です。
5分~10分もあればできます。
形だけではなしに、実行していただきたいと思います。
そのように日課を定めることが、常に念仏を称えることにつながるのです。
後篇第十四章 四修
(本文)
問う。信心のようは承りぬ。行(ぎょう)の次第、いかが候うべき。
答う。四修(ししゅ)をこそ、本(ほん)とすることにて候え。一つには長時修(じょうじしゅ)、乃至四つには無余修(むよしゅ)なり。一つには長時修というは、善導(ぜんどう)は命の終わるを期(ご)として誓って中止せざれという。二つに恭敬修(くぎょうしゅ)というは、極楽の仏法僧宝(ぶっぽうそうぼう)において、常に憶念(おくねん)して尊重(そんじゅう)をなすなり。三つに無間修(むけんじゅ)というは、要決に曰く常に念仏して往生の心をなせ。一切の時において心に常に思い、たくむべし。四つに無余修というは、要決にいわく、専ら極楽を求めて弥陀を礼念するなり。ただ諸余(しょよ)の行業(ぎょうごう)を雑起(ぞうき)せざれ。所作(しょささ)の業(ごう)は日別に念仏すべし。
(現代語訳)
問い。
信心のありようはお伺いいたしました。行のはこびはどのようであるべきでしょうか。
答え。
四修を基本とするのです。第一の長時修から、第四の無余修までです。
第一の長時修というのは、善導大師は「命が終わる時までを期限とし、誓って中止しないように」とおっしゃいました。
第二に恭敬修というのは、極楽の仏・法・僧の三宝を常に心にかけ、尊び重んじるのです。
第三に無間修というのは、『西方要決』によれば、「常に念仏して、往生したいという思いを抱け。どんなときでも〔それを〕心にいつも思い定めよ」とあります。
第四に無余修というのは、『西方要決』によれば、「ただひたすら極楽を求めて阿弥陀仏を礼拝し、心にかけるのである。他の様々な修行を交えてはならない。なすべき勤めとしては、日々に念仏することである」とあります。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
「お念仏を称えましょう」「とにかくお念仏を称えましょう」と言いますが、何でもかんでも称えればそれでいい、というわけではありません。
「100円あげるから称えてごらん」と子どもに言い、「じゃあ南無阿弥陀仏」と称えてそれで往生できますよ、というわけではもちろんありません。
やはり心、すなわち「信心」が必要です。
お念仏を称える者の信心とは、「極楽へ往生したい」と願い、「必ず阿弥陀様が救ってくださる」と深く信じるということです。
この信心なしにただ南無阿弥陀仏と称えているだけでは極楽往生はできません。
いや、この心なしで南無阿弥陀仏と称えること自体が矛盾していますので、称えることはできないでしょう。
このご法語は問答形式になっています。
お弟子さんが法然上人に質問をし、それに法然上人がお答えになってるものです。
恐らくこの問答の前に、信心に関する問答があったのでしょう。
「問う。信心の様は承りぬ。行の次第、いかが候うべき」
「質問します。信心のことはよくわかりました。極楽往生を願って阿弥陀様を深く信じるのですね。では、行としてのお念仏は具体的にどのように称えていけばよろしいのでしょうか?」という質問です。
「答う。四修をこそ本とすることにて候え。一つには長時修、乃至四つには無余修なり」「答えましょう。四修が基本ですよ。第一の長時修から第四の無余修までです」
「一つに長時修というは、善導は命の終わるを期として誓って中止せざれという」
「一つ目の長時修というのは、善導大師がおっしゃるには死ぬまで続けるということです。
お念仏のみ教えを知って、「そうか、有り難いな。では称えましょう」と言って千遍お念仏を称えたとします。
「これだけ称えたからもう大丈夫。一生分称えました」というようなものではありません。
お念仏のみ教えと出会ったその時から命終わるまで、ずっと称え続けるのです。
40歳でお念仏と出会った人が80歳まで生きるとしたら40年間、60歳で出会ったら20年間、70歳なら10年間称えることができます。
さらには臨終間際でお念仏と出会ってたった10遍しか称えることができなかくてもいいのです。
お念仏との出会いから死ぬときまでです。
たとえ途中で一旦称えることができなくなったとしても、また再開した時から死ぬときまで称えればよいのです。
これが長時修です。
「二つに恭敬修というは、極楽の佛・法・僧宝において、常に臆念して尊重をなすなり」
「二つ目の恭敬修は、極楽の佛・法・僧に常に思いを寄せ、大切にすることです」
恭敬修は、恭しく敬うと書きますように、敬って大切にすることをいいます。
何を大切にするのかというと、極楽の佛・法・僧です。
佛・法・僧を三宝といいます。
お釈迦様の時代から、佛教徒になりたいという人がお釈迦様の元にやってきたら、まず「佛・法・僧を敬いますか?」「はい、敬います」というところから入りました。
佛教徒の基本です。
佛はお釈迦様、法はお釈迦様が説かれた八万四千のみ教え、僧は佛教教団を構成する人々です。
佛教のみ教えを信じる者同士がお互いに敬い合うということです。
いつもお勤めの最初に香偈を称えた後、三宝礼というものを称えますね。
三宝礼はこの「佛・法・僧の三宝を私は敬います」ということを言葉と身体で表現したものです。
このご法語では「極楽の佛・法・僧宝」とあります。
極楽の佛は阿弥陀様です。
極楽の法は極楽へ往生するための法ですから、お念仏のみ教え。極楽の僧は極楽におられる菩薩様です。
観音菩薩、勢至菩薩をはじめ、多くの菩薩様がおられます。
菩薩様の中にはみなさんのご先祖様、みなさんの大切なあの方もこの方もおられます。
極楽へ往生した方は、みんな仏様になるために楽しく修行に励まれます。
仏様になるために修行する方を菩薩といいます。
ですから極楽の僧にはお仏壇にお祀りしているお位牌のあの方も含まれます。
その極楽の佛である阿弥陀様に思いを寄せ、お念仏に思いを寄せ、極楽におられる方々に思いを寄せるのです。
「極楽はよいところなんだろうなあ。阿弥陀様がおられてみんな仲良く過ごしておられるんだろうなあ。あの人も極楽で幸せに過ごしているんだろうなあ。また会いたいなあ。お念仏を称えていたらいつか極楽で会えるなあ」と思いを寄せ、そして敬うのです。
身近なところで言いますと、お仏壇を大切にする、仏具を大切にするということも大事です。
仏様を敬う方がお仏壇や仏具を粗末に扱うということはあり得ません。
法が記されたお経の本も大切にしなければなりません。
あるお檀家さんは、夏場蚊が飛んできて、思わずお経の本で「パチン」と殺してしまわれました。
さすがに私も「それはいかんでしょう」と注意しました。
「すみません。」と反省されましたが、これはいけません。
また、法事の際に私はお経の本を施主さんにお渡しして、「みなさんに配ってください」と言います。
ときどき乱暴な方もにます。
「いくで。ホイッ、ホイッ」と畳の上を滑らせるようにお経の本を投げる方がおられます。今まで何人もおられました。
子どもではありませんので、叱るわけにもいかず、いつも心で嘆いています。
お経の本は雑誌ではありません。
私たちの命の行き先と善きところへ行く方法が説かれた大切な大切なものです。
注意しなくてはなりません。
僧はお仏壇のお位牌です。
仏様同様お水やご飯をお供えし、旅先でおみやげを買ってはお供えし、その方が目の前におられるかの如く話しかけるのです。
その方が最も喜ばれるお念仏を称えるのです。
これが恭敬修です。
「三つに無間修というは、要訣に曰く、常に念仏して往生の心をなせ。一切の時に於いて、心に常に思い巧むべし」
「第三の無間修とは、『西方要訣』によれば、常に念仏して往生したいという思いを抱きなさい、どんなときもそれを心に思い定めなさい、とあります。」
無間修は、お念仏を忘れないように続けることです。
「ゴルフを続けていますか?」と尋ねると、「続けていますよ」と答える。
ゴルフを続けている方も24時間ずっとゴルフをしているわけではありません。
たとえ月に一度でも「続けていますよ。」と答えるはずです。
やめてしまわずに定期的に続けているわけです。
「今日は七回忌ですな。お念仏を称えるのは三回忌以来ですわ」というのは続けているのではないですね。
七回忌まですっかり忘れていたわけですから。
お念仏の場合は月一度を続けているとは言い難いでしょう。
「月参りの時に毎回称えています」という方は、私が月参りに伺わなくなったらやめてしまいますね。
月参りに行った時に想い出して称えているにすぎません。
やはりお念仏は最低毎日称えるべきでしょう。
毎日一遍でもいいのかというと、一遍でも構いません。
しかし数が多ければ多いほど続きやすいと言えます。
お念仏を続けるために最も効果的なのは、数を定めることです。
一日に100遍、300遍と数を定めて称えていきますと、癖付きます。
歯を磨くことは習慣付いていなければ相当な手間なはずです。
洗面所まで行って3分、5分と毎日朝夕磨かなくてはならないのですから。
でも習慣付くと磨かないと気持ち悪くて仕方ないでしょう。
お念仏も習慣付くと、毎日の定めた数を称えていないと気持ち悪くなります。
そうなるとしめたものです。有り難いことにお念仏はお仏壇の前だけでなく、どこでも称えることができますから、忙しくてもできるのです。
私はいつも「歩きながらでもできますし、お風呂に入っていてもできますし、洗い物をしていてもできますし、車を運転していてもできますよ。」と申します。
有る方が、「お風呂に入ってやってみたけど難しい」とおっしゃるので、「なぜ難しいのですか?お湯に浸かっている間に称えればいいではないですか。」と言いますと、「私は浴槽で腹ばいになって体操しているんです。体操しながらお念仏は難しいです。」とおっしゃいました。大きな身体のその方が腹ばいになるほどの浴槽ですから、相当大きいのでしょう。その方にはお風呂の中でなく、違う方法を色々試すことをお勧めしました。自分の生活の中で、やりやすい方法をお試しください。
そうやってお念仏が身につきますと、心を極楽へ向けやすくなります。今まで法事の時ぐらいしか向かなかった心が日々向くようになります。
お念仏と信心は凧とたこ糸の関係に似ています。凧が信心、凧糸がお念仏とします。凧は遠く離れることもありますし、風に揺られてフラフラすることもあります。信心は深まるときもあれば、薄らぐこともあるでしょう。でも凧糸をしっかり持っていれば、またちゃんと凧は風に乗ります。お念仏を称え続けていれば、信心はふらついても無くなりません。また取り戻すことができます。
お念仏が無くてはならないと感じるようになることでしょう。
「四つに無余修というは、要訣に曰く、専ら極楽を求めて弥陀を礼念するなり。ただ諸余の行業を雑起せざれ。所作の業は日別に念仏すべし。」
「第四の無余修というのは、『西方要訣』によれば、ただひたすら極楽を求めて阿弥陀様に礼拝し、思いを寄せるのである、他の修行を交えてはならない、毎日の行は念仏を称えることである、とあります。」
無余修は「私の信仰は阿弥陀様一筋。求めるのは極楽への往生一筋。行はお念仏一筋。」ということです。
他にも多くの宗教や宗派があります。どれもぞんざいに扱う必要はありません。どれも尊いと思っておればよいのです。しかし、自分の信仰としてあっちもこっちもとフラフラしているとどっちつかずの信仰になり、結局臨終の時に迷います。自分のピンチの時に役に立たない信仰しか育ちません。
どの教えも尊いけれども、私の信仰は阿弥陀様であり、求めるところは極楽浄土、行はお念仏、と定めることが必要です。
もちろん知り合いの結婚式のために教会へ行っても結構です。賛美歌を歌いましょうと言われれば歌えばいい。初詣に家族で神社に行くことも結構です。柏手を打てばいい。でも自分が信じる道、求める道、行ずる道は一本である、と明確に定めておく。
これが無余修です。
この四修の説明をある94歳のおばあちゃんに言いましたら、「こんな言葉は知らんかったけど、こんなん当たり前ですやん」とおっしゃり、感動しました。
これは念仏を日々称えてお念仏を生きる糧にしている人からすれば当たり前のことです。何の苦労もいりません。
しかし、まだ信心もない人に言うと「難しいなあ」となることでしょう。
「信心の様は承りぬ」という方に説かれたものだというのはそういうことなのでしょう。
しかし苦から逃れたい人、往生を目指す人には必要不可欠の大切だということは間違いありません。
後篇第十三章 無比法楽
(本文)
一々の願の終わりに、もし爾(しか)らずば正覚(しょうがく)を取らじと誓い給(たま)えり。しかるに阿弥陀仏、仏になり給いてよりこのかた、すでに十劫(じっこう)を経(へ)給えり。正に知るべし、誓願虚(むな)しからず。しかれば、衆生(しゅじょう)の称念(しょうねん)する者、一人も虚しからず、往生することを得(う)。もししからずば、誰(たれ)か仏になり給える事を信ずべき。三宝(さんぼう)滅尽(めつじん)の時なりと言えども、一念すれば尚往生す。五逆深重(じんじゅう)の人なりと言えども、十念すれば往生す。いかに況(いわん)や三宝の世に生まれて五逆を造らざる我ら、弥陀の名号を称えんに往生疑うべからず。今、この願に遇える事、実にこれおぼろげの縁にあらず。よくよく悦(よろこ)び思(おぼ)し召(め)すべし。たとひ又、遇うといえども、もし信ぜざれば遇わざるがごとし。今深くこの願を信ぜさせ給えり。往生疑い思し召すべからず。必ず必ず二心(ふたごころ)なく、よくよくお念仏候(そうろう)て、このたび生死(しょうじ)を離れ、極楽に生まれさせ給うべし。
(現代語訳)
〔阿弥陀仏が四十八の誓願を立てられたとき、〕それぞれの願の最後に「もし、この〔願いの〕通りにならなければ、〔私は〕正しい覚りを開くことはない」と誓われました。そして、阿弥陀仏は仏となられてから、すでに十劫という長い年月を過ごしておられます。まさしく知らねばなりません、誓願は空言(そらごと)ではないのです。ですから念仏を称える人々は、一人残らず往生することができます。もしそうでなければ、〔阿弥陀仏が〕仏になられたことを誰が信じられるでしょうか。
仏・法・僧の三宝がことごとく滅びてしまった時代でさえ、一度でも念仏すれば往生します。五逆という深くて重い罪を犯した人でさえ、十遍念仏すれば往生します。まして仏・法・僧の三宝がなお残る時代に生まれ、五逆の罪を犯していない私たちが、阿弥陀仏の名号を称えれば往生することを疑ってはなりません。
今この阿弥陀仏の本願に出逢えたことは、本当に並大抵の因縁ではありません。よくよくお喜びなさいませ。たとえまた、本願に出逢えたとしても、もし信じないならば、出逢わないのと同じことです。〔あなたは〕今、深くこの願を信じておられます。ご自身の往生をお疑いになってはなりません。必ず必ず二心なく、よくよくお念仏なさり、この生涯を限りに迷いの境涯を離れ、極楽にお生まれ下さいませ。
(解説)
みなさんは阿弥陀さまのプロフィールをご存じでしょうか?
私たち浄土宗の者のご本尊は阿弥陀さまですから、阿弥陀さまのことについては知っておく必要があります。
阿弥陀さまも最初から仏さまだったのではありません。
厳しい修行の末覚りを開き、阿弥陀仏という仏になられたのです。
ですから当然覚りを開く前は阿弥陀仏ではありませんでした。
仏になるために厳しい修行をなさる方を菩薩と申します。
観音菩薩さまや勢至菩薩さま、地蔵菩薩さまなどは有名ですが、いずれの菩薩さまもまだ仏にはなっておられません。
阿弥陀さまも修業時代は「法蔵菩薩」というお名前でした。
法蔵菩薩さまは修行を始めるにあたって、すべての者を救いたいという思いのもと、四十八の誓いを建てられました。
その一々には「もし私が仏になったならば、○○をしよう。もしそれができないならば私は仏にはならない!」という強い決意が示されています。
政治家の公約に似ていますが、政治家の公約は守られないことも多くあります。
しかし菩薩の誓いに「それができないならば私は仏にならない」とあれば、できなかったら仏になれないのです。
これから修行をしようという時に強い決意をしてから修行に入るのです。
法蔵菩薩さまは「もし仏になったならばこんな世界を造ろう」、「その世界はこんな世界にしよう」、「その世界にはこんな者を招こう」と細かく設定されます。
これを「仏が昔仏になる前の菩薩時代に建てた願」という意味で本願と申します。
「かつての願」だから「本願」なのです。
京都には浄土真宗の本山で本願寺というお寺があります。
本願寺の「本願」という言葉は、この仏がかつて誓った願のことです。
相撲の技が四十八手あるとか、柔道の四十八手などというのは四十八願からきています。
四十八の阿弥陀様の本願の第十八番目の願を念仏往生の願といいます。
「もし私が仏になったならば、私が造った世界に来たいと願い、私を信じて私の名前を呼ぶ者をその世界に迎え取ろう。それができないならば私は仏にならない」という誓いです。
この十八という数字は後に歌舞伎の十八番の数字の由来となり、カラオケの得意曲を十八番と呼ぶようになります。
法蔵菩薩さまは本願を建てた後、長い間厳しい修行に耐えてとうとう仏になられました。
それが阿弥陀仏です。
「もし○○ができければ仏にならない」と誓われているのにちゃんと仏になられたとお経には記されています。
ということはすべての本願は達成されたということを示します。
阿弥陀仏が「私の名前を呼ぶならば私の世界に迎えとろう」とおっしゃるのですから、私たちは阿弥陀様の名前を呼べばいいのです。それが「南無阿弥陀仏」です。「南無」は「助け給え」ですから、「南無阿弥陀仏」は「阿弥陀様助け給え」を意味します。
以上を踏まえて本文を見てまいります。
「一々の願の終わりに、「もし爾らずば正覚をとらじ」と誓い給えり。」
「四十八の本願の一々の願の終わりに、もしできなければ仏にならない、と誓っておられる」
「然るに阿弥陀仏、仏になり給いてよりこのかた、すでに十劫を経給えり」
「しかし阿弥陀さまは仏になってからすでに途方もない長い時間が経っている」
つまりもうとっくに仏になられたということになります。
「当に知るべし、誓願虚しからず」
「阿弥陀仏の四十八の誓いの言葉はそら言ではありません」
「然れば衆生の称念する者、一人も虚しからず往生することを得」
「だから衆生の中で南無阿弥陀仏と称える者は一人残らず往生することができる」
「もし一人でも往生したいと願って南無阿弥陀仏と称えているのに一人でも往生できない者があれば、阿弥陀仏がほとけになられたこと自体を疑わねばなりません」
「三宝滅尽の時なりといえども、一念すればなお往生す」
次にその阿弥陀様の本願がどれぐらいの未来まで効力を発揮できるかについて説かれています。
「仏教が滅びた後でも念仏を称えれば往生できる」と説かれます。
遠く未来まで念仏を称える者は救われることが約束されています。
これは無量寿経というお経に記されていることです。
「五逆深重の人なりといえども、十念すれば往生す」
次は、悪人でも救うというけれども、どれぐらいの悪人を救うかが説かれています。
親を殺すなどの極悪な行いを五逆といい、仏教では五逆の罪人は地獄の中でも無間地獄という最悪の地獄に堕ちて永く苦しむとされます。
しかし、「五逆の罪人でも臨終間際に念仏との縁を得て念仏を称えるならば救われる」といいます。
これは観無量寿経というお経に記されています。
「いかに況んや三宝の世に生まれて五逆を造らざる我ら、弥陀の名号を称えんに、往生疑うべからず」
仏教が滅びた後の者でも念仏を称えれば往生できるのに、「私たちはまだ仏教がある時代に生まれているじゃないか。」
そして五逆という最悪の罪人でも救われるというけれども、「私たちは罪深いといっても五逆を造るほどの悪人ではないではないか」
だから「お念仏を称えて極楽へ往生することには疑う余地はない」のです。
「今この願に遇えることは、実にこれおぼろげの縁にあらず。よくよく悦び思し召すべし」
私たちは仏教と出会い、念仏の教えと出会ったことを偶然だと思い、当たり前に思っていますが、無量寿経にはこの縁がいかに大変なことなのかが説かれます。仏教と出会うことができる人というのは、全く記憶にはないけれども前世に相当な善いことをしたというのです。生まれ変わり死に変わりする中で、全く覚えていないけれどもかなりの善いことをしたのだと書かれています。
更に念仏の教えを信じる人はどういう人かというと、前世のどこかで仏様と逢ったことがある人なのだそうです。
私はこのように説かれていることに気づいたとき、鳥肌が立ちました。
仏さまと逢った覚えはないけれども、今阿弥陀さまを信じ、お念仏を称えることができるのは前世のどこかで仏さまと逢ったことが縁となって繋がっているというのです。
しかしよくよく考えてみると、その仏さまと逢った時に仏さまの説かれる教えに従っておれば、とっくに覚りを開くなり極楽へ往生していたはずです。
しかし未だに迷いの世界である人間に生まれているということは、仏さまと逢ったにも関わらずそのみ教えを信じることができなかったということです。
なんということでしょう。
かつて仏と逢うまでの強烈な縁にありながら背いた私ですが、そこからコツコツと善い行いを積み重ねて今またお念仏の教えと出会ったのです。
今度こそ信じて称えなければなりません。もう二度と同じ失敗をくり返してはなりません。
「たといまた遇うといえども、もし信ぜざれば遇わざるがごとし。」
「たとえお念仏の教えと遇っても、信じていなければ遇っていないのと同じことだ」
仏教という言葉やお念仏という言葉は日本全国多くの人が知っています。
知恩院に観光で来られる方もたくさんいます。
でもだからといって、仏教のみ教えを信じお念仏のみ教えを信じているかといえば、そういう人は極稀でしょう。
法然上人は別のご法語で「称えていなければ信じていないのと同じである」ともおっしゃっています。
とても厳しいようですが、よく考えてみますと当たり前のことです。
「今深くこの願を信ぜさせ給えり。往生疑い思し召すべからず」
「今あなたは深くこのお念仏の教え、本願を信じていますね。極楽への往生を疑ってはなりません」
「必ず必ず二心なく、よくよくお念仏候うて、このたび生死を離れ、極楽に生まれさせ給うべし」
「どうかあちこちの信仰に振り回されることなくしっかりとお念仏を称えて、このたびこそは迷いの世界を離れて極楽浄土へ往生させていただきましょう」
信仰がある程度進むと、かえって迷うこともあるやもしれません。他の信仰も有り難く感じることもあるかもしれません。しかしそのようにフラフラしていてはどっちつかず
で結局迷い、逆戻りする因となります。
だから「二心なく」なのです。
お念仏のみ教え一筋にいきましょうねと法然上人はお説きくださっているのです。
後篇第十二章 二河白道
(本文)
昔の太子は万里の波を凌ぎて、竜王の如意宝珠(にょいほうじゅ)を得給えり。今の我らは二河(にが)の水火を分けて弥陀本願の宝珠を得たり。彼は竜神の悔いしがために奪われ、これは異学異見のために奪わる。彼は貝の殻をもて大海を汲みしかば、六欲四禅(ろくよくしぜん)の諸天来たりて同じく汲みき。これは信の手をもて疑謗(ぎぼう)の難を汲まば、六方恒沙(ろっぽうごうじゃ)の諸仏来たりて汲みし給うべし。
(現代語訳)
その昔、〔印度の波羅奈国の〕大施太子は、遙か遠い波路をくぐり抜け、龍王が持つ、あらゆる願いがかなう宝玉を手にしましたが、今の私たちは〔貪りと憎しみという〕水火の二河に分け入り、阿弥陀仏の本願という宝玉を得たのです。
龍王の宝玉は、龍神たちが惜しんだために奪い返されましたが、本願という宝玉は、学説や見解の異なる者によって奪われるのです。
太子が貝殻で大海の水を汲み干そうとしたところ、六欲、四禅の神々が来て、ともに水を汲み出しました。
私たちが信心の手で〔他宗の人の〕疑いや謗りという困難を汲み出すならば、六方の、ガンジス河の砂の数ほどの諸仏が来て、味方して下さるでしょう。(総本山知恩院布教師会刊『法然上人のお言葉』)
(解説)
この御法語は、二つのお話を比較しながら説かれたもので、その二つの話を知らないと何のことやらさっぱり分からないでしょう。
ですから前提となる二つのお話をまずご紹介いたします。
一つ目は『賢愚経』というお経にあるお話です。
昔インドの波羅奈国という国に大施太子という方がおられました。
大施太子は自ら治める国にいる貧しい人々に財産からずっと施しを与えていました。
しかし財産はどんどん減っていくけれども貧しい人々は減っていきません。
どうすればよいか考えていると、竜宮の如意宝珠のことを知ります。
海底にある竜宮に竜王がおり、その髻に如意宝珠という立派な美しい玉が飾られている。その如意宝珠を手に入れれば金銀財宝は思いのままに手に入るといいます。
如意宝珠があれば貧しい人々を救うことができると、大施太子は勇んで海の中に入り、竜宮へ行きます。
竜宮で竜王と面会し、如意宝珠を譲ってくれと懇願します。
竜宮は大施太子の志にいたく感動して、如意宝珠を譲ってくれることになりました。
竜王は帰りの道中に危険があってはいけないと竜神を大施太子のお供につけてくれました。
ところが竜神達は大施太子のようなどこの馬の骨かもわからない者に竜宮の宝である如意宝珠を持って行かれることをよしとしませんでした。
そこで大施太子を騙して、「竜宮の宝である如意宝珠をもう見ることができないので、最後一目見せてください」と太子に頼み、太子が差し出したとたん、竜神達は如意宝珠を奪って逃げていきました。
大施太子は慌てて追いかけますが、追いつきません。
困り果てた大施太子は竜神達に言います。
「如意宝珠を返さないというならば、貝殻でもって海の水を汲み尽くしてしまうぞ」と。「そんなことができるものか。一生掛かってもできるわけがない」と竜神達は笑います。大施太子は「一生掛かってできなければ、何度生まれ変わっても汲み尽くしてみせる。
そして貧しい人々を救うのだ」と一人で水を汲み始めます。
ところがそこに天の神々が大施太子の志に感激して降りてきました。
無数の神々が同じく貝の殻でもって海水を汲み始めたところ、みるみる海水は減っていき、とうとう竜宮の甍が見えてきました。
竜神達は慌てて、奪った如意宝珠を大施太子に返します。
その如意宝珠の力で、大施太子は多くの貧しい人々を救ったというお話です。
もう一つは二河白道という譬え話です。
浄土宗の高祖、唐の善導大師が私たちが極楽浄土への往生を願う心を細く白い道に譬えてくださいました。
旅人が一人行く当てもなく暗い霧の中を彷徨っていました。
そこに盗賊が現れ、旅人は逃げます。
さらに猛獣たちが襲いかかります。
旅人は必死で西へ西へと逃げます。
ようやく盗賊や猛獣から離れたと思ったその時、突然目の前に大きな河が現れます。
北は逆巻く水の河、南は燃えたぎる火の河です。
河は南北に際限なく続いています。
後ろからは盗賊や猛獣が迫ってきます。
しかし前の河をよく見ると、火の河と水の河の間に一本の細い道が見えます。
わずか四・五寸といいますから、12センチ~15センチの細い細い道です。
川の幅は約百歩(ぶ)。
善導大師の時代一歩は今の約1.56メートルですから、百歩は約156メートルです。
道の細さを考えると、相当遠く感じる距離でしょう。
その道を水が洗い、火が被るのです。
そんな状況では、道があるといってもとても向こう岸まで渡りきることができそうにありません。
旅人はどうするか。
前に進むも立ち止まるも後ろに戻るもすべて死が待っています。
当に万事休すの状態です。
そこに向こう岸から声が聞こえます。
「大丈夫だ、渡って来いよ。必ず渡りきることができるであろう」
後ろからも声が聞こえます。
「向こう岸からの声を信じて渡れよ。大丈夫だから。必ず助かるから」
その声を頼りに旅人は一歩一歩白道を渡ります。
しかし何歩か歩いた時に後ろから別の声が聞こえます。
「そんな道渡ったら危ないぞ。戻ってこいよ」
旅人は迷います。
「そうだな。とても渡りきることなんてできないな。後ろから声をかけてくれている人は良さそうな人だな。助けてくれるかも知れない」
そこにまた前から先ほどの声が聞こえます。
「大丈夫だ。必ず渡れるから。大丈夫だ。大丈夫だ」
そして後ろからも先ほどと同じ励ましの声が聞こえます。
「向こう岸の声を信じて行けよ。大丈夫だ。大丈夫だ」
旅人は再び意を決して向こう岸に向かい、無事に渡って平和に暮らしました。
この譬えを「二河白道の譬え」と申します。
これは譬喩ですから、譬えているものを説明する必要があります。
まず旅人は私たち。暗い霧は私たちの自分ばかりを生かそう、生かそうという自分中心の心です。
そんな煩悩の中で人生に迷っている私たちです。
そこに現れた盗賊は私たちの感覚器官です。
目に見るものによって、食欲や性欲が湧いてくる。
聞くことによって人を偏見の目で見たり、憎しみを抱いたりします。
臭うことによって、必要以上に食欲が増し、際限がないのです。
味わうことによってまた欲しくなってしまう。
そして一瞬一瞬考えることはろくなことがありません。
そういった観覚器官によって煩悩は更に膨らんでいきます。
猛獣は私たちの疑い心や高慢な心です。
正しい教えを受けても信じようとせず、また自分を上にして教えを判定しようとする、救われがたい心です。
突然目の前に現れた河。
水の河は私たちの貪りの心を表します。
欲しい物が手に入ってもまた次の物が欲しくなる。
火の河は瞋りの心です。
自分の思い通りにならないと腹を立てる私たちの怒りの心。
間の白道は極楽へ往きたいという心。
極楽往生を願う心です。
それはとてもか細い心です。
貪りの水に流され、瞋りの火に燃やされそうな弱い心です。
ただ、たった一人きりで渡るのではありません。
たった一人であったならば渡りきることはできないでしょう。
向こう岸からの声があります。
後ろからの励ましの声があります。
向こう岸から「来いよ」と言ってくれる声は阿弥陀さまの声です。
後ろから「行けよ」と言ってくださる声はお釈迦さまの声です。
また後ろから聞こえる「帰ってこいよ」の声は他の信仰の人です。
せっかく極楽へ往生しようと思っているのに、それを邪魔する誘惑です。
しかし前からの「来い」と後ろからの「往け」の声に励まされてお念仏を称えて往けば、間違いなく向こう岸、西方極楽浄土へ往生し、先に往生した方々と手に手を取り合って再会し、幸せに過ごすことができるのです。
以上が二河白道の譬えの意味するところです。
大施太子の話と二河白道の話をまずご紹介しました。
これでようやく御法語に入ることができます。
「昔の太子は、万里の波を凌ぎて竜王の如意宝珠を得給えり」
「大施太子は、遙か遠い波をくぐり抜けて竜王が持つ如意宝珠を手に入れた」
「今の我らは二河の水火を分けて弥陀本願の宝珠を得たり」
「今の私たちは水と火の二つの河を分け入って、弥陀本願の宝珠を手に入れた」
「彼は竜神の悔いしがために奪われ、此は異学異見のために奪わる」
「如意宝珠は竜神達が悔しがったために奪われたが、弥陀本願は違った考え方や信仰の人によって奪われる。」
「彼は貝の殻をもて大海を汲みしかば、六欲四禅の諸天、来たりて同じく汲みき。」
「大施太子が貝の殻でもって海の水を汲もうとしたら、天の神々が降りてきて一緒に水を汲み出した」
「此は信の手をもて疑謗の難を汲まば、六方恒沙の諸仏来たりて与し給うべし」
「私たちが信心の手で、違う見解や違う信仰の人達からの疑いや謗りを汲むなら、東西南北上下、つまりあらゆるところの、ガンジス川の砂の数ほどたくさんの仏様方がやってきて、疑いを晴らしてくださるだろう」
私たちは今まで自分の経験と自分の考えだけで生きてきました。
しかし今お念仏のみ教えと出会いました。
「そうか、ありがたいな」と思って一歩二歩と進もうとします。
そうしますと素直な心で歩みますから、あらゆることを素直に聞こうとします。そこに声が聞こえる。
後ろからの誘惑の声です。
「帰ってこいよ。危ないぞ」この声はお念仏と異なった信仰の人の声です。
「極楽なんて本当にあると思ってるの?あるはずないじゃないか」という無神論の人もそこに含まれるでしょう。
「念仏なんて称えると地獄に堕ちるぞ」という新宗教の人の声もそうです。
もしかしたら一人一人の声を聞けばそれなりに納得できるのかも知れません。
でも私たちは今お念仏の教えを漸く信じて一歩二歩と進み始めたところです。
一一の話を聞いて、「なるほど。一理あるな」などと納得していると、一歩も進めません。
前からは「来い」と阿弥陀様が言って下さっているんです。
後ろからはお釈迦様が「往け」と言って下さっています。
誘惑の声は所詮人間の声、凡夫の声です。
「来い」と「往け」は凡夫の声ではありません。
仏の声です。
お念仏を称えていても貪りや瞋りの煩悩は湧いてきます。
疑いの心も出てくるでしょう。
しかし「仏様が示してくださり、間違いないと言って下さっている教えなんだ」と信じ、そのことのみを信じて往くのです。
これが二河白道の譬えです。
まずは自分から進んで疑いを晴らそうとしなくてはなりません。
自分から疑いの心を大きくしたり、人からの心ない言葉に惑わされていてはなりません。そのためには何よりもお念仏を続けることです。
疑いが湧いてこようが、人から何を言われようがお念仏を続けることです。
阿弥陀さまが、お釈迦さまが、あらゆる諸仏がみんな力を貸してくださって、苦しみ多き娑婆世界にあっては間違った道に進まないようにお守りくださり、幸せをつかめるように導いてくださるのです。