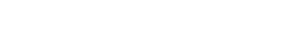前篇第十八章 自身安穏
(原文)
現世(げんぜ)を過(す)ぐべきようは、念仏の申されん方(かた)によりて過(す)ぐべし。念仏の障(さわ)りになりぬべからんことをば厭(いと)い捨(す)つべし。一所(いっしょ)にて申(もう)されずば修行(しゅぎょう)して申すべし。修行(しゅぎょう)して申されずば一所(いっしょ)に住(じゅう)して申すべし。聖(ひじり)て申されずば在家(ぜいけ)になりて申すべし。在家(ざいけ)にて申されずば遁世(とんせ)して申すべし。一人籠(こ)もり居て申されずば同行(どうぎょう)と共行(ぐうぎょう)して申すべし。共行(ぐうぎょう)して申されずば一人籠(こ)もり居て申すべし。衣食(えじき)かなわずして申されずば他人に助けられて申すべし。他人の助けにて申されずば自力にて申すべし。妻子も従類(じゅうるい)も自身助けられて念仏申さんためなり。念仏の障(さわ)りになるべくば、ゆめゆめ持つべからず。所知所領(しょちしょりょう)も念仏の助業(じょごう)ならば大切なり。妨げにならば持つべからず。総じてこれを言わば、自身安穏(あんのん)にして念仏往生を遂(と)げんがためには、何事も皆念仏の助業(じょごう)なり。三途(さんず)に還(かえ)るべきことをする身をだにも捨(す)て難(がた)ければ、顧(かえり)み育(はぐく)むぞかし。まして往生すべき念仏申さん身をば、いかにも育みもてなすべし。念仏の助業(じょごう)ならずして、今生(こんじょう)のために身を貪求(とんぐ)するは、三悪道(さんなくどう)の業(ごう)となる。往生極楽のために身を貪求(とんぐ)するは、往生の助業(じょごう)となるなり。
(現代語訳)
この世の過ごし方は、念仏を称えやすいようにして過ごすべきです。念仏の妨げになることは厭い捨てるべきです。
同じ場所に留まって称えることができなければ、行脚して称えなさい。行脚して称えることができなければ、同じ場所に留まって称えなさい。出家して称えることができなければ、在家者となって称えなさい。在家者として称えることができなければ、出家して称えなさい。
一人こもって称えることができなければ、仲間と共に称えなさい。(仲間と)共に称えることができなければ、一人こもって称えなさい。生計が立たないために称えることができなければ、他人に支えられて称えなさい。他人に支えられて称えることができなければ、自活して称えなさい。
妻子も一族や家来も、自分が支えられて念仏を称えるためです。念仏の障害になるならば、決して持つべきではありません。領地も、念仏の助けとなるならば大切です。妨げになるならば、持つべきではありません。
これをまとめて言うならば、自身が平穏無事で、念仏による往生を遂げるためには、何事もすべて念仏の助けであります。
たとえ三悪道に舞い戻らねばならない悪業を犯す身であっても、捨てがたいので、心にかけて、守り養うのです。ましてや、往生が叶う念仏を称える身なのですから、ぜひとも守り養い、大切にすべきであります。
念仏の助けとすることなく、この世を楽しむために我が身を愛することは、三悪道へ墜ちる行為となります。極楽往生のために自身を愛することは、往生の助けとなるのです。
(解説)
法然上人にはたくさんのお弟子さんがおられましたが、
その中に禅勝房(ぜんしょうぼう)という方がおられました。
禅勝房様は元々天台宗のお坊さんで、
ながらく学問や仏道修行を積んでこられました。
しかし学問をすればするほどに、
修行をすればするほどにご自身の器が
「とても天台の教えについていけない」
と考えるようになられました。
そこで禅勝房様は今まで積んできた学問も修行も
すべて捨てて法然上人のお念仏の教えに入られました。
法然上人のお念仏の教えは
「自分自身の器をしっかり見つめ、
難しい修行や学問で救われない自分であると正面から見つめて、
自分の力ではなく阿弥陀様の力で救われていく」
という教えです。
法然上人の門下に入ってからの禅勝房様は、
ひたすらお念仏一行に打ち込まれました。
門下の中でも特に
「信心の堅い禅勝房」
と言われるようにまでなりました。
この禅勝房様が法然上人に色々と質問をされ、
法然上人が丁寧にお答えになるという問答が今に伝えられています。
このご法語はその一つです。
このご法語は法然上人がお答えになった部分のみですが、
禅勝房様のご質問は次のようなものです。
「南無阿弥陀仏と称えれば極楽浄土へ往生できるということはよくわかりました。
その上で私達は臨終の時まではどのように過ごせばよろしいでしょうか?」
それに対するお答えが本文です。
「現世を過ぐべきようは念仏の申されん方によりて過ぐべし。
念仏の障りにならんことをば厭い捨つべし」
「この世を過ごすには念仏を申しやすいようにして過ごしなさい。
念仏の邪魔になることを止めてしまいなさい」
ということです。
これは一見なんでもないようですが、
真剣に考えると非常に厳しいお言葉です。
私達は「念仏を申しやすいように」と思ってしていることが
どれほどあるでしょうか?
お仏壇をお祀りすることと、お墓参りをすること、
お寺の法要にお参りなさることぐらいではないでしょうか。
逆に「これを止めればもう少しお念仏を称えることができる」
ということはたくさんあるのではないでしょうか。
ですから、このお言葉を真剣に受け止めると
私達の生活自体を見直さなくてはならないということになります。
これは禅勝房という信心が堅いことで名高いお弟子に対して
おっしゃったお言葉ですので、特に厳しいのでしょう。
これを私達がどのように受け止めていくかを考えねばなりません。
「一所にて申されずば修行して申すべし。修行して申されずば一所に住して申すべし」
「一カ所に定住してお念仏を申すことができなければ、あちこちを旅してお念仏を申しなさい」
昔の坊さんは定住する人と旅する人がおりました。
どちらがよいというわけではないけれども、
お念仏を申しやすいかどうかという価値観で選びなさいということです。
「聖て申されずば在家になりて申すべし。在家にて申されずば遁世して申すべし。」
「坊さんになっているのにお念仏を申すことができないならば、坊さんを辞めて在家になって申しなさい。
在家であって申すことができないならば、坊さんになって申しなさい」
必ずしも坊さんになった方がお念仏を申しやすいとは限らないのです。
在家であった方が申しやすかったらそうすればいいということです。
「一人籠もり居て申されずば同行と共行して申すべし。共行して申されずば一人籠もり居て申すべし。」
「一人っきりで念仏を申すことができないならば、仲間と集まって申しなさい。
仲間と集まって申すことができないならば、一人で申しなさい。」
法輪寺では年に二度念仏会を行っています。
大抵の人にとっては一人でお念仏を申すよりも仲間と集まって申す方がやりやすいと思います。
念仏会はそのために行っています。
しかし特にお念仏を申し慣れている方の中には、一人で申す方がよいという方もおられます。
他人と一緒だと気が散る、他人のペースに惑わされるとやりにくいという方も少なからずおられます。
そういう方は一人で申せばいいのです。
一人でも仲間と一緒でも「お念仏を申しやすい方」を選びなさいということです。
「衣食かなわずして申されずば他人に助けられて申すべし。他人に助けられて申されずば自力にて申すべし。」
「生計が立てられないからお念仏どころではないと言うならば、他人に生活の援助をしてもらって申しなさい。
他人の援助を受けていると気が引けて申しにくいというのであれば、自分の力で生計を立てて申しなさい。」
「念仏念仏と言うけれど、生活もできないのに念仏どころではない!」という人がいても、「それなら人に援助してもらってでも念仏はできるぞ」ということです。
念仏はどんな場合でもできるのです。
極楽へ往生するということの大切さをしっかりと認識できれば、この世を生きるよりも大切なことだということが理解できるでしょう。
しかし厳しいですね。
次は益々厳しいです。
「妻子も従類も自身助けられて念仏申さんためなり。念仏の障りになるべくばゆめゆめ持つべからず」
「妻子も親戚も自分自身がそういう方々に助けられて念仏申してこそありがたいのですよ。もし念仏の邪魔になるのでしたら必要ないのです」
非常に厳しいですね。
結婚さえもお念仏を申しやすいかどうかという基準で決めなさいということです。
私は結婚前からこのご法語を知っていましたので、少なからず考えました。
普通に考えると結婚すると自分の時間は少なくなりますので、念仏も減ってしまうのではないかと思いました。
でも縁が深かったので結婚しました。
結婚したからにはお念仏が減ったというわけにはいきませんので、益々称えるようになりました。
結果的に私にとっては結婚した方がお念仏を申しやすかったということになります。
「総じてこれを言わば自身安穏にして念仏往生を遂げんがためには、何事もみな念仏の助業なり」
「まとめてこれを言うならば、自分自身が安らかに念仏を申して往生を遂げるためにはすべてをお念仏の助けとすべきですよ」
助業とはお念仏を申しやすいようにする行いをいいます。
例えばお経を読むこともそれだけでは大した功徳はありませんが、
お経の中にお念仏を称えれば必ず往生できるということが
しっかりと記されていますので、お経を読むとお念仏を称えやすくなります。
また、お供え物などもただ黙って供えるだけでは功徳はありません。
「阿弥陀様、ご先祖様どうぞ」という思いでお供えし、「いつか極楽へ往生したいものだ」と思いを馳せてお念仏を称えてこそ大切なこととなるのです。
私は歩いているときにも歩くリズムでお念仏を称えています。
ということは私にとりましては歩くことがお念仏の助けとなるのです。
お檀家さんの中にお念仏を称えつつ洗い物をしていますという方もおられます。
その方にとりましては洗い物がお念仏の助けとなります。
お念仏を称えつつお風呂に入るという方にとりましては
お風呂に入ることがお念仏の助けとなるのです。
「三途に還るべきことをする身をだにも捨て難ければ顧みはぐくむぞかし。
まして往生すべき念仏申さん身をば、いかにもはぐくみもてなすべし」
三途とは地獄、餓鬼、畜生の三つを言います。
三途の川と言いますが、あれは地獄、餓鬼、畜生行きの川です。
お葬式に行きますと、葬儀屋さんのアナウンスで「享年○才をもちまして極楽浄土へとお還りになりました」というのをお聞きになったことがあるかも知れません。
しかしこれは言葉としてはおかしいのです。
なぜなら、私達は極楽から来たわけではありません。
極楽から来て極楽へ還るのであれば、お念仏など必要ないではありませんか。
「お念仏がなければ極楽へなど到底行くことができない私」であるということを忘れてはなりません。
お念仏を称えて、「このたび初めてようやく極楽へ往生するチャンスを得た」私達です。
「極楽へ還るどころか三途に還るしかないようなことばかりしかしていないではないか」という法然上人のご指摘です。
「三途に還るようなことばかりをしているこんな我が身でも決して要らないわけではなく、捨てがたいものだから大事にするであろう。
ましてやこれから往生しようとお念仏を称える身であるならば、益々大事にしなさいよ」ということです。
「念仏の助業ならずして今生のために身を貪求するは三悪道の業となる。
往生極楽のために自身を貪求するは往生の助業となるなり」
「念仏の助けにもならないのにこの世を生きるためだけに自分自身を大事にするのは所詮地獄、餓鬼、畜生行きの行いを重ねているだけですよ。
でも往生極楽のために自分自身を大切にするのは往生の助けとなるのですよ。」
という内容です。
これは禅勝房様に宛てられたもので、非常に厳しいことが書かれています。
だからと言って、「こりゃ無理だ」と言ってしまうのは少し違うような気がします。
「これほどに法然上人が重ねて勧めて下さっているのに、自分はできていないなあ」ということをやはり自覚すべきだと思います。
これは私にとっては座右の言葉というべきで、
いつもこのご法語を思い出して、
「お念仏中心の生活になっていないなあ」と反省しています。
どうかみなさんも進むべき方向を示唆して下さっていると
ご理解いただきたいと思います。
実際に法然上人から直接お言葉を授かった禅勝房様は、
これを真摯に受け止めて
「自分にとっては坊さんを辞めた方がお念仏が称え易いと考えられ、
故郷の静岡に帰って大工をしながらお念仏を称えておられました。
法然上人の滅後15年ほど経った時に、法然上人の有力なお弟子の一人、
隆寛律師という方がご自身のお弟子を連れて、
静岡辺りを通られました。
そこで「この辺りに禅勝房様がおられるはずだ。
久しぶりにお会いして法然上人の思い出話などもしたいものだ。」
と思われ、訪ねて行かれました。
「この辺りに法然上人のお弟子で禅勝房という方がおられるはずなのですが…」とあちこちで尋ねても「そんな人は知らんなあ」というご返事です。
おかしいと思っていると、
「そんな偉い人は知らないが、大工の禅勝という取るに足りない者ならいるぞ。」と言うことを聞きます。
隆寛律師は念のためにその大工の禅勝さんへ手紙を書かれます。
それをご覧になった禅勝房様は喜んで隆寛律師の元へ飛んできました。
お二人は懐かしい法然上人の思い出話を堪能されました。
周りの人たちは今まで半ば馬鹿にしていた禅勝房様が
法然上人のお弟子であったことを知って驚きます。
隆寛律師は「禅勝房さん、あなたはお念仏が申しやすくなるように、坊さんを辞めて大工さんになられたのでしょう。
でも法然上人はおっしゃっていましたよ。
禅勝房さんは人々に教えを広めるべき人だと」
隆寛律師に説得され、禅勝房様は再び僧侶となられました。
隆寛律師のお弟子は別れ際に、
「禅勝房様、私にもお言葉を頂戴しとうございます。」と頼みました。
禅勝房様はしばらくお考えになり、
「お念仏が癖づくように工夫することが大切ですよ。」
とおっしゃったといいます。
正にこのご法語の内容ですね。
お念仏は「南無阿弥陀仏」と称えるだけですから、
やる気さえあれば誰でもできます。
でも続けることは非常に難しいのです。
ですから色々と工夫して癖づけるのです。
癖づけば何ということもなく称えることができるでしょう。
有り難いお示しです。
前篇第十七章 易行往生
(原文)
念仏を申し候(そうろう)ことはようようの義(ぎ)候(そうら)えども、ただ六字(ろくじ)を称(とな)うる中(うち)に、一切の行(ぎょう)は収まり候(そうろう)なり。心には本願(ほんがん)を頼み、口には名号(みょうごう)を称(とな)え、手には念珠(ねんじゅ)をとるばかりなり。常に心を掛くるが極めたる決定(けつじょう)往生の業(ごう)にて候(そうろう)なり。念仏の行(ぎょう)は、元より行住坐臥(ぎょうじゅうざが)時処諸縁(じしょしょえん)を嫌わず、身口(しんく)の不浄を嫌わぬ行(ぎょう)にて易行(いぎょう)往生と申し候(そうろう)なり。ただし、心を清くして申すを第一の行(ぎょう)と申し候(そうろう)なり。人をも左様(さよう)にお勧め候(そうろう)べし。ゆめゆめこの御心(みこころ)はいよいよ強くならせ給い候(そうろう)べし。
(現代語訳)
念仏を称えることには、様々な意味がありますが、ただ(南無阿弥陀仏の)六字を称える中に、一切の行がおさまっています。心には本願を頼みとして、口には名号を称え、手には数珠を繰るだけです。常に(そのように)心がけることが、必ず極楽往生の叶う、この上ない行であります。
念仏の行は、言うまでもなく、立ち居起き臥しや、時、所、状況を選ばず、身と口との不浄を問わない行であって、(それによるのを)易しい行による往生と申すのです。
ただし、心を浄くして称える念仏を、最上の行と申します。他の人にも、そのようにお勧め下さい。つとめてこの御心を、よりいっそう強くなさって下さいますように。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会)
(解説)
法然上人のお弟子、信者の層の幅は多岐にわたります。
天皇や貴族から何と泥棒までいます。
もちろん説かれた教えが念仏という誰もが救われるみ教えであるということもありますが、法然上人のお人柄の懐の広さがよくわかります。
その中でも武士が目立ちます。
武士というと多く身分が高いというイメージを持ちますが、鎌倉時代の武士と江戸時代の武士では全く違います。
鎌倉時代の武士は野蛮人と見られていたようです。
教養もありません。
武勲を挙げるということ、つまり出世するためには殺生を重ねなくてはなりません。
武士だってできれば殺生なんてしたくありません。
そしてそれが罪だということは分かっています。
でもせざるを得ない。
もう救いを諦めるしかなかったのです。
そこに法然上人は、「その生業をやめることができるのであればやめなさい。しかしやめることができなければ、その身そのままでお念仏を称えなさい。必ず救われますよ。」とお説き下さいました。
こうして多くの鎌倉武士が法然上人に帰依し、念仏者となっていきました。
その鎌倉武士の頂点は源頼朝公です。
その奥さんは北条政子さま。
「尼将軍」などとも呼ばれ、NHKの大河ドラマでも何度も取り上げられてきましたのでご存じでしょう。
北条政子さまは臨済宗の信仰を持っていました。
しかし部下である御家人の中に多くの念仏者がいたので、念仏の教えも知っておかねばということも思われたのかも知れません。
そういう思いで法然上人に手紙を送られました。
それに対して法然上人がご返事を書かれました。
その一部分がこのご法語です。
「念仏を申し候事は、ようようの義候らえども、ただ六字を称うる中に一切の行はおさまり候なり。」
「念仏を申すということには、三心や四修などの色んな義があるけれども、ただ南無阿弥陀仏という六文字を称えるという中にすべての行の功徳が収まっています。」
法然上人は常に「極楽浄土へ往くには、ただ南無阿弥陀仏と称えるだけ」とお示しくださいます。
その一方「誠の心を持って」「深く信じる心をもって」「極楽へ往きたいと願って」という「三心」や、念仏生活の仕方を示す「四修」などもお説きくださっています。
ただ、これらは細かく分析して色んな角度から説いてくださったもので、その一々を常に気にしないといけないのではありません。
ただ「南無阿弥陀仏の六字を称える」という行為の中に、すべて収まってくるのです。
そして私達がすべきことは
「心には本願を頼み、口には名号を称え、手には念珠をとるばかりなり」です。
「心には阿弥陀様の本願を頼りにし、阿弥陀様お救い下さいと思って、口には南無阿弥陀仏と称え、手には数珠を繰るだけですよ」ということです。
体の行い、口の行い、心の行いすべてを極楽へ、阿弥陀様へ、念仏へと向けていくのです。
数珠というのは念仏の数を数える道具です。
数を数えるというのは非常に励みになります。
これは間違いのないことです。
例えばダイエットをするにも、体重を量りますよね。
体重を量らないと成果がわからないので努力する気が起こりにくいようです。
食べるものを減らし、運動をして体重を量る。
そうして少しでも減っていると嬉しくなってまた運動する気が起こる。
でもダイエットはある程度まで体重が下がるとその後一旦どれだけやっても減らない時期が来るのだそうです。
そうするとやる気が失せてきます。
そしてダイエットを止めてしまう。
しかしお念仏は称えれば称えるほどに増えていきます。
増えるともう少し、もう少しと益々やろうという気が起こってくるわけです。
私達はお寺へ来てどれだけ有り難い法話を聞いて、お念仏を称える気になっても家に帰ったら「あーおなか空いた、晩ご飯、晩ご飯!」とすっかりスイッチを切り替えてしまいます。
お念仏のスイッチをオンオフしてしまうんですね。
でもそれではいけません。
お念仏生活が底辺にあって、その上で日常の生活ができればありがたいことです。
そのためには放っておいてはいけません。
お念仏が続くように工夫や努力が必要です。
数珠を使うのもその一つです。
私は万歩計を使ってお念仏を数えて、日々の念仏が続くように工夫しております。
色々と工夫をして、極楽へ、阿弥陀様へ、お念仏へと向けていくことが必要です。
ですからご法語はこのように続きます。
「常に心をかくるが極めたる決定往生の業にて候なり」
「常に心を極楽、阿弥陀様、お念仏にかけるのが往生するための究極の行いなのですよ。」ということです。
そして念仏とは決して難しいものではないのですよ、ということが書かれています。
「念仏の行はもとより行住坐臥、時処諸縁をきらわず、身口の不浄をきらわぬ行にて、易行往生と申し候なり」
「念仏の行は元々歩いていても立ち止まっていても座っていても寝転んでいても、できますよ。いつでもどこでもどんな時でも称えることができますよ。そして体や口の汚れ、不浄も嫌わない行であるから、容易く往生できる行であるよというのです。」ということです。
どんな行でも場所を選びます。例えば座禅でしたら、時々電話が掛かってきたり、車の音が聞こえたりする場所ではきません。
ですから曹洞宗のお寺は多く山の中にあります。
でもお念仏は歩きながらでもできますし、たとえ雑踏の中でもできます。
もちろん大きな声では称えられませんが、私は電車の中でも称えます。
隣の人が気づかないほどの声でいつも称えます。
そんなことができる行は念仏以外にありません。
また、神社や大きなお寺に行きますと柄杓で手を洗い、口を洗ってから神前、仏前に進みます。
あるいはお香を焚いて、時にはお香を跨いで、体にお香を塗ったりして道場に入ります。
しかし念仏はそれすらも必要ないのです。
その身そのままでできる唯一の行なのです。
これはとても有り難いことです。
いつも正座をしてビシッと背筋を伸ばして念仏を称えよと言われたら、足が痛くなったり病気になったらできなくなってしまいます。
私達は好む好まざるにかかわらず、老いていきますし病気にもなります。
誰一人寝たきりになりたい人はいないのに、なってしまうこともあります。
でもそうなったらそうなったままで称えることができます。
起きられなかったら寝転んだままで、大きな声で称えられなかったら小さな声で称えることができるというのは本当に有り難いことです。
阿弥陀様は私達の弱いところをとことんお考え下さって、私達が置かれた状況のままでできる行を用意して下さったのです。
もちろんやる気がなかったらできません。
極楽へ往生したくない人には念仏を称えることは難しいでしょう。
しかし往生したいと思う人、やろうと思う人は誰でもできるという行です。
やろうと思ってもできないことは山ほどあります。やる気はあっても体がついてこない、能力がついてこないということは一杯あります。
念仏は本当に誰でもできます。
あとはこちら次第です。
そして次の一文です。
「但し、心を清くして申すを第一の行と申し候なり」
「色々と理屈もあるけれども、それは一旦おいて、但し、心を清くしてお念仏を申すのが第一ですよ。」ということです。
心を清くするといっても心を清くするのは非常に難しいことです。
私達は中々心が清くなりません。煩悩だらけの凡夫です。
心は汚れ、散り乱れています。
それを清くせよと言われたらとてもできません。
ここではそのようなことをいうのではありません。
ただ純粋に「阿弥陀様お救いください」という思いで南無阿弥陀仏と称えるだけです。
それだけなのです。
「人をも左様にお勧め候うべし。ゆめゆめこの御心はいよいよ強くならせ給いそうろうべし。」
「北条政子さま、あなたのようなお立場の方は人にもそのようにお勧めください。どうぞどうぞこの御心を益々強くお持ち下さいよ」ということです。
臨済宗の信仰をお持ちの北条政子さんに対して、浄土宗の大きな特長をお伝え下さっている有り難いお言葉です。
前篇第十六章 他力往生
(原文)
念仏の数を多く申す者をば、自力を励むという事、これまたものも覚えず浅ましき僻事(ひがごと)なり。ただ一念二念を称うとも、自力の心ならん人は自力の念仏とすべし。千遍万遍を称え、百日千日夜昼励み勤むとも、偏(ひとえ)に願力(がんりき)を頼み、他力を仰(あお)ぎたらん人の念仏は、声々念々(しょうしょうねんねん)、しかしながら、他力の念仏にてあるべし。されば、三心(さんじん)を起こしたる人の念仏は、日々夜々(にちにちやや)、時々刻々(じじこくこく)に称うれども、しかしながら願力を仰ぎ、他力を頼みたる心にて称えいたれば、かけてもふれても、自力の念仏とはいうべからず。
(現代語訳)
「念仏の数を多く称えるのは自力を励む人だ」と言うこと、これまた道理を外れ、あきれる程の心得違いです。わずか一念二念を称えても、自力の心構えである人(の念仏)は、自力の念仏とすべきであります。
千遍万遍を称え、百日千日、昼夜に励み努めても、ひたすら(阿弥陀仏の)願力を頼みとし、他力を尊ぶ人の念仏は、一声一声が、そのまま全部他力の念仏であるとすべきです。
それゆえ三心を起こした人の念仏は、毎日毎夜、絶え間なく称えたとしても、それらはすべて願力を尊び、他力を頼みとする心で称えているのですから、決して自力の念仏と言うべきではありません。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
お念仏の教えは「南無阿弥陀仏と称える者を阿弥陀様が救って下さる」という教えです。お念仏を称えてこちらが段々偉くなって救われるのではありません。こちらは自分の力ではどうにも救われない身であるけれども、阿弥陀様の力によって救われるのです。その阿弥陀様の力を「他力」といいます。
一般的に「他力本願」といいますと、「自分は大した努力もせずに他人任せにすること」と、とらえられていますが、本来の意味とは大きく違います。本来は「阿弥陀様の力」のことを限定して「他力」というのです。
自力というのは、自分を磨いて正しい生活をし、難しい修行をして悟りを開く力をいいます。そういうことがとてもできない私達は、他力にすがらなくてはならないのです。
ですから、自力の心で念仏を称えてはなりません。あくまで、阿弥陀様の力、他力を仰いでお念仏をお称えするのです。
ただ他力という言葉に固執するとややこしいことになります。といいますのは、念仏を多く称えるのは自力であるなどということを言う人がいます。
たとえば「お念仏をたくさん称えるのは半自力半他力だ」などという批判です。
法然上人ご在世当時からそういった批判はあったようです。それに対して法然上人が「そうじゃないですよ。」とおっしゃったのが今日のご法語です。
最初から読んで参ります。
「念仏の数を多く申す者をば自力を励むということ、これまたものも覚えず浅ましき僻事なり」「念仏の数を多く申す者のことを、自力を励んでいるという人がいるが、これは物事を知らない浅はかな考えであるぞ」ということです。
「ただ一念二念を称うとも、自力の心ならん人は自力の念仏とすべし」「たった一遍、二遍というわずかな念仏しか称えていないとしても、自力の心で称えていれば自力の念仏となります」
「千遍、一万遍称え、百日、千日夜も昼も念仏に励み勤めたとしても、偏に阿弥陀さまの本願の力を頼りにし、他力を仰ぐ人の念仏は、一声一声ごとがすべて他力の念仏となるでしょう」
「されば三心を起こしたる人の念仏は、日々夜々、時々刻々に称うれども、しかしながら願力を仰ぎ他力を頼みたる心にて称えいたれば、かけてもふれても自力の念仏とは言うべからず」
三心とは、至誠心、深心、回向発願心の三つです。至誠心とは誠の心、深心は深く阿弥陀さまを信じる心、回向発願心はとにかく極楽へ往きたいと願う心です。この三つの心をもって念仏する者が極楽へ往生するのです。
このように言いますと、非常に難しいですが、「阿弥陀さま、極楽へ往生させて下さい、南無阿弥陀仏」と称える念仏がすなわち三心が具わった念仏なのです。
ですから前文を訳しますと、「三心を起こした人の念仏は、昼も夜もずっと称えていて、はたから見たら大変な苦行をしているうように見えても、すべて本願力を仰ぎ、他力に頼る心で称えているのであるから、決して自力の念仏ではありません」となります。
つまり念仏の数が少ないから他力で、念仏の数が多いから自力というわけではないということです。数の多少に関わらず、自力の心で称えれば自力の念仏となるし、他力の心で称えれば他力の念仏となるのです。自力、他力と分けて考えると非常にややこしいですが、つまりは「阿弥陀さま、お救い下さい」という思いで念仏を称える、ただそれだけなのです。
それだけなのに私達は念仏を称えるようになると、他人と比べて「あの人より私の方が念仏を称えている」と意識し、何となく偉くなったような気になるものです。でも南無阿弥陀仏とは、「阿弥陀さま、助けて下さい!」です。「阿弥陀さま、助けて下さい、阿弥陀さま、助けて下さい!」と称える者が偉いはずがないのです。阿弥陀さまにすがらなくては救われないのですから。そこを勘違いしないようにしなくてはなりません。
救う側は仏です。これは当たり前でありながら、実は理解しにくいことです。
たとえば知恩院の御前様は非常に知識も豊富、経験も豊富、人徳も勝れた方です。その御前様と私を知識や経験、人徳という基準で比べれば雲泥の差があります。しかし、称える念仏は同じです。「阿弥陀さま、助けて下さい。」の念仏です。救って下さるのは阿弥陀さまですから、知識や経験の差は関係ありません。
あくまで救う側は阿弥陀さまなのです。阿弥陀さまの力、つまり他力によって初めて救われるのが私達なのです。
前篇第十五章 信行双修
(原文)
一念十念に往生をすといえばとて、念仏を疎想に申すは信が行を妨ぐるなり。念々不捨者といえばとて、一念を不定に思うは行が信を妨ぐるなり。信をば一念に生まると信じ、行をば一形に励むべし。又一念を不定に思うは、念々の念仏ごとに不信の念仏になるなり。その故は、阿弥陀仏は一念に一度の往生を当ておき給える願なれば、念ごとに往生の業となるなり。
(現代語訳)
「一念や十念でも往生する」と説かれるからといって、念仏をおざなりに称えるのは、(本願への)信心が念仏の行を妨げているのです。「念仏し続けて片時もやめないならば(往生できる)」と解釈されるからといって、「一念では(往生が)不確かだ」と思うのは、(念仏の)行が(本願への)信を妨げているのです。信心については「一念で往生できる」と信じ、行については、生涯続けて励むべきです。
また「一念では(往生が)不確かだ」と思うならば、一声一声の念仏が、それぞれに不信の念仏となります。そのわけは、阿弥陀仏(の本願は)、一念に一度の往生をあてがわれた願なので、念仏するたびにそれが往生のための行いとなるからです。(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
念仏の教えは「阿弥陀様の本願を信じて南無阿弥陀仏と称えれば必ず阿弥陀様が救ってくださる」というみ教えです。そのお念仏の数についてお経には「たとえ十遍の念仏であっても」と記されています。中国の唐の時代にお念仏の教えを完成された善導大師は「十遍の念仏で救われる」というのは「一遍の念仏でも救われる」というこのなのだとおっしゃいます。
そうすると、「それじゃ一遍でいいじゃないか。阿弥陀様の教えを信じてさえいれば、多く称える必要などない。」という人が出てきます。「一念義」といいます。「一度念仏を称えた、その時にはすでに救われているのだ」というのです。
そ れに対して「いやいや、そうではないんだ。念仏は多ければ多いほどいいんだ」と言う人もできてきます。これを「多念義」といいます。
「一念義」は、称えることよりも信じること、「信」を重視します。「多念義」は、「信」よりも「行」を重視します。ですから、「一念義」か「多念義」かという議論は、「信」か「行」かという議論なのです。
法然上人はどのようにおっしゃっているかというと、「信」だけでもなく「行」だけでもない、どちらも必要なんだとおっしゃいます。どちらか片方でよいということではない、車の両輪のように「信」と「行」はお互いを励まし合いながら進んでいくのだとおっしゃいます。それをふまえて本文をお読みします。
「一念十念に往生をすといえばとて、念仏を疎想に申すは信が行をさまたぐるなり」「一遍十遍の念仏で往生するからといって、念仏を称えるのをいい加減にするのは信が行を妨げることになります。」
「念々不捨者といえばとて、一念を不定に思うは行が信をさまたぐるなり」
「念々不捨者」というのは、善導大師のお言葉で、一瞬一瞬に捨てない、つまり「ずっと続けていく」という意味です。ですから、「念仏をずっと続けていくようにと善導大師はおっしゃっているが、一遍の念仏では往生できないと思うのは、行が信を妨げているのですよ」となります。
次の言葉が法然上人の立場を明確に表現しています。「信をば一念に生まると信じて行をば一行に励むべし」「一遍の念仏で往生できるのだと信じてひたすら称えましょう」つまり一遍で往生できるからといって、一遍で終わりではないということです。たった一遍の念仏で往生できるのだから、益々称えましょうということです。
「又一念を不定に思うは念々の念仏ごとに不信の念仏になるなり」「一遍の念仏では往生できないと思うのは、一声一声の念仏がすべて信のない念仏になりますよ。」要は一遍でだめだというのなら、何遍称えてもだめでしょう、だめなものをどれだけ重ねてもだでしょう、というわけです。
「その故は阿弥陀仏は一念に一度の往生をあておき給える願なれば、念ごとに往生の業となるなり」「なぜならば、阿弥陀様は一遍の念仏で救うと願を立ててくださっているのだから、一声一声がどれも往生の業となるのですよ 」というのです。一声で往生なのですから、称える毎に「往生、往生、往生、往生」と往生の業が積み重なっていくのです。
ただ、そもそも十遍の念仏というのは、お経では臨終の時の十念をいいます。『観無量寿経』というお経には、生きている間散々悪いことをしてきた人が、臨終の時に念仏者によって初めて念仏の教えを聞いて、念仏を称えた人の、その称えた数が十遍であったけれども間違いなく往生したとあります。
臨終間際に念仏信仰のある人がお見舞いにやってきて、念仏の教えを伝え「今まで知らなかったけれどもそんなありがたい教えがあったのか」と気づき、南無阿弥陀仏と称えた人は往生するのです。
実際に臨終間際で念仏の教えと出会う人は多くはないと思います。でも私などは、枕経で初めてお会いする人がいます。恐らく今までお念仏を称えてはおられなかったでしょう。そういう人に私は枕経の際に直接話しかけます。「初めまして。法輪寺です。阿弥陀仏という仏様が私たちのために極楽浄土という絶対の幸せの国を作ってくださいました。南無阿弥陀仏と称える者はすべて極楽へと迎えとると言ってくださっています。今まであなたがお念仏を称えてこられたかどうかわかりませんが、どうか今称えてください。声に出して称えることはできないでしょうが、私も家族のみなさんも一緒にお念仏を称えてくださいますので、どうか最後の今、称えてください」と申し上げてお念仏を十遍称えます。それから改めて家族の方にご挨拶をし、打ち合わせをし、正式に枕経のお勤めをします。枕経というのは大事な時です。それが終わって念仏を称えてお通夜を勤めます。親しい人が故人を思って思い出話をするのもよいのかも知れませんが、取り返しのつかない大事な時ですから、やはりお通夜はお念仏を称えて過ごすべきでしょう。そしてお葬式で導師が引導を渡し、十遍の念仏を授けるのです。
信心さえあれば一遍の念仏でもいいなどと言いますが、私達凡夫の信心なんていい加減なものです。「ありがたいな」と思っても、そのまま放っておいたら信心なんてなくなってしまいます。だからやはり念仏を称えなくてはならないのです。ありがたいと思ったら、南無阿弥陀仏と称えるのです。そしてまたありがたいと信心を深めて更にお念仏を称えるのです。
また、「多念義」のように、ただ多く称えればよいと言っても、信心がなければ多く称えることなんてできません。信仰もないのに1万遍念仏を称えるなんてことは、苦痛以外の何者でもないでしょう。
信心を起こし、念仏を称え、また信仰を深める。これが法然上人がお説きくださるお念仏のみ教えです。
前篇第十四章 専修念仏
(原文)
本願の念仏には独り立ちをせさせて助をささぬなり。助というは、知恵をも助にさし、持戒をも助にさし、道心をも助にさし、慈悲をも助にさすなり。善人は善人ながら念仏し、悪人は悪人ながら念仏して、ただ生まれつきのままにて念仏する人を、念仏に助ささぬとはいうなり。さりながら、悪を改め善人となりて念仏せん人は、仏の御心に叶うべし。叶わぬもの故に、とあらんかからんと思いて決定心起こらぬ人は、往生不定の人なるべし。
(現代語訳)
本願の念仏には独立をさせて、助けを差しはさみません。「助け」というのは、智慧をも助けとし、持戒をも助けとし、菩提心をも助けとし、慈悲をも助けとして差しはさむのです。
善人は善人のままで念仏し、悪人は悪人のままで念仏して、ただ生まれつきのままに念仏する人を、「念仏に助けを差しはさまない人」と言うのです。
しかしながら、悪を悔い改め、善人となって念仏する人は、阿弥陀仏の御心に適うでしょう。
(ただし)仏の御心に適わない自分であることから、「ああだろう、こうだろう」と心配して、「必ず往生できる」という思いの起こらない人は、往生の確実でない人なのです。
(解説)
法然上人は色々なお言葉を残されていますが、その中でもしょっちゅう仰っていたお言葉というものがあります。「常に仰せられけるお言葉」と呼ばれるもので、この御法語もその一つです。
まず全体的に申し上げますと、念仏というのはあまりに簡単ですので、何となく頼りなく思われるようです。念仏だけでは物足りないから般若心経も称えた方が功徳があるような気がするのです。しかし念仏は阿弥陀さまがご修行くださったすべての功徳を収め込んでくださった、極楽へ往生するためにはこの上ない行です。私たちが私たちの力で極楽へ往生するのではありません。私たちは極楽浄土への往生を願い、阿弥陀さまがご用意くださったお念仏を称えるだけです。阿弥陀さまのお力によって救われるのです。この阿弥陀さまのお力を他力といいます。いわゆる「他人まかせ」の他力ではありません。本来他力とは、阿弥陀さまのお力を限定していうものです。自分の力ではとても極楽へ往生することなど覚束ない私たちが念仏を称え、阿弥陀さまの力によって初めて往生するのです。どんなに罪深い身でも阿弥陀さまは必ず救って下さいます。そのことを踏まえ、本文を見ていきましょう。
「本願の念仏にはひとりだちをせさせて助をささぬなり。」
「阿弥陀さまの本願であるお念仏は、ひとりだちをしたものであって、補助が必要なものではないのだ。」
ここで助とは何かを具体的に挙げています。
知恵、持戒、道心、慈悲の四つです。私たちは知恵がある人の念仏の方がそうでない人の念仏よりも勝れているように思います。また、戒を守って生活を厳しく整えている人の念仏の方が勝れているように思います。「必ず悟りを開いて人々を救うぞ!」という強い決意を持った人の念仏の方が勝れているように思います。全ての人へ慈しむ人がいたならば、その人の念仏の方がそうでない人の念仏よりも勝れているように思います。しかしそうではありません。私たちは私たちが勝れているから救われるのではないのです。決して勝れた身ではない私たちが、阿弥陀さまの力でのみ救われるのです。
善人は善人のまま、悪人は悪人のまま、ただ生まれつきのままに念仏する人こそ、「念仏に助をささない人」というのです。その身そのままで阿弥陀さまはお救いくださるのです。
しかしこのように言いますと、必ず勘違いする人が出てきます。「念仏を称えれば救われるというなら、どんなに悪いことをしてもいいのか」という人です。もちろんそんなことはありません。本来仏教は「悪いことはやめましょう。善いことをしましょう。」というのが基本です。ただ、私たちには煩悩があるので善い行いがなかなかできません。善い行いができないだけでなく、煩悩による悪い行いが知らず知らずの内にも積み重なっていくのです。だからといって開き直ってはいけません。悪い行いをしたくないのにしてしまうのと、「どうせ悪い行いしかできないのだから、どんどん悪い行いをすればいい」と開き直るのでは大違いです。「悪を改め、善人となって念仏しようという人」が阿弥陀さまの御心に叶う人です。
また逆の勘違いもあります。自分を深く見つめる余りに、「私のような愚かな者は、阿弥陀さまの力でも往生などできない」と仏の力を疑ってしまうのです。私の力ではどうしようもないけれども阿弥陀さまの力は大きいのです。それを信じなくてはなりません。「どうせ私は愚かで、阿弥陀さまの御心になど叶わない」と、ああだこうだ思って往生決定の心が起こらない人は往生できないと書かれています。
阿弥陀さまの力を信じるということは、簡単なようで難しいのですね。こちら側の計らいを捨てて阿弥陀さまにお任せしていくのです。これだけのことをしっかりと信じることは昔から難しかったのでしょう。昔から勘違いする人が多かったのでしょう。だからこそ法然上人は、常に仰せられたのでありましょう。