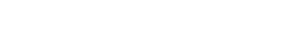前篇第四章 出世本懐
原文
念仏往生の誓願は、平等の慈悲に住(じゅう)して発(お)こし給いたることなれば、人を嫌うことは候わぬなり。仏の御心は、慈悲をもて躰(たい)とすることにて候うなり。されば、観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)には、仏心(ぶっしん)というは大慈悲これなりと説かれて候う。善導和尚(かしょう)この文(もん)を受けて、この平等の慈悲を持てば普(あまね)く一切を接すと、釈し給えり。一切の言(ごん)広くして、漏るる人候うべからず。されば、念仏往生の願はこれ弥陀如来の本地(ほんじ)の誓願なり。余(よ)の種々(しゅじゅ)の行は本地の誓いにあらず。釈迦も世に出(い)で給うことは、弥陀の本願を説かんと思(おぼ)し召す御心にて候らえども、衆生の機縁に随い給う日は、余の種々の行をも説き給うは、これ随機の法なり。仏の自らの御心の底には候わず。されば、念仏は弥陀にも利生(りしょう)の本願、釈迦にも出世の本懐(ほんがい)なり。余の種々の行には似ず候うなり。
現代語訳(『法然上人のおことば』総本山知恩院布教師会発行より)
念仏往生の誓願は、平等の慈悲に立って起こされたものですから、人を分け隔てすることはありません。仏の御心は慈悲そのものであります。だからこそ『観無量寿経』には、「仏の心とは、大慈悲に他ならない」と説かれているのです。
善導和尚はこの一文を受けて、「(阿弥陀仏は)この平等の慈悲によって、あまねく一切(の衆生)を救い取る」と解釈しておられます。「一切」という言葉(の意味)は広いので、もれ落ちる人のいるはずはありません。ですから念仏往生の願は、阿弥陀仏が菩薩であった時の願なのです。念仏以外の様々な修行は、その時の誓いではありません。
釈尊が、この世にお出ましになったのも、阿弥陀仏の本願を説こうとお考えになった御心からでありますが、衆生の能力や状況に合わせられた折には、念仏以外の様々な修行をもお説きになられました。これは(あくまでも)聞き手に応じて説かれた教えであります。釈尊ご自身の御心の奥底から出たものではありません。
ですから、念仏は、阿弥陀仏にとっても衆生に利益を与えるための本願であり、釈尊にとっても世にお出ましになった本意であります。その他の様々な修行とは異なるのです。
解説
法然上人のお弟子に津の戸三郎為守という方がおられます。この御法語は法然上人が津の戸三郎様に送られた手紙の一部です。
津の戸三郎様は鎌倉幕府の御家人、つまり武士です。奈良の東大寺が源平の争いの際に平重衡公によって焼き討ちされました。その再建に法然上人のお念仏信仰の同志であります俊乗房重源(しゅうじょうぼうちょうげん)上人が勧進役(寄付集め等の重要な役割)としてご尽力なさいました。いよいよ東大寺再建、大仏様の開眼法要ということで、鎌倉からも多くの武士がやってきました。津の戸三郎様もその中のお一人でした。
奈良までやってきたのだから、名高い法然上人を訪ねようと思って京都へ向かい、お念仏のみ教えと出会われます。お伝記には「合戦の罪を懺悔して」と記されています。嫌でも戦をしなくてはならない武士の身です。殺生をせざるを得ないのです。それを「仕方がない」と開き直らないのがありがたいと思います。「恐ろしいことをしている」という自覚を持っておられたわけです。当時多くの武士達が津の戸三郎様と同様、自らの罪を恐れて法然上人の元に集まってこられました。
当時の武士は江戸時代と違い、必ずしも身分が高いと一般には認識されていなかったようです。また、学問ができる武士というのはごく一部であり、殆どの武士には教養がありませんでした。そして武士自身がそのことを自覚し、コンプレックスを持っていたようです。
津の戸三郎様は法然上人から直接にお念仏の尊いみ教えを聞き、「この私が救われるのか!」と喜んで関東へ帰られました。
関東で念仏を称えていますと、よからぬ噂が聞こえてきました。「津の戸三郎は無教養な人間だから、法然上人も念仏を称えるだけで救われるというような簡単な教えを説かれたのだ。教養がある人にはもっと深い教えを説かれるのだ。」というのです。
このように言われますと、人によると腹を立てることもあるでしょう。しかし津の戸三郎様は真面目な方です。「もしかしたらそうかも知れない。」と思われました。
法然上人に「こんなことを言われたのですが本当でしょうか?」とお手紙をしたためて尋ねられました。そのご返事は御法語後編三十一章に記されています。
法然上人は津の戸三郎様に「そのような不信の者の言うことに惑わされず、しっかりと信心を持ちなさいよ。」と励まされました。津の戸三郎様はその励ましによって今まで以上にお念仏に励まれるようになりました。
一途にお念仏を称えておりますと、段々仲間が増えてきました。初めは一人であったのに、三十人の仲間ができたと法然上人にご報告なさいました。何ともけなげではありませんか。法然上人もご自分のこと以上に喜ばれ、讃えられます。そのご返事の一部が今日の御法語です。
「念仏往生の誓願は、平等の慈悲に住して起こし給いたることなれば、人を嫌うことは候わぬなり。」念仏往生の誓願といいますのは本願です。「阿弥陀さまの本願は平等の慈悲によって起こして下さったものでありますから、人を選びません。」
私たちの世界は平等、平等と言いながら、決して平等ではありません。一人一人性格も能力も考え方も違うということを知りながら、違いを見つけて上下、勝ち負け、損得、好き嫌いをいうのです。違いを見つけては区別をし、差別をするのです。これでは差別や争い、憎しみはなくなりません。
そもそも私たちは「自分のため」だけに生きています。「いやいや、私は自分の家族のために生きているのです」という方もおられるでしょう。しかしそれは「我が家族」です。
あくまで「自分」「我が」という「枠」の中に取り込んでしまいます。
「我が子」を完全に囲い、他人の子とは明らかに区別します。そして「我が子」を自分の思い通りにしようとコントロールします。しかもやっかいなことに、自分ではそんなつもりは微塵もなく、「あの子のため」だと思っています。
場合によっては大人になってから精神的に辛い日々が続き、その原因を探ったら自分の母親のエゴであった、ということもかなりあるといいます。しかし「あの優しかった母親が原因のはずがない」と本人も思い、もちろん母や「ウチの子のために」と思っていますから、自分が原因だとは気づきにくいというのです。
もちろん子にとって親は「我が親」です。他の大人には丁寧に接しても、「我が親」は自分の「枠」の中にいますから、多少暴言を吐いても許されます。そうやってお互いを傷つけ合うのです。
「私は家族も大事ですが、会社がよくなるようにと思って日々頑張っています」という方もおられるでしょう。しかしそれも「我が社」です。会社や母校の評価が自分のアイデンティティーになります。母校を馬鹿にされたら自分が馬鹿にされたように感じるのは、学校をも自分の中に取り込んでしまうからです。
「外国が日本のことをないがしろにするのは許せない!」という「愛国心」も同じです。
「我が国」です。
「愛」という言葉は仏教用語では「執着」を意味します。「執着」は「煩悩」です。我々の苦しみの原因です。
「我が」という「枠」は即ち「煩悩」なのです。その「枠」を取り去った状態を「無我」といい、仏様は「無我の境地」にて判断されますが、私たちにはそれは殆ど不可能です。
ですから阿弥陀さまは「こちらの方が仏教のことをよく学んでいるから救おう」とはおっしゃいません。「こちらの方があの人より善人だから救おう」ともおっしゃいません。 普通「善人が救われる」というのが私たちの常識なのかも知れませんが、それも阿弥陀さまからご覧になれば、私たちの違いはドングリの背比べです。「善人悪人、勝った負けたというけれど、どちらも凡夫。自分の力で悟ることができない凡夫ではないか」
阿弥陀さまは「自分の好み」「縁のある者だけ」という有縁の慈悲ではなく、無縁の大慈悲によって本願を建ててくださいました。
善悪や勝ち負けではなく、「ただ我が名を呼べ」とおっしゃっています。我が名を呼ぶ者を必ず極楽へ迎えとってやるぞ。」阿弥陀さまのお慈悲は私たちの優しさとは次元が違うのです。すべてを救いとる平等のお慈悲なのです。
「仏の御心は慈悲をもて体とすることにて候なり。」「仏様の御心はお慈悲を根本とするのである。」
「されば観無量寿経には仏心というは大慈悲これなりと説かれて候。」「だから観無量寿経には仏の心は大慈悲であると説かれている。」
「善導和尚この文を受けて、この平等の慈悲をもては遍く一切を摂すと釈し給えり。」「善導大師様はこの一文を受けて、この平等の慈悲をもって、遍くすべて一切を救って下さるのだと釈して下さっています。
「一切の言広くして、漏るる人候べからず。」「一切という言葉の意味は広い。だから漏れる人はいない。」一部を一切とはいいません。80%を一切ともいいません。100%を一切というのであります。だから漏れる人がいないのです。
「されば、念仏往生の願はこれ弥陀如来の本地の誓願なり。余の種々の行は本地の誓いにあらず。」「だから、念仏往生の願は阿弥陀さまの本願なのである。他の修行は本願ではないのだ。」と書かれています。
仏教を大きく二つに分けて、この世で自分の力によって悟りを開く教えと、阿弥陀さまの力で救われていく教えの二つがあります。お念仏はもちろん後者です。座禅、護摩を焚く、千日回峰など色んな修行がありますが、どれもこの世で悟りを開く為の修行です。念仏は阿弥陀さまが、この世で悟りを開くことなどできない私たちをみて、極楽という絶対の楽土(らくど)をおつくり下さり、我が名を呼ぶ者を極楽に迎えとるとお約束下さったのです。それが本願です。極楽へ往くにはお念仏なのです。他の修行も尊い修行でありますが、極楽へ迎えとるという本願ではないのです。
「釈迦も世に出で給うことは、弥陀の本願を説かんと思し召す御心にて候えども、衆生の機縁に随い給う日は、余の種々の行をも説き給うは、これ随機の法なり。」「お釈迦様がこの世にお出まし下さったのは、阿弥陀さまの本願を説こうという御心であった。しかし、人々の素質や能力、仏法と出会う縁もまちまちであるから、それに合わせて色んな修行方法を説かれたのである。これは人々の教えを受ける能力に合わせた教えなのです。」
お釈迦様は、人に合わせて教えを説かれました。お医者様が患者の病状に合わせて薬を処方されるように、人それぞれの性格や能力に合わせて、「あなたはこういう修行をしなさい。」と説かれました。ですから八万四千と言われるほどの教えがあり、多くのお経があるのです。これを対機説法(たいきせっぽう)といいます。この御法語で随機(ずいき)の法と書かれているのがこれに当たります。
しかし、それはあくまでその人に合わせた修行方法であり、万人に通じるものではありません。念仏が唯一、万人に通じる教えなのです。
お釈迦様の時代は宗教的な能力に優れた人たちが多くいました。そして何よりお釈迦様ご本人がおられるので、人に合わせて教えることがでいました。しかし、時代が下りますと人々の能力も衰え、優れた教えや修行があっても人々がそれについていけなくなってしまいます。念仏はそのような後の人々を救うために説かれた教えです。能力の劣った者の為に説かれた教えが能力の劣った者にしか通用しないかというと、決してそうではありません。すべての者を網羅する教えなのです。
お釈迦様もすべての者を救いたいと思っておられます。ですから、お釈迦様も念仏を説きたいと思ってこの世にお出まし下さったのです。
「仏の自らの御心には候わず。」「色んな修行を説いたけれども、それはお釈迦様が本当に説きたかったものではないのである。」
「されば、念仏は弥陀にも利生の本願、釈迦にも出世の本懐なり。余の種々の行には似ず候なり。」「念仏は阿弥陀さまにとってはすべての人々を救う為の本願であり、お釈迦様にとってはこの世にお出まし下さった目的である。他の修行とは異なります。」
こう言いますと、我田引水のように思われるかも知れません。しかしそうではありません。
法然上人は絶えず「自分にとって合うか」ということに視点をおかれます。他の修行もお釈迦様が説かれた教えですから、尊く有り難いのです。でも自分に合うかということです。法然上人ご自身が修行を重ねた上で「私にはとてもできない。私に合う教えは念仏しかない。皆さんはどうですか?」ということなのです。
前篇第三章 聖浄二門
原文
ある人、上人(しょうにん)の申させ給うお念仏は念々ごとに仏の御心にかない候うらんなど申しけるを、いかなればと上人返し問われければ、智者にておわしませば、名号(みょうごう)の功徳をも詳しく知ろしめし、本願の様をも明らかに御心得あるゆえにと申しけるとき、汝本願を信ずることまだしかりけり。弥陀如来の本願の名号は、木こり、草刈り、菜摘み水くむたぐいごときの者の、内外(ないげ)共に欠けて、一文不通(いちもんぶつう)なるが、称うれば必ず生まると信じて、真実に願いて常に念仏申すを最上の機とす。もし智慧を持(たも)ちて生死(しょうじ)を離るべくば、源空(げんくう)いかでかかの聖道門(しょうどうもん)を捨てて、この浄土門に赴くべきや。聖道門の修行は智慧を極めて生死を離れ、浄土門の修行は、愚痴(ち)に還りて極楽に生まると知るべしとぞ、仰せられける。
現代語訳
ある人が「法然上人がお称えになるお念仏は、その一念一念が(阿弥陀)仏のご意向に適っているのでしょうね」などと申し上げたのに対し、「どういうわけで」と、上人は問い返されました。そこで(その人は、)「智慧の深い方でいらっしゃるので、名号に具わる勝れた特性をも詳しくご存じで、本願のありさまをも、よくご理解なさっているからです」と申し上げました。そのとき(上人は)、「あなたの本願への信心はその程度だったのですか。阿弥陀如来の本願である名号は、(生業として)木を切り、草を刈り、野菜を摘み、水を汲むような人々で、仏典と仏典以外の書物のいずれについても文字一つ知らない人が、(称えれば必ず浄土に生まれる)と信じて、いつわりのない心で願い、常に念仏をお称えする、そうした人を、(救いの)最適の対象者とするのです。もしも智慧によって迷いの境涯を離れることができるならば、私、源空がどうしてあの聖道門を捨てて、この浄土門に帰依するでしょうか。聖道門の修行は、智慧を極めて迷いを離れ、浄土門の修行は、愚かな自分に立ち返って極楽に生まれると理解なさい」と、おっしゃったのです。
解説
偉いお坊さんがお念仏をお称えになるのと、小僧さんがお念仏を称えるのでは、何となく偉いお坊さんのお念仏の方が有り難いような気がしませんか?
修行を多く積み、人格が勝れた方がお念仏を称えると我々が唱える念仏とひと味違うような気がいたします。しかし浄土宗のお念仏はそのようなものではありません。
阿弥陀さまが、「私の名前を呼ぶ者を、私が救ってやろう」とお誓い下さった、これを本願といいます。この本願を信じて阿弥陀さまのお名前を呼ぶのです。これが南無阿弥陀仏のお念仏です。それぞれの能力に関係なく、極楽への往生を願って念仏する者を、阿弥陀さまがお救い下さるのです。救う側は阿弥陀さまです。偉いお坊さんのお念仏も小僧のお念仏も称える者を救って下さるのが阿弥陀さまです。昔からこのことは理解しにくかったのでしょう。ある人が法然上人と会話し、法然上人に勘違いを諫められているのがこの御法語です。本文を訳していきます。
ある人が「法然上人のお称えになるお念仏は、一声一声ごとに阿弥陀さまの御心に叶ってますね。」と言いますと、法然上人は「なぜですか?」と返答なさいました。その人は「法然上人は智者でいらっしゃいます。お念仏の功徳も詳しくご存知ですし、阿弥陀さまの本願のことも明らかに心得ておられますから、法然上人のお念仏は仏様の御心に叶い、ありがたいのです。」と言いました。そうしますと、法然上人は少し語気を強められて、「あなたはまだ本願を信じてませんね。」とおっしゃいました。
「弥陀如来の本願の名号は、木こり草刈り菜摘み水汲む云々」という文章です。現代でしたら差別ですが、当時木こりや草刈り、菜摘み、水汲む、こういった職業の方が一段下に見られていたという社会背景があります。それを法然上人は、「あなたは木こりや草刈り、菜摘み、水汲む、こういった仕事を生業としている方を愚かだと思っているでしょう。そういった方は見た目は見すぼらしい格好をし、学もなく、お経の文字はおろか普通の文字一つも知らないかもしれません。でもその方々が、「お念仏を称えれば必ず極楽へ往生できる」と信じて、本気で往生を願って常に念仏を称えていれば、それが最も往生が叶う素質なのですよ。
「もし智慧を持ちて生死を離るべくば源空いかでかかの聖道門を捨ててこの浄土門に赴くべきや。」
法然上人は仏教を大きく二つに分けて捉えておられます。一つは聖道門、もう一つは浄土門です。聖道門は自力の教え、浄土門は他力の教えです。聖道門を具体的にいいますと、天台宗、真言宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗他、殆どの宗派がこれに当たります。お釈迦様の教えにしたがって修行をし、この世で悟りを開くことを目指す教えです。
対して浄土門は、お念仏を称えて、阿弥陀さまの力によって極楽へ救いとっていただく教えです。他力です。一般的に他力といいますと、「他人任せ」のことを指しますが、本来の意味は「仏の力」、「阿弥陀仏の力」を限定して他力というのです。
法然上人は元々天台宗の僧で、三十年以上も比叡山で修行なさり、しかも「智慧第一の法然房」と呼ばれるほどの秀才でした。飛び抜けて優等生だったのです。その法然上人が、「自分の力ではとても悟りを開くことなどできない。」と気付かれ、浄土門に入られたのです。
ですから「あなたは私の智慧が勝れているから仏の御心に叶うと言うが、もし私が自分の智慧によってこの苦しみ迷いの娑婆世界から逃れようとするならば、私は何のために聖道門を捨ててこの浄土門に入る必要があったのか。聖道門の修行は智慧を極めて苦しみ迷いの世界から逃れる教えであるぞ。浄土門の修行は愚痴に帰って極楽へ往生させていただく教えだということを知りなさいよ。」とおっしゃったのです。
智慧があってもなくても往生を願って念仏を称える者を阿弥陀さまはお救い下さいます。しかし、智慧があると信じる心を邪魔することがよくあります。「科学的にみたら極楽や阿弥陀さまなんて考えられない」などと言って自分の知識や経験にないものを信じることができないようになるのです。
どれだけ知識や経験、学問に勝れていても、極楽へ往生するのは阿弥陀さまの力によるのです。信じてお念仏を称えるかどうかなのです。知識や経験は生活には色々と役立つことでしょう。
しかし往生のためにはそれを一旦横に置いて、自分は自分の力で往生することなどできない、愚痴の身なんだと知って阿弥陀さまにお任せしてお念仏を称えるのです。
法然上人は一枚起請文でも「一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無知の輩に同じうして、智者のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし。」とおっしゃっています。これも同じことです。同じ内容を何度もおっしゃるということは、今も昔も「修行を一生懸命した者の念仏が勝れている」、「高いお金を出して買った物は良いモノ、安いモノは悪いモノ」、「難しい試験をクリアして入る学校は良い学校、簡単に入れる学校は悪い学校」などという私たちの価値観はなかなか変わらないということでしょう。お念仏は「誰もができる簡単な行」ですが、「誰もが救われる最も勝れた行」です。なぜならば、救う側は阿弥陀さまだからです。
前篇第二章 立教開宗
原文
おおよそ仏教多しといえども、所詮(せん)戒定慧(かいじょうえ)の三学(さんがく)をば過ぎず。いわゆる小乗の戒定慧、大乗の戒定慧、顕教(けんぎょう)の戒定慧、密教の戒定慧なり。しかるに、我がこの身は戒行(かいぎょう)において一戒(いっかい)をも持(たも)たず、禅定(ぜんじょう)において一つもこれを得ず。人師(にんじ)釈して、尸羅(しら)清浄(しょうじょう)ならざれば三昧(さんまい)現前(げんぜん)せずといえり。又、凡夫(ぼんぶ)の心は物に従いて移り易し。例えば猿猴(えんこう)の枝に伝うが如し。誠に散乱して動じ易く、一心静まり難し。無漏(むろ)の正智(しょうち)、何によりてか起こらんや。もし無漏の智剣(ちけん)なくば、いかでか悪業(あくごう)煩悩(ぼんのう)の絆(きずな)を断たんや。悪業煩悩の絆を断たずば、何ぞ生死(しょうじ)繋縛(けばく)の身を解脱(げだつ)することを得んや。悲しきかな、悲しきかな。いかがせん、いかがせん。ここに我ら如きは、すでに戒定慧の三学の器(うつわもの)にあらず。この三学の他に我が心に相応(そうおう)する法門ありや、我が身に堪(た)えたる修行やあると、よろずの智者に求め、諸々の学者に訪(とぶ)らいしに、教うるに人もなく、示すに輩(ともがら)もなし。しかる間、嘆き嘆き経蔵(きょうぞう)に入(い)り、悲しみ悲しみ聖経(しょうぎょう)に向かいて、手ずから自ら開き見しに、善導和尚(かしょう)の観経の疏(かんぎょうのしょ)の一心に専(もっぱ)ら弥陀(みだ)の名号(みょうごう)を念じ、行住坐臥(ぎょうじゅうざが)に時節(じせつ)の久近(くごん)を問わず、念々に捨てざる、これを正定(しょうじょう)の業(ごう)と名付く、彼の仏の願に順ずるが故に、という文(もん)を見得(みえ)て後、我らが如くの無智(むち)の身は、ひとえにこの文(もん)を仰ぎ、専らこの理(ことわり)を頼みて、念々不捨の称名(しょうみょう)を修(しゅ)して、決定(けつじょう)往生の業因(ごういん)に備うべし。
現代語訳
およそ仏の教えは数多くありますが、つまるところは、戒定慧という三種の修行方法以外にありません。すなわち、小乗仏教の戒定慧、大乗仏教の戒定慧、顕教の戒定慧、密教の戒定慧であります。
ところが私自身は、戒の修行については一つの戒すら守ることができず、禅定については一つもこれを体得していません。ある高僧が解釈して「戒が浄らかでなければ、対象に心を集中する境地は現れてこない」と言われました。
また、凡夫の心は物事を見聞きするにつれて移ろい易いのです。たとえば、猿が枝から枝へと渡っていくようなものです。本当に散乱して動き易く、心を静めることは難しいのです。(そんな時、)煩悩に染まらない正しい智慧が、どうして起こるでしょうか。もし煩悩に染まらない正しい智慧が、どうして起こるでしょうか。もし煩悩に染まらない智慧の剣がなければ、どうして悪業や煩悩という絆を断ち切ることができるでしょうか。本当に悲しいことです。本当にどうしたらよいのでしょうか。
そこで、「我々のような者は、もはや戒定慧という三種の修行の器ではない。この三種の修行方法の他に、私のような者の心にふさわしい教えはあるだろうか、私のような者の身に可能な修行はあるだろうか」と、多くの智者に教えを請い、様々な学者を訪ねましたが、教えてくれる人もなく、示してくれる友もありませんでした。
そういうわけで、嘆きつつ経蔵に入り、悲しみつつ仏典と向き合い、みずから手にとって読んだところ、善導尚の『観経疏』の「心を一つにしてひたすら阿弥陀仏の名号を念じ、立ち居起き伏し、時間の長短を問題とせず、片時もやめない、これを正しく定まった行いと名づける。それはかの阿弥陀仏の本願に順っているからである」という一文を知ることができました。それからというもの、「我々のような無智の者は、ひたすらこの文を仰ぎ敬い、専らこの道理を頼みとして、片時もやめない称名念仏を修めて、往生を決定させる因として準備するべきである」(と深く心に留めたのであります)。
解説
今回の御法語について申し上げる前に、法然上人の半生について触れる必要があります。
法然上人は岡山のお生まれです。岡山の北部、美作というところで、現在お生まれの地には誕生寺というお寺が建っております。もちろん元々お寺があったのではなく、法然上人の誕生の地だということで、お弟子の熊谷次郎直実という方が建てたお寺です。
法然上人は武士の子です。押領使という役人で、地方の治安を維持するお役目でありました。武士といいますと、身分が高かったのですねと言われる方がおられますが、そうでもないようです。我々は多く江戸時代の、身分制度が確立してその頂点に武士が収まっている武士をイメージしますが、古代の武士はそうではありません。天皇や貴族の警護をしたり、地方を武力でもって治める、どちらかというと乱暴者のようなイメージでみられていた部分もあるようです。法然上人のお父様、漆時国公も下級武士 ですから、そのような面もあったのかも知れません。
押領使は国が任命する役人です。ですから押領使が管理するのは朝廷の土地です。それとは異なり古代、中世には荘園というものがありました。貴族や寺社が土地を所有していて、そこから年貢などを徴収します。この荘園の管理者を預所といいます。預所も武士です。
漆時国公が治安を守る土地のすぐそばに荘園があり、京都から派遣された預所の明石源内武者定明という武士がいました。近い場所で立場の違う武士がいて、どちらが身分が高いかも定かになっていません。この時代は政治のシステムが崩れている時代でした。
そのようなことから、漆時国公と明石源内武者定明は非常に仲が悪かったといいます。法然上人が数え年9歳のある夜、突然定明が大勢で時国公の屋敷を攻めてきました。時国公は深手を負い、それが致命傷となって死んでしまいます。ご自分の死を覚悟した時国公は、枕元に息子である法然上人を呼び、非常に尊い遺言を残されます。法然上人は武士の子ですから、当然「必ず仇を討ちます!」とおっしゃったことでしょう。
しかし時国公はそれをお許しになりませんでした。「仇を討つな」とおっしゃったのです。「仇を討つな。お前が私の仇を討ったならば、敵の子や家来がまたお前の命を狙うであろう。恨み憎しみというものは尽きることがないのだよ。恨み、憎しみはお前のところで断ち切るべきだ。そしてお前は出家をして私の菩提を弔ってくれ。そしてお前自身が覚る為の道をしっかりと突き進んでくれよ。」とお示しになったのです。
これは現代でいう平和主義というものとは大きく次元を異にします。当時は敵討ちは美徳でありました。ましてや夜討ちという卑怯な手でやられたのですから、敵討ちをしない方がおかしいと考えます。卑怯者と言われるのです。その時代に、しかも自分が普段から憎む相手に今やられたところです。そんな時に「仇を討つな」と仰ったということは並のことではありません。
ただ、遺言は尊いですが、それを言われる法然上人はつらかっただろうと思います。「この恨みを忘れず、臥薪嘗胆、いずれ大きくなったら必ず私の仇を討ってくれよ。」と言われる方がよっぽど気が楽だったと思います。
しかしお父様はそのまま亡くなってしまいますから、その遺言を守らなくてはなりません。
まだ数えで9歳、今でいう小学校2年生という幼さです。私の先輩がかつて養護施設に勤めておられまして、その方が仰るには、一番心を開かないのは目の前で親を殺された子だということです。何を言っても笑わないというのです。実際にそういう子がいたのだそうです。法然上人の時代と現代を比べると、現代人は精神的に弱くなっているということもあるかも知れません。しかし目の前で親を殺されたというショック、悔しさ、悲しさには違いはないでしょう。
法然上人はお父様のご遺言を胸に、お母様の弟、観覚得業というお坊さんの元で仏教を学ばれます。同じ岡山の菩提寺という山の中のお寺です。法然上人は一を聞いて十を知る、非常に頭の良いお方でした。観覚得業様は「こんな田舎の山寺にいつまでも置いておくにはもったいない」と法然上人を比叡山に送られます。法然上人数え年十三歳、今でいう小学校六年生で比叡山に登られたのです。登山の年齢につきましては十五歳という説もありますが、多くの学者が十三歳説を採っておられるのでそれに従います。
このときにお母様とは生き別れです。二度と会われることはありませんでした。もちろん今のように交通は発達していませんし、比叡山に登るということは二度と家族と会わないという覚悟をしなくてはならないことでした。
比叡山に登ってから法然上人はがむしゃらに学び、修行に励まれます。そうしているとやはり徐々に有名になってきます。お師匠様には「お前は頭が良い。いずれは天台の棟梁になるべき器だ。」などと言われます。しかし法然上人はそんな出世や名声には全く興味がありません。法然上人の目的はただ一つ、お父様のご遺言の通りに悟りを開くことです。このままいたら出世競争に巻き込まれてしまうということで、わずか十八歳、これも数えですから今でいう高校二年生という若さで隠遁してしまわれます。比叡山の中でも特に奥深い黒谷という土地に青竜寺というお寺があります。青龍寺には叡空上人がおられ、法然上人と同じように隠遁してひたすら学問と修行をする人が集まっていました。法然上人はそれ以来、この黒谷青龍寺で二十五年間も過ごされます。黒谷におられる上人という意味で、法然上人のことを黒谷上人ともいいます。
京都に浄土宗の大本山、黒谷金戒光明寺がありますが、ここは黒谷上人が比叡山から下りて来られて念仏布教をなさった土地ですから、黒谷と名付けられたのです。青龍寺を元黒谷、金戒光明寺を新黒谷と呼び分ける場合もあります。金戒光明寺がある場所は丘になっており、決して谷ではありません。その場所を黒谷と呼ぶのは、以上のような謂われがあるからなのです。
さて、黒谷青龍寺に入られてからの法然上人は今までにも増して学び、厳しい修行をなさいます。しかし学べば学ぶほど、修行すればするほどに、教えの尊さと自分の器に距離を実感してきます。前置きが長くなりましたが、この御法語は法然上人が大きな悩みにぶつかられた部分なのです。
「おおよそ佛教多しと言えども、所詮戒定慧の三学をば過ぎず。」とあります。
「佛教には色んな宗派があるが、どれをとっても所詮戒定慧の三学に過ぎないんだ。」ということです。
戒定慧の戒は、仏教徒としての正しい習慣です。悟りに至るには、正しい行いをしなくてはなりません。しかし私達は何が正しい行いなのか、何が悪い行いなのかが分かりません。時代や集団の価値観に左右されてしまうからです。だから、お釈迦様が「○○をしてはいけません。」と悪い行いを示して下さっているのです。これが戒です。例えば「人を殺してはいけませんよ。」「嘘をついてはいけませんよ。」 「人の物を盗んではいけませんよ。」などです。悪い行いを止めることが即ち善い行いをする習慣になっていきます。
戒を守る人が定という修行をします。定は、心を静かに定めることをいいます。禅定などとも言います。いわゆる座禅などの瞑想です。
そして悟りの智慧を得る。これが慧です。
戒定慧と言いますと、三つが並列に価値を持つと思われるかも知れませんが、実はこれは修行の段階です。戒を守る者が定という修行をし、悟りの智慧を目指すのです。
佛教には色んな宗派や学派がありますが、どれも修行方法としては戒定慧の三学に過ぎないのだ、ということです。
「いわゆる小乗の戒定慧、大乗の戒定慧、顕教の戒定慧、密教の戒定慧なり。」
佛教を大きく、小乗仏教、大乗仏教の二つに分けることができます。ただ、「小乗仏教」という呼称は「大乗仏教」から見て「小さな乗り物」を表す蔑称だということで、原文と現代語訳はそのままにしますが、この解説では以後「南伝仏教」と表現します。南伝仏教はタイやミャンマー、スリランカなどに伝わっていった佛教です。大乗仏教は中国、朝鮮、日本、あるいはチベットに伝わっていった佛教です。
「南伝仏教と大乗仏教は、教えは色々と違うところがあるけれども、修行はそれぞれに戒定慧を行うのだ。」ということです。
また、大乗仏教を大きく二つに分けて、顕教と密教とに分けることができます。顕教とは教えが明らかになっている佛教です。殆どの宗派がこれに当たります。密教は教えが明らかになっていない佛教、真言宗と天台宗の一部です。その顕教も密教も修行の段階としては戒定慧なのです。
「しかるに我がこの身は戒行において一戒をも持たず、禅定において一つもこれを得ず。」
「しかし私は戒を一つも守れない。心を静かに定める禅定も一つもできない。」と仰るのです。法然上人は智慧第一の法然房と呼ばれていましたが、戒についても法然上人ほど厳しく戒を守る人はいないと尊敬されていました。その法然上人が戒を一つも守れないとおっしゃるのです。これは謙遜ではありません。殊勝なお言葉を述べておられるのではありません。戒は厳密に言うと、体と口と心で守らなくてはなりません。法然上人は体や口では一生涯きっちりと戒を守り通されたのです。しかし、心ではどうか。人を殺してはいけない、不殺生戒でさえも守れない。父を殺した明石源内武者定明を亡き者にしたい。あいつがいなければ父と死に別れ、母と生き別れることもなかった。殺してやりたい。そんな思いがあったのかもしれません。心を静かに定めようにも、怒り、憎しみを持ち続けている私である。一つの戒も守れない、心を静かに保つことなどできない私であるという、真剣にご自分自身を見つめられた告白なのです。
「人師釈して、尸羅清浄ならざれば三昧現前せずといえり。」
「人師釈して」は「昔の偉い方が仰るには」という意味です。
「尸羅」というのは「戒」と同じ意味です。インドの昔の言葉で戒のことをシーラと言ったのです。それを音写した言葉です。「三昧」は瞑想の境地です。カニづくし料理をカニ三昧だなどと言いますが、本来の意味から言うと全く違います。
ですから、「昔の人が仰るには、戒を守って行いを清くしておかなければ、瞑想の境地である三昧には到達しないと言われています。」ということです。
「又、凡夫の心は物に従いて移り易し。たとえば猿候の枝に伝うが如し。誠に散乱して動じ易く、一心静まり難し。」
「私達凡夫の心というものは一々移り変わり易いものだ。まるで猿が木の枝から枝へピョンピョン飛び移るかのように、心が散乱して動いてしまい、一つ処に心を静めることができないのだ。」ということです。
「無漏の正智、何によりてか起こらんや。もし無漏の智剣なくば、いかでか悪業煩悩の絆を断たんや。悪業煩悩の絆を断たずば、何ぞ生死繋縛の身を解脱することを得んや。」
「悟りの智慧はどうやったら得られるのだ。もし悟りの智慧を得る方法がなければ、どうやって悪業煩悩を断つことができようか。悪業煩悩を断つことができなければ、どうやって苦しみ迷いの娑婆世界から抜け出すことができようか。」と絶望なさるのです。
「悲しきかな悲しきかな、いかがせん、いかがせん。」
このままでは父の遺言である悟りへ到達することなどとてもできないと行き詰まってしまわれるのです。「ああ、悲しいことだ、どうすればいいんだ。」
「ここに我ら如きはすでに戒定慧の三学の器にあらず。」
「私のような者はすでに戒定慧の三学の器ではありません。」と仰います。先ほど、佛教は戒定慧の三学に尽きると仰ったのに、私は戒定慧の器ではないと仰るのです。もう私は佛教では救われないのかというところまで追い込まれているのです。
法然上人は数え年十八歳で黒谷青龍寺に入り、それから二十五年間修行を続けられたのですが、二十四歳の時に一度だけ比叡山を下りておられます。そして奈良や京都の他の宗派の偉い学者達を訪ね歩いて教えを請われました。元々頭脳明晰で多くの知識を持っておられる法然上人ですから、学者達の説く教えを悉く理解されます。どの宗派の教えも素晴らしい。どれもお釈迦様が説かれた教えですから尊い教えばかりです。しかし、どれも修行は戒定慧の三学です。どの教えも極めれば尊いけれども、そこに到達することができなければ意味がない。私ができる教えがどこにもないと気付かれ、また肩を落として比叡山に戻って行かれるのです。
「この三学の外に我が心に相応する法門ありや、我が身に堪えたる修行やあると、万の智者に求め、諸々の学者に訪いしに教うるに人もなく、示すに輩もなし。」
「この三学の外に私の心に相応しい教えはあるのか、この私が耐えられる修行はなるのかと多くの智者や学者を訪ねて教えを請うが、誰も教えてくれない、誰も示してくれない。」というのです。
青龍寺に戻った法然上人は、経蔵に籠もってお釈迦様が説かれたお経をひたすら読み続けられます。お釈迦様が生涯かけて説かれた教えをすべて合わせて一切経といいます。五千巻以上のお経がありますから、一人の人が一生かけても読み尽くせないと言われています。それを法然上人は十八歳から四十三歳までの二十五年間で何と五回もご覧になったといいます。お釈迦様が説かれた教えの中にこの私が救われる教えがないはずがない、必ずどこかにあるはずだとひたすらに探し求められました。
「嘆き嘆き経蔵に入り、悲しみ悲しみ聖教に向かいて、手ずから自ら開き見しに、善導大師の観経疏の、一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥に時節の久近を問わず、念々に捨てざる、これを正定の業と名付く、彼の仏の願に順ずるが故に、という文を見得て後、我らが如くの無智の身は、偏にこの文を仰ぎ、専らこの理を頼みて、念々不捨の称名を修して、決定往生の業因に備うべし。」
嘆きながら経蔵に入り、悲しみながらお釈迦様が説かれた一切経をくまなくご覧になること五回、とうとう五回目に中国の唐の時代に浄土教を大成された善導大師の観経疏という書物と出会われました。
そこには「一心にただひたすら阿弥陀様の名前を称え、歩いていても立ち止まっていても座っていても寝ていても、念仏を称える期間の長さに関係なく、一生涯続ける。これを極楽往き間違いなしの行いという。なぜなら極楽の主である阿弥陀様がそう約束して下さっているのだから。」という一文がありました。
弥陀は阿弥陀様です。名号は南無阿弥陀仏のお念仏。念じるは声に出して称えることです。時節の久近を問わずというのは、念仏のみ教えと若い時に出会えば長い期間お念仏が称えられます。しかし年を取ってから出会えば、称える期間は短くなります。あるいは死ぬ間際に念仏と出会っても、殆ど称える時間はありません。でもその期間の長さに関係なく、ということです。
念々は一瞬一瞬です。一瞬一瞬捨てない、つまりずっと続けるということです。
正定の業とは、極楽往きの為の正しく定まった行いということです。
彼の仏とはもちろん阿弥陀仏です。願とは阿弥陀仏の本願です。本願に南無阿弥陀仏と称える者を必ず極楽浄土に迎え取るとお約束下さっています。
「ただひたすら南無阿弥陀仏と称える。いつでもどこでもどんな時でも、死ぬまで称える。そうすれば必ず極楽へ往生できる。阿弥陀様の本願にそう誓われているのだから。」という文です。
法然上人はこの一文を見つけて、男泣きに泣かれたといいます。お伝記には「落涙千行」と書かれています。とうとう三学を超えた教えを見つけた。これなら私にもできる。父も母もすべての人々も救われる。
「この一文を見つけてからは、私のような無智の者は偏にこの一文を仰ぎ、この理を頼りにして、一声の念仏も見捨てられないという称名念仏を行って、来る往生に備えなくてはならない。」と締めくくっておられるのです。
このように申しますと、よく「昔の人はすごいですねえ。」と言われます。しかし、そんな次元の話ではありません。昔の人の中でも比叡山で修行される勝れた人ばかり、その中でも飛び抜けて勝れた法然上人が、この私にできる教えは念仏しかないとおっしゃったのです。昔の人でも多くの人は、できていないのにできているようなフリをし、あるいはできているような錯覚をして、三学を行っていたのです。法然上人の素晴らしいところは智慧が勝れていることはもちろんですが、それ以上にご自分自身を見つめられる厳しい目を持っておられたことです。
法然上人はお父様の遺言通り、悟りを目指されたのです。形だけの出世が目的ではありません。だから、三学をできていないのにできているような顔をしていても何にもならなかったのです。
本気でやろうとしたら、私には絶対にできない。どれも教えは尊いが、できなければ絵に描いた餅です。本気で私達が救われる教えはお念仏しかないのです。
私達はたまたま浄土宗のウチに生まれ、あるいは嫁いだ先が浄土宗であったと思っています。でもそうではないのです。本気で求めたならば、真剣に自分自身を見つめたならば、浄土宗の教えでなければ救われない私に気付くはずです。
前篇第一章 難値特遇
原文
それ流浪三界のうち、何れの境に趣きてか釈尊の出世に遇わざるりし。輪廻四生の間、何れの生を受けてか如来の説法を聞かざりし。
華厳開講の莚にも交わらず、般若演説の座にも連ならず、鷲峰説法の庭にも望まず、鶴林涅槃の砌りにも至らず。我れ舎衛の三億の家にや宿りけん。知らず、地獄八熱の底にや住みけん。恥ずべし、恥ずべし。悲しむべし、悲しむべし。
まさに今、多生曠劫を経ても生まれ難き人界に生まれ、無量億劫を送りても遇い難き仏教に遇えり。釈尊の在世に遇わざる事は悲しみなりといえども、教法流布の世に遇う事を得たるは、これ悦びなり。譬えば目しいたる亀の、浮き木の穴に遇えるがごとし。
我が朝に仏法の流布せし事も、欽明天皇、天の下を知ろしめして十三年、壬申の歳、冬十月一日、初めて仏法渡り給いし。それより前には如来の教法も流布せざりしかば、菩提の覚路いまだ聞かず。
ここに我等、いかなる宿縁に応え、いかなる善業によりてか、仏法流布の時に生まれて、生死解脱の道を聞く事を得たる。
然るを、今、遇い難くして遇う事を得たり。徒らに明かし暮らして止みなんこそ悲しけれ。出典:『法然上人行状絵図』第三十二巻
現代語訳
そもそも三界という迷いの境涯を流れさすらうなか、いかなる境界にあったがために、釈尊の出現に巡り遇わなかったのでしょうか。四種の生を廻る間、いかなる生を受けたが為ために、釈尊の説法を聞かなかったのでしょうか。
『華厳経』講説の席にも加わらず、『般若経』説示の座にも列せず、霊鷲山での『法華経』説法の場にも臨まず、鶴林での釈尊涅槃の場面にも出会えませんでした。私は舎衛国の、[釈尊に無縁であった]三億の家に生を受けていたのでしょうか。いったい、八熱地獄の底にでも沈んでいたのでしょうか。本当に恥ずべきことです。本当に悲しむべきことです。
[ところが]まさに今、極めて多くの生涯を繰り返しても生まれ難い人間の境界に生まれ、極めて長い年月を送っても遇い難い仏教に出遇いました。釈尊の在世に遇わなかったことは悲しみでありますが、その教えが伝わっている世に遭遇することができたのは、まことに喜びであります。たとえば、盲目の亀が大海に浮かぶ木の穴に、偶然首を入れるようなものです。
わが国に仏法が伝わったこともその通りで、欽明天皇が日本国を統治なさって十三年目、壬申の年(五五二年)の冬の十月一日に、初めて[百済から]仏法が渡ってきましたが、それ以前には、釈尊の教法も広まっていなかったので、覚りへの路はまだ誰も耳にしていませんでした。
ここに我々は、どのような過去世の良縁に報われ、どのような善業によって、仏の教えが行きわたる時世に生まれて、迷いの境涯を解脱する道を聞くことができたのでありましょうか。
それを今、遇い難い身で出遇うことができたのです。無益に月日を送って人生が終わるとしたら、残念なことであります。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊より)
解説
私達はこうして人間として生まれてきたことを、当たり前のこととして、さほど不思議にも思わず日々過ごしておりますが、決してこれは当たり前のことではありません。科学的に考えても、1億精子の中で卵子とひっつくのはただ一つ、とてつもない確率です。先祖から自分までがそのように繋がるわけですから、気の遠くなるような確率です。私なども両親がどうやって出会い、その両親がどうやって出会い、先祖代々が一人でも欠けたら今の私はいないのだなあと、時々思います。生涯の中でも様々な縁があり、その一つが違うだけで未来は変わっていきます。そう考えますと、今あることが不思議でなりません。
更に仏教では、輪廻を説きます。私達は生まれ変わり死に変わりを繰り返しているのです。行いのことを業(ごう)といいます。過去世の業と様々な縁によって今が決まるわけです。私達の過去世の数え切れないほどの業と、数え切れないほどの縁によって、今があるのです。今、生まれ変わり死に変わりを繰り返して、ようやく人間になることができたわけです。決して楽しいばかりの人生ではないでしょうが、とてつもない様々な因縁によって今があるということは事実です。そして今、どういうご縁か、不思議なご縁によって仏教のみ教えと出会ったのです。たまたま家が浄土宗だから、嫁いだ先が浄土宗だったから、などということではなく、それも数限りない縁と、自分の業によってようやく尊きみ教えと出会ったのですよ、今お念仏称えないとどうするんですか、というのが本日の御法語の主旨です。
文面は非常に難しいものです。これは一般の方向けに書かれたものではなく、法然上人が比叡山に向けて送られた、つまり坊さん相手に書かれた文章なのです。比叡山に送られたものですから、「登山状」と呼ばれています。今日の文章はその「登山状」の一部分です。坊さん向けのものですから、専門用語がたくさん出て参りますし、また非常に推敲を重ねられた文、練られた文章です。美文といいます。ですから一般には読みにくいものですが、大切なことが記されていますので、順番に読んで参ります。
「それ流浪三界のうち、いずれの境に赴きてか、釈尊の出世に遇わざりし。」
流浪三界というのは、輪廻のことです。生まれ変わり死に変わりし、さまよい続けていることを表します。さまよい続ける中で、もしかしたら、お釈迦様と会っていたかも知れないわけです。前世か前前世か分かりませんが、お釈迦様と会ったことがあるのかも知れないのですね。しかし、私は一度もお釈迦様に会うことがなかったと書かれているのです。
「輪廻四生の間」
これも輪廻のこと、「流浪三界」と同じ意味です。輪廻し続けているうちに、仏様から直接教えを受ける可能性もあるはずですが、私は一度も仏の説法を聞くことができなかったと書かれています。
もしお釈迦様と出会い、教えを直接聞いていたならば、もうとっくにこの輪廻から脱出しているはずなのに、未だにこうして人間として輪廻をさまよっているということは、一度も教えを聞かなかったんだなあ、ということになるわけです。
「華厳開講の筵にも交わらず」華厳経というお経があります。このお経を大事にするのが華厳宗です。奈良の東大寺、大仏様の東大寺は華厳宗です。お経はお釈迦様が説かれたものです。もちろん華厳経もそうです。私は生まれ変わり死に変わり輪廻する中で、華厳経が説かれた場所に居合わすことができなかったんだなあ、ということです。
「般若演説の座にも連ならず」
般若経というお経、非常に量の多いお経です。その中の一部、有名なのが般若心経です。この般若経が説かれた座にも連なることができなかった。
「鷲峰説法の庭にも臨まず」
これは法華経のことです。法華経が説かれたときにもそこに居ることができなかった。
「鶴林涅槃のみぎりにもいたらず」
お釈迦様の臨終の時を涅槃といいます。涅槃の時にもお釈迦様は教えを説かれた、これが涅槃経です。そこにも縁がなかった私達です。
「我舎衛の三億の家にや宿りけん」
舎衛とは、お釈迦様在世当時のインドにあった舎衛国という国の名前です。お釈迦様はこの舎衛国で多くの人に布教なさっています。お釈迦様当時最も栄えた場所で、九億の家があると言われていたのです。もちろん誇張表現ですが、それほどに栄えていたのでしょう。その九億の内、三億の家の人はお釈迦様の教えを直接聞いたと言われます。また三億の人は、お釈迦様に直接会うことはなかったけれども、お釈迦様の存在は知っている、仏教の存在は知っているといいます。しかし、残りの三億の人はお釈迦様と同じ時代に生まれ、同じ国に居ながらお釈迦様のお名前も知らなければ、仏教という言葉も聞いたことがないといいます。もちろんテレビなどもない時代ですから、どれだけ有名な人でも知らない人はいるということですね。
「私は輪廻を繰り返す中で、お釈迦様と同じ時代に生まれ、同じ舎衛国に居たかも知れない。でも私は残りの三億だったのだなあ。恥ずべし、恥ずべし、悲しむべし、悲しむべし。」とおっしゃるのです。
何が恥ずかしいのかといいますと、「輪廻を続ける中で、自分が良い業を積み、良い縁があったならば、お釈迦様と出会い、仏様のみ教えと出会うこともできたであろうに、私は一度もその機会がなかった。これはよほどろくな行いをしてこなかったんだなあ。ああ恥ずかしい、恥ずかしい。悲しいことだなあ。」ということなのです。
それが正に今、どれだけ生まれ変わり、どれだけ死に変わりしたのかわからないほどの時間を経て、生まれがたい人間に生まれることができたのです。そして、永遠に近いほどの時を経て、遇いがたい仏教に遇ったのです。お釈迦様の在世中に直接会うことはできなかったけれども、でもみ教えが伝わっている時代に生まれることができたことは悦びであります。それは喩えるならば、目の見えない亀が浮き木の穴に遇うようなものだと書かれています。
これは仏教特有の喩えです。目の見えない亀が海を泳いでいます。亀は100年に一度海面から顔を出すといいます。そこにたまたま浮き木が流れてくるわけです。浮き木には亀の首が丁度入るだけの穴が空いています。目の見えない亀が百年に一度海面から顔を出し、そこにたまたま流木があって、その穴に亀の頭がスポッと入るほど、仏教と出会うことは不思議な縁だという喩えなのです。かえってわかりにくいでしょうか。目が見える亀であれば、穴に向かって泳ぐこともあるかも知れない。でも目が見えない亀です。それも百年に一度しか顔を出さないのです。またそこに流木が流れてくる、しかもそこに亀の首と同じ大きさの穴が空いているなんて、それだけでも滅多にないことです。それほどのご縁なのですね。盲亀の浮木といわれる喩えですが、今では差別用語になるとも言われています。しかし古くから伝わる有名な譬喩ですので、そのままお伝えしました。
「我が朝に仏法の流布せしことも」
「我が朝」とはもちろん日本です。日本に仏教が伝わったのが、欽明天皇が天下を治めている、欽明天皇の十三年、壬申の年、冬十月一日です。仏教公伝です。西暦538年とか552年という説がありますが、定かではありません。日本史の教科書にも、百済の聖明王から欽明天皇に仏像や経典が送られたことが最初とされています。実はそれ以前に私的には入ってきていたようですが、公にはこの時といわれます。
ですから、それ以前にもし、自分がこの日本に生まれていたとしても、仏様の教えはまだ日本に伝わっていないのであるから、悟りの為の教えは聞けなかったのだ、ということです。
ここに私達は過去世にどういうご縁があったのか、全く記憶にはないけれどもどれだけ良い業を積んだのか、何と仏教が広まっている時代に生まれ、悟りの為の教えを聞くことができたのだ。今本当に遇いがたくして教えと出会ったんだ。いい加減に過ごして終わったら、そんなに悲しいことはないだろう、ということです。
もちろん法然上人がおっしゃることですから、お念仏を称えずに過ごしてはいけませんよということになります。
私達は全然覚えていなけれども、ずっと輪廻をさまよい続け、しかも自分たちがさまよい続けていることにすら気付かずに過ごしているのです。それがどういうわけか、色んな縁や自分の行いによって、ようやく人間として生まれてきたのです。そして本当に不思議な縁で仏教のみ教えに出会ったわけです。
今ようやくこの苦しみの輪廻の世界から抜け出すチャンスなのです。ここで、抜け出せばよいのですが、「お念仏も有り難いかわからんけども、なかなかねえ。」などと言って過ごせば、またさまよい続けなくてはならないのです。そうすると前世の記憶はなくなりますから、やり直すことはできません。次にいつ抜け出すチャンスがくるかわからないわけです。
お念仏との出会いに限らず、すべてにおいて今あることが不思議であります。ただ、その中でもお念仏とのご縁を今結んだのにこれを無駄にしてしまうと、輪廻から抜け出すチャンスがもう巡ってこないかも知れないという時であるということを強く認識する必要があります。
私はいつも観覧車を想像します。15分ほどで一周回り、下について係の人が扉を開けて用意して下さっているのに、ペチャクチャ喋って降り損ねたら、また15分待たないといけないですね。観覧車なら定期的に戻って来ますが、輪廻は一度チャンスを逃したら、とてつもない時間をさまよい、もう一度チャンスが巡ってくるかどうかすらわからないのです。今しなくてはならない。この御法語を読むたびにその思いを強くいたします。