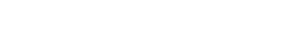後篇第三十一章 還来度生
(本文)
左様(さよう)にそらごとをたくみて、申し候(そうろ)うらん人をば、かえりて哀れむべきなり。さほどの者の申さんによりて、念仏に疑いをなし不信を起こさん者は、言うに足らぬほどの事にてこそは候わめ。大方弥陀に縁浅く、往生に時到らぬ者は、聞けども信ぜず行うを見ては腹を立て怒りを含みて、妨げんとすることにて候うなり。その心を得ていかに人申すとも、御心ばかりはゆるがせ給うべからず。強(あなが)ちに信ぜざらんは、仏なお力及び給うまじ。いかにいわんや凡夫の力及び候まじきことなり。かかる不信の衆生を利益せんと思わんにつけても、とく極楽へ参りて、悟りを開きて、生死(しょうじ)にかえりて、誹謗(ひぼう)不信の者をも渡して、一切衆生遍く利益せんと思うべきことにて候うなり。
(現代語訳)
そのように嘘をたくらんで言うような人のことを、かえって気の毒に思うべきです。そんな程度の者が言うことで、念仏に疑いを抱き、不信の念を持つなどは、口に出す必要もないほどの〔愚かしい〕ことでありましょう。
およそ、阿弥陀仏に縁が浅く、往生の機が熟していない者は、〔教えを〕聞いても信じず、〔念仏を〕修める人を見ては腹を立て、怒りを心に抱いて、妨害しようとすることになるのです。この道理をわきまえて、どのように人が申しても、お心だけは動かされてはなりません。かたくなに信じようとしない人は、御仏でさえどうしようもないでしょう。ましてわれわれ凡夫の力ではどうにもならないことです。
このような信心のない人々にも利益を与えようと思うにつけても、早く極楽に往生して覚りを開き、この迷いの境涯に舞い戻って、念仏の教えを謗る者や、信じない者までをも〔覚りの向こう岸へ〕渡し、すべての衆生にもれなく利益を与えようと思うべきなのです。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
法然上人のお弟子や信者の幅は非常に広い範囲に及びます。上は天皇から、下は泥棒、強盗までいるのです。
天野四郎という有名な盗賊の頭が法然上人の念仏の教えを聞いて、今までの罪を悔い改め、念仏の道に入られたというお話が伝わっています。帰依した人の中には遊女もいます。遊女といいましても今でいう売春婦とは大きく異なります。芸をしっかり身につけ、教養もある人たちで、別に「白拍子」とも呼ばれます。そんな遊女も法然上人の説かれる念仏の教えに帰依なさいました。
それから漁師、一般庶民はもちろんのこと、武士が大勢おられます。一般にイメージされる武士は、恐らく 江戸時代の武士、つまり身分の高い武士でありましょう。しかし法然上人がおられた平安末期から鎌倉初期の武士というのは、決して皆から身分が高いと認識されていたわけではありません。かつては地方の豪族であり、また天皇や貴族を守護する立場でありました。それが力をつけて、平氏や源氏を中心に台頭してきたわけです。実際に力は持っていたけれども、他からは「野蛮人」、「教養のない者」という見方をされていたようです。武士自身も自分たちは教養がなく、殺生をなりわいとする罪深い存在であると自覚していたといいます。そういう人達が法然上人の元に集まってこられ、教えを請われました。
多くの武士の中に、津の戸の三郎という武士がおられました。関東の武士ですが、奈良の大仏開眼の際に関西へやって来ました。奈良の大仏は平重衡によって焼き討ちにされたのですが、法然上人とも親しい念仏者、俊乗房重源という方が中心になって寄付を集められ、再興されました。津の戸の三郎公はその開眼法要のために関東から奈良に来たのです。奈良まで来たのだから、名高い法然上人の元を訪ねてみようと思い、上洛なさいます。法然上人は津の戸の三郎公に丁寧に念仏のみ教えを説かれ、津の戸の三郎公は今までの罪を悔いて念仏の教え一筋に生きていかれるようになりました。
津の戸三郎公は、関東に帰ってからも一生懸命念仏に励まれました。熱心に念仏を称えていると、要らぬことを言う人が出て参ります。また、信じてもらおう思って教えを伝えても、そっぽを向かれたり、時には悪口を言う人も出てきます。中には「津の戸の三郎は無智だから、法然上人も南無阿弥陀仏と称えるだけで救われるというような簡単な教えを説かれたのだ。もう少し教養のある人には法然上人も上等の教えを説かれるのだ」などとあらぬ噂を立てる者も出てくるのでした。
津の戸の三郎公は非常に真面目な人であったようです。「もしかしたらその通りかも知れない」と思い、法然上人に質問状を書かれたのです。その質問状に対して法然上人は懇切丁寧なご返事を書かれます。その一節が今日のところです。
冒頭から「左様に」とありますのは手紙に対する返事だから、こういう書き方になるのです。「そらごと」と言いますのは「嘘」のことです。
「そのように嘘をうまく言ってくるような人はかえって哀れむべき、気の毒な人なのですよ」とあります。そんな人が言うことを気にするなと励ましておられるわけです。
「その程度の者が言うことによって、念仏に疑いを持ったり信じないという心を起こす者はどうしようもありません」そんな人が言うことに一々振り回されていてはいけませんということです。
「大方阿弥陀さまに縁が浅く、往生の時期にない者は、教えを聞いても信じることができないし、念仏を称える人を見ては腹を立てたり怒って妨げようとするものです。そういう人がいるということを心得て、どんな人がどんなことを言おうとも、信仰する心だけは揺るがせてはいけませんよ。絶対に信じる気がない人には、仏さまの力さえも及びません。ましてや凡夫の力が及ぶはずはないでしょう」ということです。
カルト宗教の人はよく、無理に信仰させようとするようです。私のところにまで、たまにそういう人が来ることがあります。しかし無理に信仰させようとされるとかえって反発します。法然上人はそうなることをご存じで、決して信仰を無理強いすることは肯定なさいません。無理強いすると相手は反発し、念仏という正しい教えを誹謗する罪を作らせるだけです。だからそっぽ向いている人に無理矢理念仏の教えを説くようなことはありません。それよりも自分の信心をしっかり持つことが大切で、一々違う立場の人が言うことに振り回されることなく念仏するように勧められるのです。
しかし、だからといってそういう人を見捨てるわけではないのです。信じない人に対してどうするかがこれ以降に書かれています。
「このような信じない人々を救おうと思うにつけても、早く極楽へ往生して悟りを開いて、この娑婆世界に再び帰ってきて、念仏の教えを誹謗する人や信じない人を導いて、全ての人々を遍く救おうと思うということが大切なのですよ」と説かれています。
まず自分の信心をしっかり持ってお念仏を称えるのです。お念仏を続ける者は臨終の時に間違いなく極楽へ往生することができます。極楽へ往生したならば、阿弥陀さまが責任持って仏になるまで育てて下さいます。仏になったならば、再びこの世に帰ってくることができます。そういう力が備わった後、この世に帰ってきて、すべての人々を導いてあげればよいのです。私が極楽へ往生することが、しいてはすべての人々を救うことにもなるのです。
極楽へ往生した者はこの世に帰ってきて残された人々を救うことを還相廻向といいます。還相廻向できるということもお念仏のみ教えならではのこと、有り難く頂戴したいものです。
後篇第三十章 廻向
(本文)
当時 日ごとのお念仏をも、かつかつ廻向しまいらせられ候うべし。亡き人のために念仏を廻向(えこう)し候えば、阿弥陀仏、光を放ちて地獄、餓鬼、畜生を照らし給い候えば、この三悪道(さんなくどう)に沈みて苦を受くる者、その苦しみ休まりて命終わりて後 解脱(げだつ)すべきにて候。大経に、もし三途(さんず)勤苦(ごんく)の処(ところ)にありてこの光明を見たてまつらば、皆休息(くkそく)を得てまた苦悩なし。寿終(じゅじゅう)の後、皆解脱を蒙(こうぶ)らんといえり。
(現代語訳)
平生においては、毎日のお念仏をも、ともかくも廻向なさるべきです。亡き人のために念仏を廻向すれば、阿弥陀仏は光を放って、地獄・餓鬼・畜生の境界を照らされますので、この三悪道に墜ちて苦しんでいる者も、その苦しみが和らぎ、命が終わって後にはその境界を逃れることができるのです。
(解説)
今回の御法語のお題は「廻向」です。
廻向という言葉はお寺の法要において聞かれるのではないでしょうか。
墓廻向、塔婆廻向、施餓鬼廻向、それから月参り、お年忌、お盆の棚行など、お寺とお檀家さんとの関わりは殆ど廻向が関係してきます。
廻向というのは、読んで字の如く「回し向ける」という意味です。
何を回し向けるのかと言いますと、功徳を回し向けるのです。
そもそもお念仏は、自分の為の行です。
「阿弥陀さま、この私をお救い下さい」「極楽浄土へ往生させて下さい」という思いで、南無阿弥陀仏と称えます。
自分が極楽浄土へ往生することを願い、念仏を称えることによって、阿弥陀さまの力で極楽へ迎えとっていただけるのです。
つまり阿弥陀さまに功徳をいただくのです。
そうして初めて廻向することができます。
自分の為に念仏を称えなければ、廻向するにも廻向するものがありません。
ここが大切なところです。
まず自分の往生を願ってお念仏を称えるのです。
だから私はいつもお経の本を皆さんにも開いていただき、一緒にお経やお念仏を称えて下さるようにしているのです。
私だけが称えて、私の功徳を廻向してもいいのですが、やはりご先祖さまも、皆さまが称えて廻向して下さったら、益々喜ばれることだと思うのです。
よく、「最近の仏教は堕落していて、先祖供養だけしかしない」などと批判されることがありますが、そういう意味では、先祖供養だけということは成り立たないのです。
自分の為に功徳を積まないと、先祖への廻向はできないのですから。
さて、本文の一行目です。
「常時日ごとのお念仏をもかつかつ廻向し参らせられ候べし」
かつかつというのは、「とりあえず」という意味だそうです。
「いつも、毎日自分の為に称えている念仏だけれども、とりあえず廻向しましょう」ということです。
廻向をよく銀行に預けるお金に喩えられます。
自分の為に貯めているお金、貯金であっても、他人の為に使うことができるわけです。
親や子供のために使うことができます。
それと同じように、自分の為に積んだ功徳を亡き人に回すことができるのです。
ただ、貯金は他人の為に使うと減ってしまいますが、功徳を廻向すると、回向した人に益々功徳が積もるのです。
これはしないと損ですね。
もっとも、そんな気持ちでする廻向ではなく、そのまま差し上げる気持ちで廻向しなくてはなりませんが。
続いて訳します。
「亡き人の為に念仏を廻向したならば、阿弥陀様がお慈悲の光を照らして下さって、地獄、餓鬼、畜生を照らして下さって、その三悪道(地獄、餓鬼、畜生、これを三途ともいう)に沈んで苦しみを受けている者は、その苦しみが休まって、命が終わった後、解脱できます」ということです。
ここでいう命が終わった後というのは、地獄や餓鬼道での寿命が終わったらという意味です。
私達に寿命があるように、もちろん地獄や餓鬼道でも寿命があります。
ただ、地獄や餓鬼道ではよい行いをすることが非常に難しいので、寿命が尽きた後、良いところには生まれにくいのです。
地獄は苦しみばかりの世界です。
苦しみばかりの世界で良いことを行うのは至難の業です。
苦しいと益々悪い行いが重なりますので、また地獄に生まれざるを得ないという悪循環になります。
しかし、念仏を廻向すれば、阿弥陀さまのお力によって、地獄での寿命が尽きたら救い出していただけるのです。
普通解脱というのは、悟りを開くという意味ですが、ここでは地獄、餓鬼、畜生から出るという意味です。
次に根拠が書かれています。
内容はほぼ前文と同じです。
「大経に」とあります。
大経とは、正式には無量寿経といいます。
非常に長いお経なので、通称大経というのです。
「大経に、もし三途の苦しみの世界にあって、阿弥陀様の光を見せていただいたならば、皆安らぎを得て、苦しみ悩みがなくなる。そして命が尽きた後、解脱できますよ」とあります。
往生を願って念仏を称える人は、すぐに極楽浄土へ往生することができます。
100%往生できます。
即得往生といって、死んだらすぐに往生できます。
しかも二度と地獄や餓鬼道といった世界に生まれなくても済みます。
ですから、皆さまのご先祖さまは極楽へ往生されているのです。
しかし、私達の周りには、念仏どころか何の信仰もしないで死んでいく人の方が多いのではありませんか?
そういう人にも、「私が自分の往生の為に称えたお念仏の功徳ですが、どうぞ差し上げます」と廻向させていただくのです。
ではご先祖への廻向は何の為にするのでしょうか。
ご先祖は極楽へ往っておられます。
極楽へ往けば、あとは成仏間違いなしです。
こちらと比べものにならないほど、修行が進んでおられるはずです。
そこに私達が廻向しても、さして役に立たないかも知れません。
しかし、残された者の心情としては、少しでも亡き人の為にして差し上げたいと思うわけです。ですから、「私達の積んだ功徳はあなたにとっては微々たる功徳かも知れませんがどうぞお使いください」と廻向するのです。
無量寿経には娑婆世界で行う善根は浄土で行う善根よりずっと大きな功徳がある、と説かれています。
我々の住む娑婆世界は誘惑が多い、非常に修行がしにくく、善根を積みにくいところです。
そんな場所で極楽往生を願って念仏する人は貴重です。
ですから我々は「こんなわずかな功徳でも」と思いますが、実は大きな功徳となるのです。
そのように廻向すれば、間違いなくご先祖は喜ばれます。「
そっちの娑婆世界の方がよっぽど大変なのに、よく私に廻向してくれた」と喜ばれることでしょう。
そして「その娑婆世界でしっかりと念仏称えて過ごせよ。命尽きたら必ず極楽へ往生できるからな」と極楽からこちらへ廻向して下さるのです。
「益々念仏称えよ」と廻向して下さるのです。
こちらはご先祖のためにと廻向しますが、ご先祖はこちらの為にと廻向して下さるのです。お互いがお互いの為に廻向する、これが有り難いのです。
後篇第二十九章 一蓮托生
(本文)
会者定離(えしゃじょうり)は常の習い、今始めたるにあらず。何ぞ深く嘆かんや。宿縁空(むな)しからずば同一蓮(どういちれん)に座せん。浄土の再会甚だ近きにあり。今の別れは暫(しばら)くの悲しみ、春の夜の夢の如し。信謗(しんぼう)共に縁として先に生まれて後を導かん。引接縁(いんじょうえん)はこれ浄土の楽しみなり。それ現生(げんしょう)すら尚もて疎(うと)からず、同名号を称え、同一光明の中(うち)にありて、同聖衆(どうしょうじゅ)の護念(ごねん)を蒙(こうぶ)る、同法最も親し。愚かに疎しと思しめすべからず。南無阿弥陀佛と称え給えば住所は隔つといえども、源空に親しとす。源空も南無阿弥陀佛と称え奉るが故なり。念佛をこととせざる人は、肩を並べ膝を組むといえども、源空に疎かるべし。三業(さんごう)皆異なるが故なり。
(現代語訳)
会う者が必ず別れるということは世の定めであって、今に始まったことではありません。どうして深く嘆くことがあるでしょうか。過去の因縁が確かなものであるならば、〔極楽に往生して〕同じ蓮の台に座ることができるでしょう。浄土での再会は間もなくのことです。今の別れは、しばしの悲しみに過ぎず、春の夜のはかない夢のようなものです。信じることも謗ることも共に縁として、先立つ者がのこされた者を導きましょう。縁ある人を迎え取ることは浄土での楽しみです。
そもそもこの世にあってさえ浅い関係ではありません。すなわち、同じ阿弥陀仏の名号を称え、同じ阿弥陀仏の光明の中にあって、同じ〔極楽の〕聖衆のお守りを受け、同じ教えを信じる者同士は、この上なく親しい間柄なのです。決して縁が薄いなどと誤解されてはなりません。
南無阿弥陀仏とお称えになれば、住む所は離れていても、私とは親しいのです。私も南無阿弥陀仏とお称えするからです。念仏に専念しない人は、たとえ肩を並べ、膝を交えていても、私との縁は浅いのです。身口意の三業すべてが〔私とは〕かけはなれているからです。
(解説)
法然上人は80年のご生涯でありました。
当時平均年齢が、40何歳であったと言われていますので、相当なご長命だといえます。
上人は御年75歳の時、流罪に遭われています。
その直接の原因は、後鳥羽上皇が熊野詣でしてらっしゃる最中に、後鳥羽上皇が寵愛されていた御所の女官、松虫と鈴虫という姉妹が勝手に出家してしまったことです。
それも法然上人のお弟子の住蓮房、安楽房という二人の元で出家してしまいました。
後鳥羽上皇は、自分の留守中に勝手に寵愛している女官を出家させたことに激怒しまして、住蓮房は近江の馬淵(今の近江八幡)で打ち首になり、安楽房は京都賀茂川六条河原にて処刑されてしまいました。
そして法然上人も師匠としてその責任を負わされて四国へ流罪が決定しました。
同じ時に親鸞聖人他何人ものお弟子が共に流罪になっています。
法然上人は師匠ですから仕方ないのかも知れませんが、親鸞聖人などは直接住蓮、安楽の事件と関係ありません。
なぜ流罪に遭わなければならなかったのでしょうか。これには伏線があります。
念仏の教えがあまりに急激に広まったために、危機感を持った旧仏教、比叡山と南都、特に興福寺が度々朝廷に念仏を止めさせろ、極端な教えを布教する者を罰せよと訴えかけてきました。
念仏を広める者の中には「一度念仏を称えればあとは何をしてもいい」、「念仏称える者以外は救われない」、「阿弥陀仏を信じる者はいかなる悪い行いをしても救われる」といった、法然上人のみ教えに違う教えを説く者もいました。
それを罪とされ、越後、備後や伯耆、伊豆、佐渡などへ流されたのです。
この事件の原因を作った、松虫と鈴虫の姉妹につきまして、広島の方で姉妹共に念仏を称えて過ごし、法然上人が四国の流刑先からの帰りに姉妹の元に立ち寄り、教えを説いたという話があります。
又、大阪に松虫塚というところがあり、姉の松虫がその地で念仏を称えてひっそりと暮らしたなどとも言われています。
阿倍野から阿倍野筋を少し南に行ったところに松虫という交差点があります。
阿倍野筋と松虫通の交差点です。それを少し西に入ったところに松虫塚があります。
能の「松虫」の舞台であるという説もありますが、念仏信仰篤い松虫の住まれたところだと思うと、近くでもありますし親しみを覚えます。
法然上人は当初土佐に流されるというお達しでした。
しかし、法然上人の一番の信者であった九条兼実公が、尽力なさいまして讃岐の国へ流刑先が変更されました。
九条兼実公は、少し前まで関白という、今の総理大臣と比べものにならないほどの権力を持っておられたのですが、失脚なさいまして、このときにはすでに法然上人の流罪を食い止めるほどの力をもっておられませんでした。
しかし、せめて流刑先を自分の領土がある讃岐へと変更するよう奔走なさいました。
しかし讃岐といっても遠いことには変わりありません。今でこそ日帰りで行き来できますが、鎌倉時代のことです。四国へとなると、もう二度と会えない、今生の別れという思いを持たれたことでありましょう。
いよいよ九条兼実公、法然上人をお送りする段になり、嘆き悲しまれます。
その兼実公に対して法然上人が仰ったお言葉が今日の御法語です。
そう思って読めば割と分かりやすい文章です。
読んで参りましょう。
「会者定離は常の習い、今始めたるにあらず。何ぞ深く嘆かんや」
「出会った者はいつか必ず別れる。これは今に始まったことではないでしょう。何を嘆く必要がありましょうか」という文章です。
出会った者はいつか必ず別れる。
そんなことは誰もが分かっているけれども、実際に愛する人と別れると、そんな理屈抜きに悲しいのです。
法然上人もそれは百も承知ですが、兼実公を励ましておられるのです。
「宿縁空しからずば同一蓮に座せん。浄土の再会甚だ近きにあり。今の別れは暫くの悲しみ、春の夜の夢の如し」
宿縁といいますのは過去の縁という意味です。
ということは、今念仏称える縁が未来には極楽浄土での再会という結果を生むことになります。
「今念仏称える縁によって、兼実さん、あなたと私は同じ極楽浄土の蓮の上に生まれることになりましょう。極楽浄土での再会は決して遠い先のことではありませんよ。もう間もなくのことです。今の別れは一時の悲しみ、まるで春の夜の夢のように一瞬のことです」
春の夜は短いものの喩えです。今の別れは一瞬の夢のようなものだ、極楽での再会を楽しみにしましょうよというのであります。
これを一蓮托生と申します。
普通一蓮托生といいますと、まるで共倒れするかのように使われることが多いでしょう。
まるで運命共同体のようなもの。
「お前と運命を共にするよ。一緒に地獄へ供するよ。一蓮托生だ」などと言いますが、全く元々の意味と違うのです。
本当の意味の一蓮托生は、念仏信仰篤い者同士が、間違いなく極楽へ往生することができることを確信して、極楽での再会を約束する、それが一蓮托生です。
「極楽で逢おうね」という念仏者同士の合い言葉です。
これは浄土宗特有の教えで、私は本当に浄土宗でよかったと思います。
これほど情の深い教えを堂々と正面から説くことができるのですから。
一蓮托生を別に倶会一処とも申します。
阿弥陀経に出てくる文言です。
「一つの処で共に会う」一つ処とはもちろん極楽浄土です。
会者定離ですから、出会った者とは必ずいつか別れなくてはなりません。
生き別れ、死に別れ、様々あります。
どんな愛する人とも必ずいつか別れるのであります。
しかし、念仏者同士には永遠の別れはありません。
必ず極楽で再会することができるのです。
「信謗共に縁として先に生まれて後を導かん。引接縁は浄土の楽しみなり」
これもまたありがたい教えです。
極楽へ往った者は、そこでのんびりと過ごすのではありません。
極楽へ往生したならば、すぐさまこの世に帰ってきて、残された人々を導くのです。
往生した人は忙しいのです。
ですから、残された私達は常にそのお導きを感じる用意をしておかなくてはなりません。
先に往生したご先祖が、いつも「念仏称えよ。念仏称えよ」と願い、導いて下さっているのです。
「これも死んだお父さんが念仏称えよと言ってくれてるのかな」「これは先に亡くなった妻が念仏を称えなさいよと伝えようとしてくれてるのかな」と色んな場面で積極的に感じていくことが大切です。
極楽からはいつも間違いなく「念仏を称えてくれよ」とご先祖がお導き下さる。
こちらはいつもそれを感じ取る。感じ取ったならば、そのまま「南無阿弥陀仏」と称えるのです。
ご先祖からのご縁がなければ、なかなか念仏を称えない私達です。
お導きがあるからこそ、こうやってお念仏を称えることができているのです。
ここでは「信謗共に」とあります。
「信じる人」と「謗る人」です。
「信じる人」は阿弥陀さまを信じてお念仏を称えますから、極楽へ往生されます。
しかし「謗る人」は難しいのです。
「念仏なんて嫌いだ」「念仏なんてインチキだ」という人に念仏のみ教えを信じてもらうのは大変なことです。
説得しても逆効果になることの方が多いことでしょう。
しかし、この世では難しくても、自分が先に極楽へ往生したならば、すぐさまこの世へ帰ってきて、信じる人も謗る人も共に念仏の道へ導くことができる。
それが極楽へ往生した後の楽しみだというのです。
法然上人は実際、念仏を謗る人によって流罪に遭われました。
「その人達に念仏のみ教えを説いて念仏信者にすることができればよいが、私の力及ばずできなかった。しかし私が極楽へ往ったならば、信謗共に縁としてどちらも導けるじゃないか。そういう楽しみが極楽にはあるのだよ」と法然上人は仰るのです。
これがまたありがたいのです。
無実の罪で流罪に遭ったことを恨みにも思わず、引接縁によって導きたいなどとはなかなか言えることではないと思います。
「それ現生すら尚もて疎からず、同名号を称え、同一光明の中にありて、同聖衆の護念を蒙る、同法最も親し。愚かに疎しと思しめすべからず」
極楽へ往生した者同士は非常に親しい関係になりますが、今生きている間でも念仏者同士は親密な関係になるということが書かれています。
「今生きている間でも決して遠い関係ではないのだ。同じ名号、つまり南無阿弥陀仏と称え、同じ阿弥陀さまのお慈悲の光の中に照らされて、同じ菩薩さま方のお守りをいただくことができる。同じ教えを信じる者同士は最も親しいのだ。自分が愚かだから親密になれないなどと思う必要はない」お念仏を称えれば、それだけで親しい関係になるのです。
「南無阿弥陀仏と称え給えば住所は隔つといえども、源空に親しとす。源空も南無阿弥陀仏と称え奉るが故なり」
源空といいますのは法然上人のことです。
法然房源空と仰います。
「九条兼実さん、あなたは京都でお念仏をお称えなさい。そうすれば住むところは遠く離れていても、私とあなたの関係は非常に近しいのですよ。なぜならば、私は讃岐の国でお念仏を称えているからです」
「念仏をこととせざる人は、肩を並べ膝を組むといえども、源空に疎かるべし。三業皆異なるが故なり」
「しかし逆にどんなに近くにいて、膝と膝をつき合わせていても、信仰が違う人達とは、念仏者同士ほどには親しくなれませんね。なぜなら、三業がすべて異なるからなんだ」ということです。
三業とは、体の行い、口の行い、心の行いの三つです。
念仏者は、体で阿弥陀さまを敬い、口でお念仏を称え、心で「阿弥陀様お助け下さい」と念じます。
念仏者同士はこの三業がすべてピタッと一致するのです。
しかし念仏の信仰を持たない人とは、どれだけ近くにいても念仏者ほどは親しくなれないわけです。なぜならば、三業が異なり、向かう方向も違うからです。
念仏者の絆は強いのだから、寂しがらなくてもよいですよと兼実公を励ましておられるのです。
兼実公は法然上人より16も年下です。普通に考えますと、75歳の法然上人の方が先に極楽へ往生なさるはずです。
しかし、老少不定、諸行無常のこの世です。法然上人が都を出られてたった20日後に兼実公59歳で往生なさいました。
現実にこの時が今生の別れになってしまったのです。
これを思ってこの御法語を読みますと、益々感慨深くちょうだいすることができます。
お二人、極楽で再会なさっていることでありましょう。
法然上人は讃岐の国ではただ9ヶ月のご滞在でありました。
その後畿内に帰ってきてもよいが、洛内には入るべからずということで、箕面の勝尾寺で4年間滞在なさっています。
勝尾寺も今でこそ車ですぐに行けますが、当時は相当な山奥で、辺鄙なところだったようです。
その後帰洛を許されて戻ってこられた、その地が今の知恩院の勢至堂というお堂の辺りです。
もちろん今のように立派な建物ではなく、雨露を凌ぐ程度の苫屋だったようです。
建暦2年一月25日、西暦1212年極楽へ往生なさいました。
80歳のご生涯でありました。
後篇第二十八章 順逆二縁
(本文)
このたび輪廻(りんね)のきずなを離るること、念仏に過ぎたることはあるべからず。この書き置きたるものを見て、謗(そし)り謗(ぼう)ぜん輩(ともがら)も、必ず九品(くほん)の台(うてな)に縁を結び、互いに順逆の縁 虚(むな)しからずして、一仏(いちぶつ)浄土の友たらん。そもそも、機を言えば五逆重罪を選ばず、女人(にょにん)闡提(せんだい)をも捨てず。行(ぎょう)を言えば、一念十念をも捨てず。これによりて五障三従(ごしょうさんじゅう)を恨むべからず、この願を頼みこの行(ぎょう)を励むべきなり。念仏の力にあらずば、善人なお生まれ難し。いわんや悪人をや。五念に五障を消し三念に三従を滅して、一念に臨終の来迎(らいこう)をこうぶらんと、行住坐臥(ぎょうじゅうざが)に名号を称(とな)うべし。時処諸縁(じしょしょえん)にこの願を頼むべし。あなかしこ、あなかしこ。
(現代語訳)
この生涯を限りに輪廻の絆を離れるには、念仏に勝る方法があるはずはありません。ここに私が書き残したものを見て謗り、非難する者も、必ず浄土の九品の蓮の台に縁を結び、信仰の同じ者も異なる者も互いに縁が実って、同じ阿弥陀仏の浄土の友となるでしょう。
そもそも救われる人はといえば、五逆重罪の悪人をも分け隔てせず、女人や一闡提を捨てることもありません。行はといえば、わずか一声十声の念仏によるのです。ですから、五障・三従の身を恨みに思うべきではありません。この〔念仏往生の〕本願を頼みとし、この念仏の行に励むべきです。
念仏の力によらなければ、善人ですら往生は難しいのです。悪人はいうまでもありません。「五遍の念仏で五障を消し、三遍の念仏で三従を滅ぼして、いっぺんの念仏で臨終の来迎を蒙りたいものだ」と、立ち居起き伏しに、阿弥陀仏の名号をお称えください。いかなる時・場所・場面でも、この本願を頼みとなさってください。あなかしこ。あなかしこ。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
私達のように、素直にお念仏のみ教えをいただく、そういうご縁を「順縁」といいます。
逆に「念仏なんて嫌いだ」「念仏なんて信じられない」と言っていたのに、それがきっかけとなって、念仏信仰に入る、そういうご縁を逆縁といいます。
正しい法を謗ることは「謗法罪(ぼうほうざい)」といって、重い罪です。
しかし、お念仏のみ教えは非常に間口の広い教えで、そういう者でも念仏信仰に入ったならば、救われると説かれるのです。
更には極悪人でも救われるといいます。
もちろんそのままではいけません。
心から今までの罪を悔いて、本気で救いを求め、念仏を称えるならば救われるのです。
そして、こういうことを申しますと、現代では違和感がありますが、「女性も救われる」と書かれています。
今でこそ男女平等が当たり前ですが、この時代は男尊女卑、いやそれ以上です。
女性は救われないかのように言われていました。
ここにあります五障三従という言葉がそれを明らかにしています。
五障といいますのは、女性がなれない五つを指します。
一つは仏になれないといいます。
もちろんお釈迦さまのお弟子には女性もたくさんおられましたし、その方々も悟っておられますから、仏になれるのです。
しかし、法然上人の時代、この当時は仏になれないと言われていたのです。
そして、理想の王様にはなれない、梵天にはなれない、帝釈天にはなれない、魔王になれない、この五つが五障です。
仏の世界、世俗の世界、宇宙、天界、悪魔の世界、どれをとっても極めることができないのが女性なのだということです。
三従といいますのは儒教の考え方で、家にあっては親に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従うという三つです。
今でも「老いては子に従え」などとおっしゃる方がありますが、元々は女性のみに使った言葉です。
失礼な話です。
現代に五障三従などという言葉は通用しませんが、鎌倉時代には女性達は自分たちが五障三従の身であるということを深く自覚していたのです。
そこで法然上人は、「阿弥陀さまは南無阿弥陀仏と称える者を救うとおっしゃっているのです。男は救うけれども女は救わないなどとは決して仰っていないのです。五障三従などということを気にする必要はありません。ただ南無阿弥陀仏と称えて阿弥陀さまにお任せしなさい」とおっしゃったのです。
これには当時の女性達、涙を流して喜ばれたことだと思います。
このようなことをふまえまして、最初から読んで参りたいと思います。
「このたび輪廻の絆を離るること、念仏に過ぎたることあるべからず」
仏教が生まれたインドでは、私たちは生まれ変わり死に変わりを繰り返すと考えます。
仏教もそれを前提としています。
数十年の人生が終わったら、それで終わりではなく、必ず何かに生まれ変わります。
これを輪廻といいます。
今人間として生きていますが、手放しで人生すべて幸せ、とは言い難いのではないでしょうか。
どちらかといいますと、苦しみの方が多いのではないでしょうか。
生まれてきたら一瞬一瞬に老いてゆき、いつか必ず病になり、そして必ず死を迎えます。
また、自分だけが死ぬのではなく、愛する人も命が尽きるときが来ます。
愛する人と必ず別れなくてはなりません。
逆に大嫌いな人とも会わなくてはならない、人間関係の苦しみにも多く遭います。
これも辛いことです。
人を憎むというのは本当に苦しいものです。
そして欲しい物が手に入らないのもこの人生です。
だれも老いたくないのに老いるのです。
病になりたい人なんて誰もいないのにみんな病になるのです。
みんな死にたくないのに必ず間違いなく皆死ぬのです。
この世界が嫌だと言って、自ら命を絶つ方もおられます。
しかしそれで終わりではありません。
これですべて終わるのでしたら、苦しい人にとれば、それも救いなのかも知れません。
でも先ほども申しましたように、何かに生まれ変わるのです。
しかも人間はまだましな方です。
私たちの生まれ変わる先は、行いによって決まるのですが、私達の行いは煩悩による行いばかりです。
人間に生まれ変わるどころか地獄や餓鬼道に生まれ変わるかも知れません。
もし地獄に生まれたら、地獄は苦しみばかりの世界ですから、そこでは善い行いをすることが非常に難しいのです。
善い行いができなければ、地獄から抜け出すことはできません。
餓鬼道に生まれたら、餓鬼道は飢えに苦しみ続ける世界ですから、ここでも善い行いをするのは難しいでしょう。
お腹が減って仕方がない、その時に人のために善い行いをする余裕はないのです。
こういう世界を経巡り続けているのが私たちです。輪廻し続けているのです。
この輪廻の世界から抜け出すのが仏教の目的です。
このご法語のお言葉で言いますと、輪廻の絆を離るる、これが仏教の目的なのです。
お釈迦さまは、この輪廻の絆を離れる方法をたくさん説いて下さったのですが、その一つ一つがとても困難です。
私たちのような難しい修行ができない者、心散り乱れる者、煩悩を断ち切ることができない者には、いくら尊い教えであっても、それらは絵に描いた餅のようなものです。
このような私たちにはお念仏以上に有り難い教えはないのです。
私たちには念仏がぴったりなのです。
それが「このたび輪廻の絆を離るること、念仏に過ぎたることあるべからず」というお言葉です。
「この書き置きたるものを見て、謗り謗ぜん輩も、必ず九品の台に縁を結び、互いに順逆の縁むなしからずして、一仏浄土の友たらん」
「この書き置きたるもの」といいますのは、この文章のことです。
本当はもっと前後に文章があります。
これは一部抜粋しているのです。
このお念仏について書かれたものを見て、悪く言う人達も、何らかのご縁をきっかけにして、極楽とのご縁を結ぶ、つまりお念仏を称えるようになったならば、順縁であろうが逆縁であろうがそういうご縁もすべて成就して、同じ仏の浄土、阿弥陀様の極楽浄土の友になることができるのです、ということです。
「そもそも機をいえば、五逆重罪を選ばず、女人闡提をも捨てず」
機といいますのは、素質とか能力という意味です。器という字の方が意味が明瞭になるかも知れません。
私達たち自分の素質とか能力をみてみると、先ほども申しましたように、救われがたい身なのです。
煩悩多き、愚かな私であります。
それを自覚することは大切なのですが、仏さまからご覧になって、極楽浄土へ迎え取るのにどのような素質能力が必要か。
どのような器の者を救って下さるのかと申しますと、どんな者でもお救い下さるのです。素質や能力は関係ないのです。
ここでは、五逆の者でも救われると書いてあります。
五逆といいますの、親殺し、坊さん殺し、仏教教団破壊、仏様に怪我をさせるといったとんでもない罪です。
それだけで地獄行きなのですが、そういう者でも、その罪を心から悔いて、本気で救いを求めて念仏を称えるならば、阿弥陀さまはお救い下さるのです。
そして当時救われないと言われていた女性も救われますよと書かれています。
「行をいえば一念十念をも捨てず」
法を謗る者、五逆の者、救われないと世間で言われている女性、そういった人たちが救われるというならば、どんなに難しい修行をせよというのかといいますと、一遍や十遍の念仏でも救われると書かれています。
もちろん一遍や十遍称えれば後は必要がないというわけではありません。法然上人のお言葉には一遍、十遍の念仏で往生できるとたびたび出て参りますが、これは最低限ということであります。ご縁が無く、一遍、十遍しか称えることができなかった人でも往生できるという意味です。
具体的にいいますと、臨終間際までお念仏の教えを知らなかったけれども、臨終の枕辺で信仰の篤い人から念仏の教えを聞き、「そんなありがたい教えがあるのか」と知り、「南無阿弥陀仏」と称えた瞬間に死んでしまった、それでも往生できるということであります。私達はご縁があってまだまだお念仏することができるのですから、たくさん称える方がよいのです。一遍の念仏でも往生すると深く信じて、たくさん称えましょうというのが浄土宗のお念仏です。
「これによりて五障三従を恨むべからず、この願を頼み、この行を励むべきなり」
先ほど申し上げました五障三従であります。
「私はなぜ女の身に生まれてきたのか。五障三従の我が身が恨めしい」と嘆く必要はないということです。
ただ阿弥陀さまの本願を信じて念仏に励むべきですよと仰るのです。
「念仏の力にあらずば、善人なお生まれ難し。いわんや悪人をや」
念仏の力でなかったら、善人だって往生することは難しいでしょう。
ましてや我々のような悪人は当然往生し難いでしょう。
念仏だからこそ私たちは往生することができるのですよということです。
「五念に五障を消し、三念に三従を滅して、一念に臨終の来迎をこうぶらんと、行住坐臥に名号を称うべし。時処所縁にこの願を頼むべし。あなかしこ、あなかしこ」
五念といいますのは、五遍の念仏、三念といいますのは三遍の念仏です。
五遍の念仏で五障が消え、三遍の念仏で三従が消えると書かれていますが、これは語呂合わせです。
実際には五障も三従も関係ないということです。
「あなたは五障だ三従だと言って気にしているけれども、そんなもの関係ないですよ。五遍三遍の念仏で消えてしまいますよ」というほどの意味です。
「一遍の念仏でも阿弥陀さまがお迎え下さると信じて、行住坐臥に念仏を称えましょう。いつでもどこでもどんな時でも阿弥陀様の本願を頼りにしましょう。ああ恐れ多いことですね」ということです。
結局、念仏を謗る者も、五逆の者も、女性もみんな救われますよ、ということです。
私たちは勝手に、男や女や、金持ちや貧しいや、家柄が良いや悪いや、頭が良い悪いやと言って違いを見つけて、区別、差別します。
でも阿弥陀さまからご覧になれば、どれもドングリの背比べなのです。
「賢い、金持ちだと言っている者は自分の力で輪廻の絆を断つことができるか、できないであろう。皆煩悩多き、悟りとは程遠い者ばかりではないか。自分の力に頼ることなく、私を信じて念仏を称えよ」と言って下さっています。
すべての者をお救い下さるのが、阿弥陀さまなのです。
後篇第二十七章 転重軽受
(本文)
宿業(しゅくごう)限りありて受くべからん病は、いかなる諸々の佛、神に祈るとも、それによるまじき事なり。祈るによりて病も止み、命も延ぶる事あらば、誰(たれ)かは一人(いちにん)として病み死ぬる人あらん。況や、又佛の御力(おんちから)は念佛を信ずる者をば、転重軽受(てんじゅうきょうじゅ)といいて、宿業限りありて重く受くべき病を軽く受けさせ給う。況(いわん)や非業(ひごう)を払い給わん事ましまさざらんや。されば念佛を信ずる人は、たとえいかなる病を受くれども、皆これ宿業なり。これよりも重くこそ受くべきに、佛の御力(おんちから)にてこれほども受くるなりとこそは申す事なれ。我らが悪業深重(じんじゅう)なるを滅して、極楽に往生する程の大事をすら遂(と)げさせ給う。ましてこの世にいく程ならぬ命を延べ病を助くる力ましまさざらんやと申す事なり。されば後生(ごしょう)を祈り本願を頼む心も薄き人は、かくの如(ごと)く囲繞(いにょう)にも護念にもあずかる事なしとこそ善導は宣(のたま)いたれ。同じく念佛すとも、深く信を起こして穢土(えど)を厭(いと)い、極楽を願うべき事なり。
(現代語訳)
前世の悪業の報いが定まっていて、受けねばならない病は、いかなる仏や神に祈ったとしても、それに左右されることはないでしょう。祈ることで病気も治り、寿命も延びるというのであれば、誰一人として病気になる人も、死ぬ人もいないでしょう。
その上、阿弥陀仏の御力は、念仏を信じる者を、「転重軽受(てんじゅうきょうじゅ)」といって、悪業の報いが定まっていて重く受けるはずの病を、軽く受けるようにして下さいます。ましていわれのない禍を防いでくださらないはずはありません。
ですから念仏を信じる人は、たとえいかなる病を受けても、「すべてこれは過去に私が犯した悪業の報いである。これよりも重く受けるはずが、仏の御力でこの程度に〔軽く〕うけるのだ」と言うものなのです。
私たちの深くて重い悪業を滅して、極楽に往生するほどの重大な事ですら成し遂げさせて下さいます。まして、この世のわずかな寿命を延ばし、病を治す力がないはずがあろうかというものです。ですから「来世を祈って本願を頼みとする心が薄い人は、このように仏・菩薩に取り囲まれることも守られることもない」と善導大師は言われたのです。同じように念仏をしても、深く信心を起こしてこの穢土を厭い、極楽を願うべきなのです。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
今月のご法語は、先月のご法語、後編第26章の続きです。
知恩院のご法語集は、あらゆるご法語の中から部分的にピックアップしたもので、続きになっているものは少ないのですが、今回のご法語は前回から直接続いています。
ですから内容も同じようなものになっています。
前回は「仏神擁護」という題のご法語でした。往生を願って念仏を称える人は、自然と仏さまや神さまに守られるという内容でした。
あくまで極楽への往生を願って称えるわけです。
往生を願って称えていると、求めずとも得られる、不求自得の功徳が得られる、知らない内に、色々と守られる、ということです。
今回は、「転重軽受」という題のご法語です。重きを転じて軽きを受ける、いわゆる大難を小難に変えるという意味なのですが、もちろん、ただ単に「念仏を称えていたら、病気が軽くなる」などというような単純なものではありません。
このことにつきまして、順を追って説明して参りたいと思いますが、今回はすべて訳すとかえって煩雑になりますので、掻い摘んで申し上げます。
まず、「宿業」というものがあるというのです。
「宿業」の「業」というのは、行いのことです。
「業が深い」などと申しますが、業は悪いものとは限りません。
善い業を善業といい、悪い業を悪業といいます。
この業によって、我々の将来、未来が決まります。
善い業を起こせば善い結果が出るし、悪い業を起こせば苦しみがやってきます。
善因楽果、悪因苦果といいます。
今起こした業の果は、一瞬後に生ずる場合もあれば、十年後になる場合もあり、更には来世、来来世に持ち越される場合もあるといいます。
でも善悪どちらかの業を起こせば、必ず将来、果が生ずるのです。
業は体と口と心で起こします。
毎日、相当な数の業を重ねていますが、その一々の果が必ず出てくるのです。
だから仏教では、「善いことをしましょう、悪いことは止めましょう」というのです。
よく「短い人生、楽しいことをして美味しい物を食べて暮らす方が賢い」などと言う人もありますが、仏教を信じる者は、今善い行いをして、悪い行いを止めなくてはなりません。
また、「親の因果が子に報い」などと聞くことがありますが、これは仏教ではありません。
仏教は「自業自得」を説きます。
親の因果は親に来ます。
子の因果は子に報いが来るのです。
自分で行った行いの果は、必ず自分に返ってきます。
自分が行ったことは、自分が責任を持たないといけないのです。
ただ、業とは別に「縁」というものがあります。
親が善い育て方をすることによって、善い行いをするようになったり、逆にひどい目にあって悪い行いをするようになる場合もあります。
縁は親に限らず、色んな人から、色んなものから得ます。
何もしないという縁もあります。
声を掛けようと思ったけれども止めた、そのことによって変わる場合もあります。
更には、どの国に生まれるか、どの時代に生まれるかという縁によって、大きく変わります。
戦争中に生まれ育って、兵隊に行かなくてはいけないような縁に遇ってしまうと、嫌でも人を殺してしまう、ということもあり得ます。
縁によって、避けられない状況になったとしても、最終的に「殺す」という業を起こしたら、自分に果がもたらされるのです。
業を因として果がもたらされるのを、因果の法則、因果応報といい、因と縁を合わせて因縁といいます。
よくご存じの言葉だと思います。
今行ったことによって未来が決まると申しましたが、逆に今起こっていることは、過去の業によるのです。
今苦しい思いをしているのは、過去に悪業を行ってきたからだといいます。
生まれてから今までの業かも知れませんが、前世の業かも知れません。
前世、前前世、過去世の業を宿業というのです。
過去世の縁を宿縁といいます。
このご法語の最初には、今病気になっているのは、宿業によるのだ、だから神や仏に祈っても仕方がないのだと書かれています。
宿業によるものだから、自分が報いを受けなくてはならないのです。
とても厳しいことです。
続けて祈って病が治るのであれば、誰が病になるのですか、祈って寿命が延びるのであれば、誰が死ぬのですかと書かれています。
そうであればお医者さんも必要ないのですから。
ただ、阿弥陀さまに病気を治したり寿命を延ばす力がないというのではありません。
阿弥陀さまには大きな力があるのです。
私達の業は、煩悩による業ばかりですから、善い業は殆ど積めないのに、悪い業はどんどん積もっていきます。
因果の法則からしますと、とても極楽へ往けるような業を私達は積んでいないのです。
しかし阿弥陀さまは「我が名を呼ぶ者、南無阿弥陀仏と称える者を極楽へ迎え取ろう」と言って下さっています。
自分の力のみではとても極楽へなど往けない私達を、因果の法則を超えてまで救って下さる力があるのです。
私達の積もり積もった悪業を払いのけて、極楽へ迎え取って下さるのです。
それほどの力をお持ちですから、私達の病気を治したり、寿命を延ばすぐらいはたやすいことなのです。
でもそうはなさらないのです。
なぜでしょうか?
それは、病気を治したって、寿命を延ばしたって、幸せにならないからです。
病気を治したら幸せになりそうにも思いますが、果たしてそうでしょうか?
病気が治ったことは嬉しいけれども、病気が治ってもまた次から次に苦しみや悩みがやってきます。
また病気になりますし、老いの苦しみがあります。
愛する人とも別れなくてはならないでしょうし、逆に大嫌いな人と会う、人間関係の苦しみも起こり得ます。
病気が治っても根本的に苦しみを無くすことにはならないのです。
阿弥陀さまは極楽への往生こそ幸せなのだとおっしゃるのです。
「娑婆世界はは苦しいであろう。悲しいであろう。その娑婆世界を念仏称えて乗り切ってくれよ。必ず極楽へ迎え取ってやるから。絶対の幸せの世界、極楽浄土へ迎え取ってやるから」と願って下さっているのです。
極楽へ往くにはどうするか。
もちろんお念仏です。
阿弥陀さまはお念仏を称える者を、益々お念仏が称えられるようにして下さるのです。
重い病気であれば、とてもお念仏など称えることができないかも知れません。
でも阿弥陀さまがこの程度にして下さった、だからまだお念仏を称えることができる。
阿弥陀さまがまだお念仏を称えることができるようにして下さったのだ!と思って、益々お念仏を称えることが大切なのです。
これは人に言われてもなかなか実感できないでしょう。
お見舞いに来た人に「このぐらいで済んでよかったですね。もっとひどい人はたくさんいますよ」などと言われたらムッとするかもしれませんね。
これは所詮軽く済んだ場合にはムッとするだけで収まるでしょうが、余命1ヶ月という人に、「まだ1ヶ月あってよかったですね」などとは絶対に言えないでしょう。
これは日頃からお念仏している人が、経験的に何度も「助けられた!」という実感があり、今回病気になったけれども、本当ならばもっとひどい病気になるところをこのぐらいにして下さったのだ、まだまだお念仏を称えることができるようにして下さったのだ、と思うことができるようになるということです。
念仏信者にとっては、阿弥陀さまに助けられたという証拠はいくらでもあるでしょう。
ただ極楽浄土へ往生したいと思ってお念仏を称えているだけなのに、何度も何度も助けてもらっているという経験があってこそ言えることなのです。
このご法語の題、転重軽受というものは、ただ単に「お念仏を称える人は病気が軽くなります」ということではないと先に申し上げました。
往生を願ってお念仏を称えている人が、知らず知らずの内に助けていただいていることを実感し、宿業からいえば、もっともっと重い病気になっていても仕方ないのに、軽くして下さって、お念仏を称えることができるようにしていただいたということを感じることができることなのです。