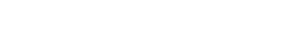後篇第二十六章 仏神擁護
(本文)
弥陀の本願を深く信じて、念佛して往生を願う人をば、弥陀佛よりはじめ奉りて、十方の諸佛諸菩薩、観音勢至、無数(むしゅ)の菩薩、この人を囲繞(いにょう)して、行住坐臥(ぎょうじゅうざが)夜昼をも嫌わず影の如くに添いて、諸々の横悩(おうのう)をなす悪鬼悪神(あっきあくじん)のたよりを払い除き給いて、現世(げんぜ)には横さまなる煩(わずら)いなく安穏(あんのん)にして、命(みょう)終(じゅう)の時(とき)は極(ごく)楽(らく)世(せ)界(かい)へ迎(むか)え給(たも)うなり。されば念(ねん)佛(ぶつ)を信(しん)じて往(おう)生(じょう)を願(ねが)う人(ひと)は、ことさらに悪魔を祓(はら)わんために、万(よろず)の佛、神に祈りをもし慎みをもする事はなじかはあるべき。いわんや、佛に帰(き)し、法に帰し、僧に帰する人には、一切の神王(しんのう)、恒沙(ごうじゃ)の鬼神(きじん)を眷属(けんぞく)として、常にこの人を守り給うといえり。然(しか)ればかくの如きの諸佛諸神囲繞(いにょう)して守り給わん上は、又いずれの佛、神かありて悩まし妨ぐる事あらん。
(現代語訳)
阿弥陀仏の本願を深く信じ、念仏して往生を願う人については、阿弥陀仏をはじめ、あらゆる世界の諸仏・諸菩薩、観音・勢至〔などの〕無数の菩薩が、この人を取り囲み、立ち居起き伏し、昼夜を問わず影のように寄り添って、様々な思わぬ悩みごとをもたらす悪鬼・悪神のつけ入るすきを払い除き、現世において不当なわずらいもなく、平穏無事に過ごさせ、命の終わる時には極楽浄土へお迎え下さるのです。
それゆえ念仏を信じて往生を願う人は、ことさら悪魔を払い除くために数多くの仏や神に祈ったり、物忌みしたりする必要がどうしてあるでしょうか。まして、「仏に帰依し、仏の教えに帰依し、仏教教団に帰依する人については、あらゆる神王が無数の鬼神たちを引き連れて常にこの人をお守りになる」と説かれています。
ですからそのような諸仏や諸神が取り囲んでお守り下さるからには、その上どのような仏や神があって悩まし妨げることがあるでしょうか。
(解説)
今回のご法語には「仏神擁護」という題がついております。
お念仏を称える者には仏さまや神さまからのお守りがあるというのです。
ただ、お守りがあると言っても、浄土宗の目的はあくまで極楽へ往生することです。
ですからお念仏を称えていても「阿弥陀さま、どうか病気が治りますように!」と願ってお念仏を称えるのありません。
「阿弥陀さま、どうか大学に合格させて下さい!」と願うのでもありません。
たまにお仏壇に宝くじを供える方がありますが、これもちょっと違います。
もし阿弥陀さまに祈って宝くじを当てて下さったら、どんどん欲望が増えてしまいます。
しかしお金持ちになったら幸せになるかというと、決してそうとは限らないでしょう。
阿弥陀さまが大学に合格させて下さるなら、だれかを阿弥陀さまが落とさないといけなくなります。
阿弥陀さまはそんなことはなさいません。
阿弥陀さまが病気を治して下さっても、いつか必ず、誰もが死にます。
だからといって、極楽に往生すること以外に何もないかというと、決してそんなことはないのです。
極楽への往生を願ってお念仏を称えている内に、自然と得られる功徳はあるといいます。不求自得の功徳といいます。
求めずとも自ずと得られる功徳です。
現代においては、洗濯するのに洗濯機を使うことが多いですが、昔は洗濯板を使って、手で服を洗っていました。
これはあくまで服をキレイにすることが目的です。
しかし、服をキレイにしようとして洗っているのに、気が付くと手までキレイになっています。
手をキレイにしようなんて思っていないのに、キレイになっています。
これと同じように、目的はあくまで極楽への往生です。
往生したいと願ってお念仏を称えているのに、気が付いたら、「色々と守られているなあ」「あれもこれも仏様のお守りなんだなあ」と感じることがあります。
そのような、求めていないのに自ずと得られる功徳というものがあります。
本日の御法語は、往生を願ってお念仏を称えていると、自然と阿弥陀さまをはじめ、色々な仏さま、菩薩さま、神々から守られる、ということについて書かれています。
本文を見て参ります。
「阿弥陀さまの本願を深く信じて、念仏を称えて往生を願う人は、阿弥陀さまをはじめ、あらゆるところにおられる仏さま方、菩薩さま方、観音菩薩さま、勢至菩薩さま、無数の菩薩さま方がこの人を取り囲んで下さり、歩いていても立ち止まっていても、座っていても寝転がっていても、夜昼も関係なく、陰の如くに寄り添って下さって、色んな悩みを作る悪鬼、悪神なのどの魔を払い覗いて下さり、現世には余計な煩いなく、心安らかに穏やかにしていただいて、命終わる時には極楽浄土へ迎え取って下さるのです。
だからお念仏を信じて往生を願う人は、ことさらに悪魔を払おうとして、仏や神に祈ったり慎んだりする必要はないですよ」ということです。
私達は、厄年だとか、前厄だなどと気にしたり、嫌なことが続くと「厄払いしてもらいなさい」などと言ったり、テレビで占い師やスピリチュアル系のタレントが言ったことを一々気する人もあります。
しかしお念仏を称える者には、自然と魔が寄りつきませんから、そんなことは一切する必要がないのですよ、というのです。
「ましてや仏に帰依し、仏が説かれた法に帰依し、仏が説かれた教えに順う僧、これはお坊さんに限らず仏教徒がお互いを敬い合う、そういう者を、一切の神々と神々に付き従う数え切れない程の鬼神達が常に守って下さるといいます。だからこのように仏様や神様が守って下さるのですから、神様や仏様に悩まされることがありましょうか」ということです。
よく罰があたるとかいいますが、お念仏を称える者を神や仏が守って下さるのですから、なぜ守って下さる方が罰をあてるようなことをしますか、するはずがないでしょう、という意味です。
「うちの母はあれだけ信心深かったのに、なぜあんな死に方をしたのでしょうか」とか、「うちの母はお墓参りに向かう途中、タクシーから下りた時に転けて骨折しました。何で良いことをしているのにこんな目に遭わないといけないのですか。神も仏もないんじゃないですか!」と言われたことがあります。
しかし、念仏信仰の篤い人は絶対にこんなことは言いません。
法輪寺のお檀家さんに大阪の○○さんというとても信心深い方がおられました。
このおばあさん、大きな体ですが、自転車に乗っておられました。
転けたら危ないですよといつも言うのですが、足が悪いから自転車に乗る方が楽だとおっしゃいます。
心配していた通り、ある時自転車で転けて大腿骨を骨折なさいました。
お見舞いに行き「奥さん、えらい目に遭いましたなあ」と私が言いますと、○○さんは「おっさん、えらい目に遭いましたわ。でもいつもお念仏称えさせていただいて、仏さんが守ってくれたはるから、このぐらいの怪我ですみました」とおっしゃるのです。
大腿骨骨折といったら大けがです。
○○さんは日頃から、「言ったらきりがないくらい、今まで守ってもらいました。どんだけ助けてもろたか」とおっしゃいます。
今までお念仏を称えてきて、実際に守ってもらった、助けてもらったという実感があるからこそ言える言葉です。
○○さんの性格が良いだけではないのです。
実際の経験上、守ってもらっていることを感じるのです。
これは気持ちの問題などということではありません。
「大けがしたけれども、考え方によったら死ななくてよかったよ。そう思わなくちゃ」などと人から言われても痛いものは痛いのです。
そんなこと言われたら腹が立つことでしょう。
自分でそのように考えようとしても、限界があります。
あくまで極楽への往生を願ってお念仏を称える者が、「ああ、やっぱり守られているな」と気付くことなのです。
しかしこれも信心のない人に言うと、誤解を招きかねません。
「うちのおばあさん、あんなに大けがしてるのにまだあんなこと言うてるわ」と言って馬鹿にしたり、逆に「怪我や病気を軽くしてもらえるのか、それなら念仏を称えよう」などという人が出てくるので、かえってこういうことを言わない方がよいのかも知れません。
病気や怪我が治ると信じて念仏を称えていて、大けがをしたら、「なんや!ちっとも効果ないやんか!」となるのがオチです。
あくまで極楽への往生を願ってお念仏を称える、その副産物だということを忘れてはなりません。
後篇第二十五章 護念増上縁
(本文)
問うていわく、摂取(せっしゅ)の益(やく)をこうぶる事は、平生(へいぜい)か臨終かいかん。
答えていわく。平生の時なり。そのゆえは、往生の心まことにて我が身を疑う事なくて来迎(らいこう)を待つ人は、これ三心(さんじん)具足(ぐそく)の念佛申す人なり。この三心具足しぬれば、必ず極楽に生まるという事は観経(かんぎょう)の説なり。かかる志ある人を阿弥陀佛は八万四千の光明を放ちて照らし給うなり。平生の時照らし始めて、最後まで捨て給わぬなり。故(かるがゆえ)に不捨(ふしゃ)の誓約と申すなり。
(現代語訳)
問い。阿弥陀仏の救いの利益を蒙るのは、平生か臨終か、どちらでしょうか。
答え。平生の時です。つまり、往生を願う心に偽りがなく、わが身〔の往生〕を疑わずに来迎を待つ人は、三心を具えた念仏を称える人です。この三心を具えているならば必ず極楽に生まれるということは『観無量寿経』の説です。
このような志のある人を、阿弥陀仏は、八万四千の光明を放って照らされるのです。平生の時に照らし始めて、臨終までお捨てになりませえん。ですから「〔念仏者を救い取って〕捨てることがない誓約」というのです。
『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊
(解説)
今回の御法語は問答形式になっています。
お弟子が法然上人に質問されて、それに法然上人がお答えになっているというものです。
どういう質問かと申しますと、「問うていわく、摂取の益をこうぶることは平生か臨終かいかん」
摂取というのは「すくい取る」という意味です。
ビタミン摂取などとは意味が違います。
「阿弥陀さまがお救い下さるのは平生ですか、それとも臨終の時ですか?」という質問です。
念仏を称える者は、臨終の時に阿弥陀さまがお迎え下さり、臨終の時に極楽浄土へ往生させていただけます。
それならば答えは臨終ではないか?と思われるかも知れません。
しかし答えは違います。
「答えていわく、平生の時なり」とあります。
その理由が書かれています。
なぜならば往生の心が誠でとありますが、これは「本気で極楽への往生を願う」ということです。
そして「我が身を疑うことなく」というのは、「偉い坊さんは往生できるでしょうが、私のような者は往生できません」と思ってはいけない、いうことです。
極楽へ往くのは自分の力ではありません。
極楽へ往くのは阿弥陀様の力です。「私みたいな者は往けない」というのは、即ち「阿弥陀さまは私みたいな者は救えない」と阿弥陀さまの力を疑うということになります。
阿弥陀さまの力を疑ってはいけません。
「こんな愚かな私であるけれども、阿弥陀さまのお力によって必ず救っていただける」と深く信じなくてはいけません。
そして「来迎」、つまり阿弥陀さまのお迎えを待つ人は、「三心具足の念佛者」だといいます。
三心というのは一枚起請文にも「三心四修と申すことの候はみな決定して…」とるように、念仏者が具えなくてはならない三つの心です。
三心が具わった念仏を称えないと往生できないのです。
三心は「至誠心」「深心」「廻向発願心」の三つです。
「至誠心」は誠の心、「深心」は深く信じる心、「廻向発願心」は往生を願う心です。
必ず具えないといけない三つの心なのですが、この言葉自体が大事なのではなく、この心を具えることが大事なのです。
先ほど申した、往生の心が誠で我が身を疑うことなく、阿弥陀さまのお迎えを待つ人は、そのままで三心が具わった人です。
つまり「極楽へ往生させて下さい。
阿弥陀さまは私のような者でも必ず救って下さる。阿弥陀さまいつか必ずお迎え下さい」と思って念仏称える人は三心具足の念仏者なのです。
この「三心を具えれば必ず極楽へ往生する」ということは、『観経』というお経に書かれていますよと書いてあります。
『観経』は『観無量寿経』の略です。
このような志、つまり「三心を具えた念仏を称える人を阿弥陀さまは八万四千ものお慈悲の光でもって照らして下さっているのだ」と書かれています。
そしてそのお慈悲の光は、平生の時に照らし始めて最後臨終の時まで決して見捨てられない、だから不捨、「見捨てない約束」というのですよ、と説かれています。
念仏を称える者はやはり臨終の時に阿弥陀さまがお迎え下さって、臨終の時に極楽浄土へ往生するのです。
しかし、三心具足の念仏者はもうすでに平生の時に「往生間違いなし」の立場です。
三心具足の念仏を申す人を阿弥陀さまは「よく念仏を称えてくれた、そのまま死ぬまで続けろよ」とずっとお慈悲の光で照らして見守り続けて下さるのです。
『観無量寿経』に「光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨」とあります。
「阿弥陀さまのお慈悲の光は遍く十方の世界を照らして下さって、念仏を称える人々を救いとって捨て給わない」のです。
この「摂取」はまさに御法語の冒頭の質問にある「摂取」で、「不捨」は御法語の最後にある「不捨」なのです。
「救いとって決して捨てない」というお約束なのです。
昔から阿弥陀さまのお慈悲を母親がわが子を思う心に喩えられました。
「母心」です。
最近ではそれすらも通用しにくいようになったかもしれません。
あるお子さんを持つ女性が「男の人にはこの感覚わからないと思います。自分の中に命がある感覚。愛おしくて仕方ない」とおっしゃっていました。
そして「できたらこのままずっとお腹の中で育てたい」とまでおっしゃいました。
「産んでしまうとみんなのモノになるけど、お腹の中にいたら「私だけのモノ」でいられるからだ」と言うのです。
確かに母心は温かいものでしょう。
きっと多くの母親は、わが子を心から慈しんでおられることでしょう。
しかし、母心は「我が子限定」なのです。
他人の子も不幸になって欲しいとは思わないけれど、我が子と同じようにはいきません。我が子は「我がモノ」なのです。
「私の家」「私の財産」「私の家族」「私の子」です。
「我が子」は「私」なのです。
だから我が子が傷つけられると悲しいし腹が立ちます。
だから実は母心は「慈悲」ではなく、「執着」なのです。
仏さまのお慈悲とは全く異質なのです。
阿弥陀さまのお慈悲は平等の慈悲です。
すべての者を救って下さるお慈悲です。
だから、難しい修行はご用意されなかったのです。
難しい修行を用意したら、この人にはできるけれどもこの人にはできない、などということになります。
あるいは誰もできないということになります。
しかし、「私の名前なら呼ぶことができるであろう」とお考え下さったのです。
子どもでも「お母さん!」、「ママ!」と呼ぶことができるように、「南無阿弥陀仏!」と称えてくれと仰ったのです。
そしてそのたった六文字の中に、ご自身がご修行下さった功徳すべてを納め込んで下さいました。
私達ならば、自分が一生かけて貯めてきた財産があって、人に施そうと思うのに、わずかしか施さないくせに施したような気になってしまうかもしれません。
たくさんあっても出し惜しみしてしまうかもしれません。
しかし当然阿弥陀さまは出し惜しみされません。
ご修行下さった功徳すべてを惜しげもなくすべて詰め込んで下さったのです。
だからお念仏は最も簡単でありながら、最も優れた功徳があるのです。
ですから「私なんてとても往生できません」などと思うのは、阿弥陀仏のお慈悲とお力を見くびっているのと同じことです。
。
今村組というダンスチームを作って、不登校の子やぐれた子に一つのことに打ち込むことを教えておられる、今村克彦という元小学校教諭がいます。
見た目は。髪の毛を伸ばし、髭を生やして、サングラスをかけて、とても元小学校の先生とは思えません。
しかし本気で子ども達を愛しておられる良い先生です。
いじめをテーマにした討論番組に今村先生も出ておられました。
今村先生は、自分の生徒がいじめられていたら、その子に「お前の力でどうしようもなくなったら俺のところに来い。絶対助けてやるから」って言うのだとおっしゃっていました。するとその番組に出ていたタレントが、「先生、そうおっしゃいますが、私は以前息子に、あんたがいじめられたらお母さんに絶対言いや、お母さんが絶対助けたるって言ったんです。そしたら息子は、お母さん、そんなことしたら余計にいじめられるねんでって言いました。今村先生、子どもにとってはもっと難しい問題なんと違いますか?」と仰いました。
すると今村先生は、「そんな中途半端なことと違うんですよ。今の親御さんは、自分の子がいじめられたらすぐに学校に怒鳴り込んできて、学校のせいにし、いじめた相手を追求します。でもそんなことをしてもいじめは無くなりません。いじめてる子にも心の傷がある。それはそれで罰を与えるだけじゃなく、きっちり対処しなくてはなりません。いじめられている子には、いざとなったら、限界がきても必ず、絶対に助けたる!と本気で思い、それを伝えるんです。子どもには絶対に伝わりますよ。子ども達はその言葉を励みに頑張ってくれるんですよ」と仰いました。
阿弥陀さまのお慈悲もそうなのです。
この世はやはり苦しみ迷いの世界です。
娑婆世界です。
子どもの時に悩んでいたことは今考えたら馬鹿馬鹿しいモノもたくさんあります。
今悩むようなことも八十歳ぐらいになって思い出したらつまらないことになるのかも知れません。
でも年を取ったら悩みが無くなるかと言ったら決してそんなことはないでしょう。
逆に年齢を重ねるごとに体は弱り、思い通りにいかないことが増えてくる、愛する人との別れも多く重なってきます。
阿弥陀さまはこの世でもがいている私達をみて、「苦しいであろう、悲しいであろう。その中で念仏を称えて乗り切ってくれ。私が見守っているぞ。そして最後には絶対の幸せの世界、極楽浄土へ迎えとってやるから、それまで念仏を称えて乗り切れよ」とずっと励まして下さっているのです。
まるでいじめに遭った子が「絶対に助けてやるから」と言われて頑張るように、私達も「必ず命尽きた時には極楽浄土へ迎えとってやる」という阿弥陀さまの約束、「不捨の誓約」を頼みにお念仏を称えてこの世を乗り切っていきたいものです。
後篇第二十四章 滅罪増上縁
(本文)
五逆罪(ごぎゃくざい)と申して現身(うつしみ)に父を殺し母を殺し、悪心をもて仏身(ぶっしん)を損(そこ)ない、諸宗を破りかくの如く重き罪を作りて、一念懺悔(さんげ)の心も無からん、其(そ)の罪によりて無間(むけん)地獄に落ちて、多くの劫(こう)を送りて苦を受くべからん者、終わりの時に善知識の勧めによりて、南無阿弥陀仏と十声(とこえ)称(とな)うるに、一声(ひとこえ)に各々八十億劫が間生死(しょうじ)に巡るべき罪を滅して、往生すと説かれて候うめれば、さほどの罪人だにもただ十声一声の念仏して、往生はし候え。誠に仏の本願の力ならでは、いかでかさること候うべきと覚え候。
(現代語訳)
〔『観無量寿経』には、〕「五逆罪といって、この生涯で父を殺し、母を殺し、〔覚りを開いた仏弟子を殺し、〕悪意をもって仏の身体を傷つけ、諸宗の和を乱すという、このような重い罪を犯しながら、少しの懺悔の心もなく、その罪によって無間地獄に墜ちて、非常に長い間、苦を受けるはずの者が、命の終わる時に、善知識の勧めによって、南無阿弥陀仏と十声称えると、一声ごとに八十億劫もの長い間、迷いの境涯を輪廻する原因となる罪を滅して往生する」と説かれていますので、「それほどの在任でさえも、ただ十声一声の念仏で往生することが出来る。本当に阿弥陀仏の本願〔の力〕によるのでなければ、どうしてこのようなことがあり得ようか」と思われます。
(解説)
私達が善悪の判断をする基準に法律があります。
しかし法律は時代によって中身が変わります。
そしてその法律を変えるものは私達の価値観です。
価値観もまた時代によってころころと変わります。
例えばたばこです。
20年ほど前まではたばこを吸う人は堂々と吸っていました。
しかし今はどうでしょうか。
たばこを堂々と吸っているだけで「ひどい!あの人堂々とたばこ吸ってる!」と言って、たばこを吸うだけでまるで悪人のような扱いを受けてしまいます。
今たばこを吸う人が肩身の狭い立場に追い込まれているのを見ますと「気の毒に」と同情してしまいます。
同じ「たばこを吸う」という行為でありながら、時代によって扱いが変わるわけです。
平和な時代の価値観と戦時中の価値観では大いに異なるでしょう。
平和な世の中で、3人、4人の人を殺めたらほぼ死刑になることでしょう。
実際に死刑にならなくても判決上はほぼ死刑です。
しかし、戦争中に敵兵を100人殺したら英雄になれるのです。
これはおかしなことです。
同じ殺人です。
殺人は絶対悪だと思いますが、戦争中に敵兵を殺すことは善になるのです。
このように時代や状況によって善悪が変わるのはなぜでしょう。
それはとりもなおさず私達には善悪の判断を下す力がないということではないでしょうか。
仏教では良い行いをすれば良い結果が出る、悪い行いをすれば悪い結果が出ると教えられます。
因果応報といいます。
すべて自分の行いは自分に返ってきます。
自業自得といいます。業は行いの意味です。
それはこの世だけでなく、前世、前前世、ずっと昔から生まれ変わり死に変わりしてきた中の結果が今出ていると考えます。
良い行いをすれば良いところに生まれ変わり、悪い行いをすれば悪いところに生まれ変わるのです。
良い行いをしていれば天や人間に生まれ、悪い行いをしていれば地獄や餓鬼道、畜生道に生まれ変わります。
しかし、それが分かっても、私達には善悪の判断がつかないわけですからどうしようもありません。
そこで仏教では「これはやってはいけません」という教えを説きます。
その中でも最も悪い行いを五逆といいます。
それが今日のテーマです。
五逆というだけあって五つあります。
「これをやったら必ず地獄行き」という行いです。
まず父親殺し、母親殺しです。
両親がいなければ自分もいません。
ですから他人を殺すよりも罪が重いのです。
今の日本では親殺しよりも他人殺しの方が罪は重いのですが、宗教的には逆です。
大恩ある両親を殺すことは即地獄行きです。
それから悟りを開いた人を殺す、仏教教団を仲違いさせたり教団を破壊することが五逆に含まれます。
悟りをひらいた人を「阿羅漢」といいます。
阿羅漢を殺したり、仏教教団を壊すということは正しい教えが広がることを邪魔することになりますから罪が重いのです。
仏教教団が無くなってしまうと、誰も善悪の判断がつかなくなって、悪いことばかりがはびこる世の中になってしまうのです。
そしてもう一つは「仏さまから血を流させる」ことです。
今は無仏の時代と言われています。
お釈迦さまが涅槃に入られてから、五十六億七千万年後に弥勒仏という仏さまがこの世に現れて下さるまでの間、仏はいないのです。
ですから実際直接仏さまに傷を付けて血を流させるようなことはありません。
しかし、仏さまを軽んじたり、仏像を粗末にすることもこれに繋がってきますので、注意しなくてはなりません。
ここには、その五逆罪を犯して、ちょっとの反省もない人は、その罪によって無間地獄におちて、気が遠くなるほどの長い間苦しみ続けなくてはならないと書かれています。
無間地獄というのは、間がないと書くように、間無く苦しみ続けるところです。
地獄の中でも最悪の地獄です。
五逆罪を犯した者は無間地獄に堕ちて苦しみ続けるのです。
ところが、そんな者であっても、臨終の時に仏教のことをよく知る人に出会って念佛を勧められて、称えたならば救われると『観無量寿経』に説かれているのです。
五逆を行うような人は、お念仏と出会う機会がありません。
その中でお念仏と出会って「あなたは散々悪いことをしてきた。五逆の罪を犯してきた。今までそれを反省することもなかった。でもこのまま死んだらあんたは地獄行きである。地獄行き間違いなしだ。でもお念仏を称えるだけで救って下さるのだ。阿弥陀さまにお任せして南無阿弥陀仏と称える者をすべて救うと言って下さっているのだ」ということを聞いて、「ああ、私は散々悪いことをしてきたけれどもどうぞお許し下さい。こんな私をお救い下さい」と阿弥陀さまにおすがりして念仏を称えるならば救われるのです。
阿弥陀さまの本願の力だからこそ救われるのです。
自分の力ならば到底救われようがないけれども、阿弥陀さまの力だから可能なのです。
そのことが一番最後に記されています。
「まことに仏の本願の力ならでは、いかでかさること候べきと覚え候」
自業自得が基本です。
自分の力ならば地獄へ行くしかないはずの者が、阿弥陀さまの力によって初めて救われるのです。
これに関しまして注意すべきことが2点あります。
まず、「親殺しをした者でも救われるんだったらどんな悪事を働いたっていいではないか」ということではありません。
積極的に悪いことをする者はダメです。
「悪いことをしてしまった、でも阿弥陀様お救い下さい。もう二度と致しません」という思いで本気で阿弥陀さまにすがって念仏を称える者は救われるのです。
これは大きな違いです。
もう一つは、このように五逆の話しなどをしますと、最近父親殺しや母親殺しをしたり、子殺し、兄弟殺し、友人殺しなどが後を絶たないものですから、「こういう人が五逆なのだな。こういう人が地獄に行くのだな」と思いがちです。
しかし、先ほども申し上げたように、仏教では自業自得を説きますから、他人のことをとやかく言っても自分には何のプラスにもなりません。
他人のことを「あんな人地獄に堕ちて当然」と思うことは私達にとって決して良い業ではないのです。
それよりも、悪いことをする人を見て、自分はどうかと考える方が大事です。
自業自得の「業」というのは「行い」であると先ほども申しました。
「業」には、「体で行う業」と「言葉で行う業」と、「心で行う業」があります。
「身口意の三業」と申します。
体で、口で、心で一瞬一瞬に様々な業を重ねている私達です。
体では決して人殺しなどはしないけれども、口で心ではどうか。
人の死を願うようなことをしていないか。
「あんな人死んでしまったらいい」と考えることは立派な殺人なのです。
「そんなこと言ったら生きていけない」などと開き直ったところで、業は業ですから結果地獄に墜ちるのです。
このように考えると、「私が五逆だ」と考えるべきです。
この御法語も、他人事として見ていたらなんてことない、「親殺しの人でも念仏で救われる」というだけですが、その五逆は正しく私なのです。
「私のことを説いて下さっている」ととらえて初めてありがたくいただけるのではないでしょうか。
先日この話をある方にしていますと、その方が突然泣き出されました。
六十代の女性です。
その方はつい先日お母さまを亡くされて、そのお葬式から法輪寺とご縁ができ、私がお葬式に伺いました。
お参りの人数は少ないけれども来られた方みんなが大きな声でお念仏をお称え下さり、本当にありがたいお葬式でした。
お葬式が終わって、納棺の際にもお参りの方みんなが涙を流し、一人一人が故人の顔を撫でてお別れを悲しんでおられたのです。
「よっぽど良い人だったのだろう」と思いました。
その方の五七日の時に、仏教のお話をしていると突然泣き出されたのです。
私は驚いて、「どうなさったんですか?」と聞きましたところ、こんな話をして下さいました。
「母はとても良い母でした。優しい母でした。しかし晩年認知症になり、病気にもなって最後は寝たきりでした。私も六十代です。仕事もしていますし、看病するのが本当に辛かったのです。だから看病しながらも心の中では早く逝って欲しいと何度願ったことかわかりません。私が五逆です」と仰いました。
「いやいや、そんなことないですよ」と言うのは簡単ですが、そんなその場だけの慰めを言っても仕方ありません。
私は「仏教の教えに照らし合わせると、五逆に当たることでしょう。私もあなたの立場なら、同じことを考えたと思います。しかし、そんな五逆の私達を救うと仰ったのが阿弥陀さまなのですよ」と申しましたらその女性はとても喜んで下さいました。
私達は自分が五逆とはなかなか思えないけれども、縁があったら簡単に五逆の罪人になるのです。
両親が元気な時には決して「早く死んで欲しい」などとは思いませんが、この方と同じような状況になったら、同じ事を思うかもしれません。
殺人犯をみて、今その行動が理解できなくても、もしその犯人と同じような環境に生まれ育って、同じ目に遭ったならば同じように人殺しをしているかもしれません。
縁が訪れたらどんな悪い行いをするか分からないのが私達です。
この御法語は私達自身のことを説いて下さった御法語です。
そう考えると益々ありがたく受け取ることができるのです。
後篇第二十三章 慈悲加祐
(本文)
まめやかに往生の志ありて、弥陀の本願を疑わずして念仏を申さん人は、臨終の悪きことは大方は候うまじきなり。そのゆえは仏の来迎(らいこう)したもうことは、もとより行者の臨終正念の為にて候うなり。それを心得ぬ人は、皆我が臨終正念にて念仏申したらん時に、仏は迎え給うべきなりとのみ心得て候うは、仏の願をも信ぜず、経の文をも心得ぬ人にて候うなり。そのゆえは称讃(しょうさん)浄土経に曰く、仏慈悲を持て加え助けて心をして乱らしめ給わずと説かれて候らえば、ただの時によくよく申しおきたる念仏によりて臨終に必ず仏は来迎し給うべし。仏の来迎し給うを見奉りて、行者正念に住すと申す義にて候。しかるに先の念仏を空しく思いなして、よしなく臨終正念をのみ祈る人などの候うは、由々しき僻胤(へきいん)に至りたることにて候うなり。されば仏の本願を信ぜん人は、かねて臨終を疑う心あるべからずとこそ、おぼえ候え。ただ当時申さん念仏をば、いよいよ至心に申すべきにて候。
(現代語訳)
真実に往生の志があり、阿弥陀仏の本願を疑うことなく念仏を称える人に、臨終の心が乱れることは、まったくありえないことです。そのわけは、仏が来迎されることは、そもそも念仏者を臨終に正念とさせるためだからです。それを心得ていない人はみな、「自分が臨終に正念であった上で念仏を称える時のみ、仏はお迎えになるはずだ」とばかり考えていますが、これは、仏の本願も信じることなく、経典の文言も理解していない人であります。
そのわけは、『称讃浄土経』に、「阿弥陀仏は慈悲をもって〔臨終の人を〕助けて、その心が乱れないようになさる」と説かれていますので、普段よくよく称えておいた念仏によって、臨終に必ず仏は来迎されるのだからです。仏が来迎なさるのを見て、念仏者が正念に留まるという道理なのです。
ところが常日頃の念仏を無意味だと思いこんで、根拠もなく臨終の正念だけを祈る人などがありますが、これは大変な考え違いに陥っていることになります。ですから、仏の本願を信じる人は、常日頃から臨終〔の正念〕を疑う心があってはならないと思われます。ただ、その時その時に称える念仏を、ますます真心をこめて称えるべきなのです。
(解説)
今回は「来迎」のお話しです。
「来迎」といいますのは、お念仏を称える者は臨終の時に阿弥陀さまがたくさんの菩薩さま方を引き連れて迎えにお越し下さることです。
浄土真宗では「らいごう」と読みますが、浄土宗では濁らずに「らいこう」と読みます。
よくご年配の方が「まだお迎え来ませんわ」とか、「そろそろお迎えが来ますやろ」とおっしゃいます。
これは「お迎え」を「死ぬ」ことと同意に受け取っておられるのでしょう。
別に目くじらを立てる必要はないのですが、「お迎え」はお念仏称える者の元に現れるものです。
お念仏を称えない者には「お迎え」は来ません。
阿弥陀さまが、この世で苦しむ私達をご覧になって、「どうしたら救うことができるだろう」と悩まれた末に、「難しいことをさせてもできる者は少ないであろう。しかし私の名前を称えることならできる。頼む、我が名を呼んでくれ」と願って下さっているのです。「頼む、救ってやるから私の名を呼べよ」と言って下さっているのです。
誰でもできる行を用意して下さっているのに、お念仏も称えずにお迎えだけ求めるのは虫が良すぎる話しです。
「阿弥陀さまがお迎え下さる」などと言いますと、おとぎ話のように思われる方がいらっしゃいますが、そんなものではありません。
うちのお檀家さんの中でも来迎を体験して亡くなった方は何人もおられます。
「うちのおじいさんが死ぬ時、ああ、阿弥陀さん、こっちですこっちです。ああよかった。阿弥陀さん来てくれはった。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。って言って亡くなりましてん」などとおっしゃいます。
死ぬときには意識がない場合が多いので、実際に「阿弥陀さん来てくれはった」とまで言えないことが多いことでしょう。
しかし意識があろうとなかろうとお念仏を称える人のところに阿弥陀さまが直々にお迎え下さることは間違いのないことです。
臨終の時は不安だといいます。
「愛」という言葉は今は殆ど「ラブ」の意味で使われていますが、元々は仏教用語で「執着」の意味です。
臨終の時には三つの愛心、「三愛」という心が起こってくると言われています。
一つ目は「自体愛」といいまして、自分の体を離れたくないという心です。
二つ目は「境界愛」といいます。
自分の家族、自分の家、自分の自分の…という自分の物を失いたくないという心です。
三つ目は「当生愛」といいます。
自分はどこに生まれるのだろうという心、人間世界を離れたくないという心です。
今まで人生において、色々な経験をし、色々な知識を積んできたけれども、死んだ後どこへ行き、どうなるのかは経験ありません。
「自分は一体どうなるんやろう」「また人間に生まれ変わるのか、動物になるのか、地獄に行くのか」「もしかしたら何も無くなってしまうのか」…色々なことが頭を駆けめぐります。
でも分からないので不安になることでしょう。
そんな不安な時に日頃信仰している阿弥陀さまが目の前に現れて下さったら、どれほど心が安らぐことでしょう。
「ああよかった、極楽へ往ける」と心から安心できること間違いなしです。
「ああ、阿弥陀さん、こっちですこっちです。ああよかった。阿弥陀さん来てくれはった。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と言って亡くなったおじいさんの言葉は本当に実感だと思います。
阿弥陀さまが来て下さってこそ心が静かになり落ち着くのです。
心が静かになることを「正念」といいます。
日頃からお念仏を称えている者は臨終の時に阿弥陀さまがお越しになって、そのお姿を見て散り乱れる心が落ち着き「正念」になるのです。
この臨終時の「正念」について、昔から間違った受け取りをする人が多かったようです。
それは、「正念になったら阿弥陀さまが来迎して下さる」という勘違いです。
だから臨終の心散り乱れ、不安で仕方が亡い時に周りで「心を落ち着けなさい!来迎してもらえませんよ!」と騒ぎ立てたのです。
こんなことをいくらしてもダメです。
いくら心を落ち着けろと言われても落ち着くものではありません。
法然上人は「そうじゃないですよ。阿弥陀さまがお越しになるからこそ正念になるのですよ。それには普段からのお念仏が何よりも大切ですよ」とおっしゃるのです。
臨終正念のために阿弥陀さまはわざわざ迎えに来て下さいます。
普段の念仏を疎かにして、臨終正念だけを祈るのはとんでもないことです。
阿弥陀さまがお救い下さることを信じてお念仏称える者には、臨終正念は疑いのないことです。
だから今申す念仏を大事にしなさいと法然上人はお説き下さっているのです。
今日のご法語は割と長いご法語ですが、内容は今申し上げたところです。
臨終の時は非常に大事な時です。
私の先輩から聞いた話です。
先輩が毎月ある一人暮らしのおばあさんのところへお参りに行っていました。
ある日いつものように月参りに行き、インターホンを鳴らすのですが、おばあさんは出てこられない。
何度鳴らしても出て来られないので仕方なく帰ったのです。
翌月行きますとおばあさんはおらました。
「おばあちゃん、先月も来ましたけどお留守でしたね。どこかに行ってたんですか?」と先輩が尋ねますと、「ああ、先月来てくれはったんですか。それはすみませんでした。実は私先月死んでましてな」とおばあさんが言うのです。
「え?死んでた?どういうことですか?」と先輩が聞きますと、おばあさんはこんな話をしてくれたそうです。
おばあさんは病気で入院して病院のベットで寝ていたのです。
そんな時に親戚の人が何人か一緒に見舞いに来てくれました。
先に亡くなったご主人のご兄弟で、普段殆ど付き合いをしていない方々です。
たまに会ってもイヤなことを言われる、仲の悪い人達です。
そんな人達ですが、一人暮らしの自分が入院したと聞いてわざわざ来てくれた、ありがたいなとおばあさん思っていました。
そのままベッドで目を閉じて寝ていると、お医者さんがやって来て、体をあちこち触られて唐突に「ご臨終です」と言われたのです。
おばあさんびっくりして起きようと思っても体が動かないのです。
そんな時に、見舞いに来た親戚の人達は「ご臨終です」とお医者さんが言ったとたん、「しかしこのおばあさんは根性の悪いおばあさんやったなあ」と悪口を言い出したのです。そして遺産相続の話をし出したというのです。
おばあさん「えらいこっちゃ」と思っていると、その親戚の一人が「何かおばあさん動いたような気がするで。もう一回お医者さん呼んでこよう」と言って、お医者さんを呼んできておばあさんは蘇生したというのです。
このおばあさんそれから十年程生きたそうですが、その親戚の人とは一切付き合いを断ったといいます。
そんな時に悪口や遺産相続の話をされたら、もうそこからどれだけ都合の良いことを言われても信用できません。
この話を聞いて、自坊に帰ってから先代に話しますと、「よく似た話がご近所でもあった」と言います。
他にも枕経を終えて帰ってきたら「生き返りましたからもう結構です」と言われたなどということを聞いたことがあります。
死後24時間経たないと火葬できないという法律があるのも、こうやって生き返るケースがあるからなのです。
もちろんこれはしょっちゅうある話ではありません。
一度死んでその間の会話を聞いて、生き返ってきたということは稀でありましょう。
しかし、聞こえていてそのまま死んでいく人は多いと思います。
聴覚は最後まで残るといいます。
お医者さんも聴覚が最後まで残る可能性は十分にあるとおっしゃっています。
お腹の中の胎児は最初に耳が聞こえるようになるそうです。
最初に耳が聞こえるようになって、最後臨終とお医者さんに言われた後も耳が聞こえていると考えます。
だから昔から臨終の枕辺で悪いことを言ってはいけない、と言われるのです。
そこはやっぱりお念仏でお送りするべきでしょう。
これは普段から思っておかないとできません。
人が亡くなったら悲しいですし、どうしてよいか分からずにおろおろしてしまいます。
親戚に電話をし、葬儀屋さんに電話をし、お寺に電話をするなどバタバタします。
そういう段取りをすることももちろん必要ですが、お念仏でお送りするということを普段から心得ておったならば、段取りをする人を誰かに決めて、少なくとも一人が枕辺でお念仏をお称えすることができます。
最後に聞いた言葉が「葬儀屋さんに電話したか!」っていう怒鳴り声やったらイヤでしょう。やはりお念仏で送られたいものです。
それからもう一つ、亡くなる前に臨終行儀というものがあります。
突然死や事故死の場合はできませんが、「今晩がいよいよ山場」という場合ならば、いよいよの時は自分でお念仏を称えることができなくなります。
だから周りの人が手を握って、病院の場合は大きな声を出すと他の人の迷惑になりますので、耳元で小さな声で「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えます。
このときに、患者さんの吐く息に合わすのです。
「南無」「阿弥」「陀仏」と吐く息に合わせてお念仏を称えます。
吐く息に合わせるのは、患者さんの代わりに称えているということです。
これは大変なことです。
「今夜が山場」と言っても、今夜でないかもわかりませんし、時間もわからないわけですから。
交代で行えるならば行っていただきたいと思います。
もちろん普段のお念仏が最も大事で、普段からお念仏を称えていれば、臨終の時、称えることができなくなってもちゃんと阿弥陀さまがお迎え下さるのですが、できる状況ならばこういう臨終行儀もしていただきたいと思います。
亡くなってすぐの念仏も、臨終行儀も送る側の心得です。
普段から意識しておかないと絶対にいざというときにはパニックになります。
また、自分の最後のこともちゃんと元気なうちに家族の人に「こうやって欲しい」と伝えておくべきでしょう。
元気なうちにこういうことを言うと、「はいはい、分かったよ」と軽く流されてしまったり、「そんなこと考えたらあかん。えらい弱気になったなあ」などと息子さんや娘さんに言われてしまいがちです。
しかし根気よく何度も言っていると、「親父、お袋があれだけしつこく言ってたんやから、やってやるか」と思い出してくれるのではないでしょうか?
ウチのお檀家さんで、堺の泉北に住んでおられる方がいます。
80代のご夫婦です。毎年夏の棚行の時しか伺わないお家です。
ある夏もそのお家に伺いました。
いつも棚経の時は、そのご夫婦と嫁いだ娘さんがおられます。
その時のことです。
一年ぶりに伺いますと、奥さんの髪の毛がとても短くなっています。
「どうしはったんですか?」と私が聞きますと、「実は私ガンなんです。そのことでちょっと聞いていただきたいことがあるんですが、お勤めの後お時間いただけますか?」とおっしゃいます。もちろん「わかりました」とお答えし、お勤めの後お話を聞きました。
奥さんは「実は私は末期ガンで、あと数ヶ月の命と言われているんです。それで私自分でお葬式の段取りをしているんです。この辺りでは光明池に泉北メモリアルホールっていうところがあって近所の人は大抵そこでお葬式をしますので、私もそこに問い合わせて色々聞いているんです。こんな遠いところですけどおっさん私のお葬式に来てくれはりますか?」とおっしゃいますので、「もちろんですよ」とお答えしました。
そこからがこの奥さんの偉いところです。「おっさん、私お寺にも遠いからって言ってあんまり寄せてもらったことありませんし、不信心でした。今さら虫のええ話かも知れませんけど、これからの短い人生はどうやって過ごしたらいいんでしょうか?」とおっしゃいました。
私は「お念仏が一番ですよ。お念仏をお称えして最後までお過ごし下さい。ご病気でしんどいでしょうから、無理なく横になったままで称えられたらいいですよ。法然上人もいつでもどこでもどんなときでもとおっしゃっています。座ってても寝転がっていてもいいからとにかく極楽への往生を願ってお念仏をお称えして下さい。大きな声じゃなくてもいいです。小さな声でいいですから称えて過ごして下さい。それから、いよいよの時になったらご本人が称えれなくなりますから、臨終行儀というものをしていただきたいです」と娘さんに先ほど申し上げた臨終行儀のやり方をお伝えしました。
奥さんは「わかりました。これからの短い人生、今までの分を取り返す思いでお念仏をお称えします」とおっしゃり、娘さんも「わかりました」とおっしゃいました。
その2ヶ月後に奥さんは往生されました。やっぱりしっかりと最後までお念仏をお称えして過ごされたそうです。
娘さんもちゃんと臨終行儀をして送られたそうです。
ありがたいことです。
でもこのようなケースは本当に稀なことです。
死ぬ寸前にギリギリセーフでお念仏の教えに出会うなんていうのは滅多にないことです。だから今からお念仏なのです。
今が大事なのです。
今が臨終と心得て絶えずお念仏をお称えすることこそが大切なのです。
最後に私の先輩に教えていただいたことを申し上げます。
先輩が私に「お前、枕経の時どんな話をしてる?」って聞くのです。
私は「遺族の方に枕経の法要の内容を説明して、お念仏をお勧めする話をします」と答えました。
先輩は「お前は遺族の方に話をするんやな。僕は亡くなった人に話をするんや」と言うのです。
先輩は枕経に伺うと、亡き人に向かって「聞こえてますよね。いつも申し上げてきたことですが、いよいよご臨終の時ですからもう一度申し上げますね。阿弥陀さまが念仏を称える者は極楽浄土に迎え取るとお約束下さっています。だからそれを信じてご一緒にお念仏をお称えしましょう。私も称えますし、ご家族の皆さんもご一緒に称えて下さいますから、あなたも声には出せないでしょうがご一緒にお称え下さいね」と言ってお念仏を称えるのだそうです。これは聴覚が最後まで残るということが大前提で行っていることです。
このやり方は素晴らしいと思いまして、これを聞いてから私もこのやり方をするようになりました。
やっぱりお念仏でお送りしたいものです。
後篇第二十二章 退縁悪知識
(本文)
往生せさせおわしますまじきようにのみ、申し聞かせ参らする人々の候うらんこそ、返す返す浅ましく心苦しく候え。いかなる智者、めでたき人々仰せらるるとも、それに尚驚かせおわしまし候うぞ。各各の道にはめでたく尊(たと)き人なりとも、悟(さと)り異(こと)に行(ぎょう)異なる人の申し候うことは、往生浄土の為にはなかなか由々(ゆゆ)しき退縁(たいえん)悪知識(あくちしき)とも申しぬべきことどもにて候。ただ凡夫(ぼんぶ)の計らいをば聞き入れさせおわしまさで、一筋に仏の御誓いを頼み参らせおわしますべく候。
(現代語訳)
「往生などお出来になりません」とばかり、〔あなたに〕申し聞かせる人たちがおられるそうですが、本当に嘆かわしく気がかりなことです。どのような、学識のある人や立派な人々がおっしゃっても、そのことで決して同様なさってはなりません。それぞれの道では立派で尊敬すべき人であっても、解釈が異なり、修行が異なっている人の言われることは、極楽往生のためには、かえって大変な身を滅ぼす縁とも、道を誤らせるものとも申すべきでありましょう。
とにかく凡夫の考えをお聞き入れにならず、一途に仏のお誓いを頼みとなさいませ。
(解説)
法然上人の熱心な信者さんに正如房という方がおられました。
高貴な身分の方で、後白河天皇の娘ともいわれています。
よくお念仏をお称えになる方でした。
その正如房様がご病気になられ、もう先が長くないと自覚された。
それで最後一目法然上人にお会いして、お念仏のみ教えをお聞きしたいと、使いを出されるのです。
お使いが来た時、ちょうど法然上人は「別時」という、お堂に籠もって何日もお念仏を集中的に称える行に入っておられたのです。
普通なら、そんな高貴な身分の人が、しかもいよいよ臨終間際の時に最後一目会いたいとおっしゃったら飛んでいくことでしょう。
ところが法然上人はそうはなさらなかったのです。
代わりに長い長い丁寧な手紙を書かれました。
「あなたのご病気が重いとお聞きして、大変驚いております。そんな状態で私にお念仏のみ教えを聞きたいとおっしゃること、大変尊くありがたいことでございます。今お別時の行を行っておりますが、これを中断してそちらへ伺うべきなのかも知れません。しかし今面会してもかえってこの世に思いを残すだけでしょう」
今すでに正如房様は、先が長くないと覚悟しておられるのに、そこに面会に行きますと、かえって「死にたくない」という思いが強くなって苦しむだけになるでしょう。
だから法然上人は、「今あなたが臨終間際だとおっしゃるけれども、もしかしたら突然私が病気になり、先に死ぬかも知れないのですよ。この世はいつ死ぬかも予測できない無常の世界なのです。しかし前から言っているでしょう。お念仏を称える者は極楽浄土へ往生することができるのですよ。お念仏を称える者同士は必ず極楽浄土で再会することができるのですよ、。極楽で会いましょうよ」と励まされたのです。
正如房様が使いに渡された手紙には疑問が書かれていたようです。
病気になりますと、色んな人が色々教えてくれます。
クロレラがいいとか、アガリスクがいいとか、この病院がいいなどと、色々と教えて下さいます。
どの方も、良かれと思って言って下さるのですが、あまりに色々言われると困ってしまう時があります。
まだ健康法や治療法ならば順番に試すこともできますが、信仰のことになりますと、順番に試すことはできません。
正如房様の元にも病気と聞いて色々な人がお見舞いに来てくれたようです。
その人達が「念仏称えても往生なんてできない」とか「こちらの信仰の方がよい」などとおっしゃって、正如坊様は困ってしまうのです。
今まで繰り返し法然上人のみ教えを聞いて、念仏を称えれば極楽浄土へ往生できると信じて実践してきたが、来る人来る人が色んな信仰を押しつけて来るので、不安になってしまわれたのです。
「もしかしたら今まで信じてきた教えは間違っていたのかしら。聞き違えて私が勘違いしていたのかも知れない」
そう思って法然上人にお手紙を書かれたのです。
法然上人は懇切丁寧に長いご返事を書かれました。
今回の後編第22章はその長い手紙の一部分です。
「あなたがまるで往生できないかのように申し聞かす人々がおられるとのこと、返す返すも嘆かわしく心苦しいことです。どんなに賢い人や立派な人が仰ったことであっても、どうかそれにそのまま驚かされないで下さい。それぞれの道には秀でた尊い人であっても、悟り方向が違ったり、行う行が違う人が仰ることは、極楽浄土への往生のためにはかえってよろしくないことで、往生の道を妨げるものとも申すべきことです。ただ凡夫の計らいを聞き入れるのではなしに、一筋に阿弥陀様の誓いを頼りに極楽へ参らせていただくのですよ」ということであります。
よく病気になったり不幸なことが重なりますと、仏教系新宗教の人が来たり、キリスト教系新宗教の人が来たり、色んな怪しい信仰の人達が来るといいます。
普段ならそんな人が来ても気にせず、断ることができます。
しかし、イヤなことがやたらと重なるときもあるでしょう。
身近な人が次々に亡くなったり、思わぬ病気や事故に遭ったり、一所懸命頑張って働いているのに努力が実らずに他人の借金を背負わされたり、この世は色んなことがあります。
そんなとき、「なぜ私だけこんな目に遭わなくてはいけないの?」と思うかもしれません。
そこに「あなたの家の玄関の位置が悪いのです」とか、「お仏壇の方向が悪い」とか「墓石に傷が入っているのが悪い」とか「お念仏を称えていると地獄に堕ちる。南無妙法蓮華経と称えなさい」などと言われますとグラッとくるかもしれません。
「そうか、イヤなことが次々に起こるのはそのせいだったのか」と思ってしまっても不思議はありません。
自分の努力が報われずに不都合なことが続いて起こると、自分以外の何か他のところに原因があるのではないかと思えてくる。
「そうか、念仏を称えていたのが悪かったのか。お題目を称えなければ!」となってしまうのです。
人間とは本当に弱いものです。
また自分より賢い人、しっかりした人に言われるとつい弱気になってしまうこともあるでしょう。
お医者さん、弁護士さん、政治家等々。
そういう人が「あなた、本気でお念仏なんて信じているの?極楽なんてあるわけないだろう」と言われると、「アレ?今まで信じてきた信仰は間違っていたのかしら。こんな賢い人が言うのだから。私が信じていたものは幼稚なものかも知れない」と、グラつくのです。
正如房様もお念仏信仰で間違いないと思っていたのに、いよいよ死が近いという時になって、「念仏で往生なんてできないよ」と色々な人に言われて心が揺らいできたのです。
そこで法然上人に「今まで聞いてきた教えで間違いないですか?」と確認されたのです。
お念仏の教えはちゃんとお経に説かれている仏様の教えです。
賢いとか、偉いと言っても所詮凡夫。
凡夫の中で、凡夫の価値観で上下をつけているだけのこと。
仏さまでもない凡夫の言うこと聞く必要はありません。
極楽浄土は阿弥陀さまの国です。
極楽浄土へ行くには極楽の主の言う通りにしなくてはなりません。
阿弥陀さまは何とおっしゃっているか。
「我が名を呼べ。南無阿弥陀佛と称えよ。私が必ず極楽へ迎え取ってやるから」とおっしゃっているのです。
仏でも何でもない凡夫の言うことを聞くのではなく、仏様の言うとおりにするのです。
当たり前のことでありながら、フラフラとグラつく私達です。
注意しないといけませんね。