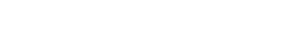後篇第二十一章 随順仏教
(本文)
念仏して往生するに不足なしと言いて、悪業をも憚(はばか)らず行(ぎょう)ずべき慈悲をも行ぜず、念仏をも励まさざらんことは仏教の掟(おきて)に相違する也。例えば父母の慈悲は良き子をも悪しき子をも育(はぐく)めども、良き子をば喜び、悪しき子をば嘆くがごとし。仏は一切衆生を哀れみて、良きをも悪しきをも渡し給えども、善人を見ては喜び悪人を見ては悲しみ給える也。良き地(ぢ)に良き種を蒔(ま)かんがごとし。構えて善人にして、しかも念仏を修すべし。是を真実に仏教に順(したご)うものという也。
(現代語訳)
「念仏して往生できるのだからそれで充分だ」などと言って、悪業をもはばかることなく、もつべき慈悲の心をももたず、念仏にも励まないとすれば、仏教の掟に反しています。
たとえば父母の慈愛は、良い子も悪い子もいつくしみますが、良い子については喜び、悪い子については嘆くようなものです。仏はあらゆる衆生を哀れんで善人も悪人もお救いになりますが、善人を見ては喜び、悪人を見ては悲しまれるのです。
良い畑に良い種を蒔くようなものです。是非とも善人となり、その上で念仏を修めなさい。これを、真実に仏の教えに従う者というのであります。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
法然上人の数多いお弟子の一人に、浄土真宗を開かれた親鸞聖人がおられます。
その親鸞聖人に有名な言葉があります。
「善人なおもて往生すべし。いわんや悪人をや」という言葉です。
日本史の教科書にも出てくる「悪人正機(あくにんしょうき)」と呼ばれる言葉です。
「善人でも往生するのだから、悪人が往生するのは当然だ」という意味です。
常識とは反対です。
実はこれと全く同じ言葉が、親鸞聖人のお師匠さまである、法然上人のお言葉として残っています。
ただ法然上人の場合は「罪人なおもて往生すべし、いわんや善人をや」という言葉、
「罪人でも往生するのだから当然善人も往生しますよ」という言葉も残されています。
こういう全く逆にとれる言葉を両方残されたことには理由があります。
法然上人は「対機説法」という、「相手に応じてその人に合うように法を説かれている」からなのです。
恐らく「親鸞聖人は自分は悪人である」という自覚を強く持っておられたので、
「悪人であるあなたこそが救われるんですよ」と法然上人は説かれたのでしょう。
それを聞いて親鸞聖人はきっと喜ばれたでしょう。
ですから親鸞聖人は、ことさらその「悪人正機」を強調されたのではないでしょうか。
「悪人正機」を強調することが良いのかどうなのかは、議論の分かれるところです。
少し間違えると、危険な方向にいく可能性があるからです。
法然上人のお弟子の中には「一念義」という、
「一遍のお念仏だけで往生できる」という考え方の人がいました。
「たった一遍の念仏でも阿弥陀さまはお救い下さる。
だから、たくさん称えるのは、阿弥陀さまを信じていない証拠だ」というのです。
また、「本願誇り」といいまして、「阿弥陀さまは、お念仏を称えるだけで救って下さるのだから、
いくら悪いことをしてもいいのだ、積極的に悪いことをする方が阿弥陀さまを信じていることになるのだ」
という考え方も出て参りました。
法然上人はこの「一念義」と「本願誇り」を強く戒めておられます。
「これは仏教じゃない」とまで言われました。
結局法然上人は晩年この「一念義」と「本願誇り」の弟子達が
勝手な解釈の教えを広めた責任をとられて流罪に遭われています。
この一念義や本願誇りを戒めたお言葉をいくつも残されておりますが、
今日のご法語もその一つです。
「念仏して往生するに不足なしと言いて、
悪業をも憚らず行ずべき慈悲をも行ぜず、念仏をも励まさざらんことは仏教の掟に相違するなり」
「お念仏を称えて往生することには、念仏以外に必要なことがない」
と言って…それは確かにそうなのです。
お念仏を称えて往生することに、他に何も加える必要はありません。
しかし、だからと言って「悪い行いも憚らないで、
やらなくてはならない慈悲を掛ける行いもせずに、またお念仏も励まない」
これはもう仏教じゃないのですよ、ということです。
「たとえば、両親の慈悲は良い子にも悪い子にも注がれるけれども、
良い子が育てば喜び、悪い子が育てば嘆くようなものですよ。
阿弥陀様はすべての人々を哀れんで、善い人も悪い人も往生させて下さるけれども、
善人を見ては喜び、悪人を見ては悲しみなさるでしょう。
それはまるで、良い土地に良い種を蒔けば良いように、
善人であって念仏を称える方が良いのですよ。
これが本当の仏教なのですよ」ということです。
「念仏を称えてるからいくら悪いことをしてもいいのだ」と言われると、
「それはいけない」と私たちは思いますね。
でも「浄土宗は念仏称えたら救われる教えだから、
何をしてもいい。だから楽でいいね」と聞くことがあります。
これは本願誇りと何ら変わりがありません。
私たち自身が本願誇りにならないように、
よくよく注意しなくてはなりません。
後篇第二十章 行者存念
(本文)
ある時には世間の無常なることを思いてこの世のいくほどなきことを知れ。ある時には仏の本願を思いて必ず迎え給(たま)えと申せ。ある時には人身(にんじん)の受け難き理(ことわり)を思いてこの度空しく止(や)まんことを悲しめ。六道(ろくどう)を巡るに人身(にんじん)を得(う)ることは梵天(ぼんてん)より糸を下(くだ)して大海の底なる針の穴を通さんが如しといえり。ある時は遇い難き仏法に遇えり。この度出離(しゅっり)の業(ごう)を植えずば何時(いつ)をか期(ご)すべきと思うべきなり。一度悪道に堕(だ)しぬれば阿僧祇劫(あそうぎこう)をふれども三宝(さんぼう)の御名(みな)を聞かず。いかにいわんや深く信ずることを得んや。ある時には我が身の宿善を悦ぶべし。かしこきも卑しきも人多しと雖(いえど)も仏法を信じ浄土を願う者は稀(まれ)なり。信ずるまでこそ難からめ、謗(そし)り憎みて悪道の因をのみ造る、然(しか)るにこれを信じこれを貴(たと)びて仏を頼み往生を志すこれ偏(ひとえ)に宿善のしからしむるなり。ただ今生(こんじょう)の励みにあらず、往生すべき期(とき)のいたれるなりと頼もしく悦ぶべし。かようのことを折(おり)に順(したが)いことによりて思うべきなり。
(現代語訳)
ある時には、世間が無常であることを思って、この人生がさほど長くないことをわきまえなさい。
またある時には、阿弥陀仏の本願を思って、「必ず極楽へお迎えください」と口に出しなさい。
ある時には、人間としては生まれ難いという道理を思い、この人生がその甲斐もなく終わるかもしれないことを悲しみなさい。「六道を輪廻する中で、人の身を得ることは、梵天から糸を垂らして、大海の底に沈む針の穴を通すようなものだ」と言われています。
またある時には、「遇い難い仏教に遇うことができた。この生涯で輪廻を逃れるための修行を積まなければ、いつの日に期待できようか」と思うべきです。ひとたび悪道に墜ちてしまえば、阿僧祇劫という長い年月を経ても、仏・法・僧という三宝の名さえ聞くこともありません。ましてそれを深く信じることなどできましょうか。
ある時には、自分が前世で積んだ善業を喜びなさい。身分の高い人もそうでない人も多くいますが、仏の教えを信じて浄土を願う者はまれであります。信じることまでは難しいにしても、〔多くの人々は〕謗り憎んで悪道に墜ちる原因ばかり造っています。ところが〔あなたは〕、この教えを信じ、これを貴んで、阿弥陀仏を頼みとし、往生を志しておられます。これはひとえに、前世で積んだ善業のおかげであります。ただ今生での努力だけではありません。「往生する機会が巡って来たのだ」と頼もしく思ってお喜びください。このようなことを、折りにふれ、事に応じて思うべきです。(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
仏教の基本に「輪廻」という思想があります。
まずはこの「輪廻」についてお話ししておきたいと思います。
我々は、数十年の一生を過ごすだけではなく、生まれ変わり死に変わりをくり返しているといいます。
しかも人間が人間に生まれ変わるとは限りません。
それどころか、人間に生まれること自体が相当に難しいことです。
我々は六つの世界を生まれ変わり死に変わりしているといいます。
六道といいます。
まず地獄です。
地獄は苦しみばかりの世界です。
苦しみしかない、つらいつらい世界です。
その上に餓鬼道があります。
餓鬼道にいる餓鬼は、いつも飢えに苦しんでいます。
いつもいつもお腹がぺこぺこに空いているといいます。
食べものを食べようとしますと、
その食べものがボッと火に変わってしまって食べられない。
いつも喉がカラカラに乾いているのに飲み物を飲むと
それが熱湯に変わって喉が焼けただれてしまいます。
いつも飢えているのに食べることも飲むこともできない世界です。
法輪寺では毎年8月19日に施餓鬼という法要をします。
あの法要は、その名の通り「餓鬼を施す」法要なのです。
先ほども申したように、餓鬼は自分の力で食べたり飲んだりすることができません。
だからみんなで法要をして、食べものを餓鬼が食べることができるようにして施すのです。
そして私達、皆様方が餓鬼に施した、その功徳を亡きご先祖に振り向けるのが施餓鬼法要です。
決してご先祖が餓鬼道で苦しんでいるということではなく、施餓鬼をして、
私達がいただいた功徳を亡き人に差し上げるのが施餓鬼法要の重要な意義です。
次に畜生です。
これは動物の世界です。
自分の身を守るためだけに明け暮れる世界です。
いつ他の動物に襲われるか分からない不安に毎日さらされている世界です。
その上が修羅です。
戦いに明け暮れる世界、殺し合いを続ける世界です。
この世界も相当に辛い世界です。
その上が人、人間の世界です。
その上に天という世界があります。
天と極楽は異なります。
天は幸せの多い世界ですが、必ず寿命があります。
生きている間幸せな分、死ぬときは辛いといいます。
人間でもいざ死が近づいて来ると、「死にたくない」という思いが強くなってくることでしょう。
天は人間と比べものにならない程幸せで、しかも寿命も長いので、
死ぬ時は「ここから離れたくない!」という強い執着が沸き、
人間と比べものにならない程辛い思いをするといいます。
そして、自分が死ぬということは誰もが死ぬということです。
天であっても愛する人と死に別れなくてはならないのです。
天の世界は生きている間、楽しいことばかりですから、
自分も死に、愛する人とも死に別れる時は余計に辛い思いが強くなるのです。
この六道、どの世界をとっても苦しみの世界です。
絶対の幸せの世界はありません。
この六つの世界を生まれ変わり死に変わりしているのが私達です。
これが六道輪廻です。
この六道輪廻の世界を「娑婆」とか、「忍土」といいます。
この娑婆から逃れ出るのが仏教の目的です。
「解脱」あるいは「出離」ともいいます。
苦しみの世界、娑婆世界から脱出するのです。
その方法に浄土宗からみて二種類あるといいます。
一つは自分で修行して、煩悩を無くして悟りを開き、自分の力で脱出する方法です。
もう一つは自分の力ではとても脱出することはできないが、
南無阿弥陀仏と称えて阿弥陀さまにお任せして、
阿弥陀さまに救い出してもらうという方法です。
阿弥陀さまの力で、脱出させてもらうのです。
もちろん浄土宗の教えは後者です。
「南無阿弥陀仏」と称えて、阿弥陀さまに救っていただく教えです。
前置きが長くなりましたが、これをふまえていただきまして本文に入って参ります。
まず、「ある時にはこの世が無常であると思い定めなさい」ということです。
「無常」といいますのは、「すべては変化する」ということです。
すべては変化し続け、形ある物は必ず壊れます。
生まれてきた者は一瞬一瞬に老いてゆき、必ず病になり、必ず死にます。
しかもいつ死ぬか分からないのです。
ですから「ある時には仏の本願を思いて必ず迎え給えと申せ」とありますように、
「いつ死ぬか分からないのだから、常にお念仏を称えなさいよ」と説かれます。
いつ死ぬかわからないのですから「年取ったら念仏称えよ」とか、
「死ぬ前になったら称えよ」というのは通用しません。
かと言って、いつも「明日死ぬかわからん、今日死ぬかわからん」などと思って生きていたら大変です。
ですからいつ死んでも極楽浄土へ往けるように、
いつもお念仏を称えることを勧めるのです。
極楽への往生が決まっていれば、いつ死を迎えても大丈夫です。
往生を確信して、力強く生きていくのです。
次には「人間として生まれることは難しい」と書かれています。
私達は人間に生まれることを当たり前のように思って生きていまが、とんでもないことです。
先ほど六道輪廻の話をしましたが、六道を均等に生まれ変わるわけではありません。
地獄の次は餓鬼道、そして畜生道と順番に上がっていくのではありません。
私達自身の行いによって、その行き先が決まるのです。
私達は自分の煩悩だらけの行いを見つめると、決して良い世界にはいけそうもありません。
地獄か、餓鬼道か、畜生か。
圧倒的に地獄や餓鬼道、畜生道へ行く可能性が高いと言えます。
人間や天に生まれることは、相当に難しいのです。
ここでは人間に生まれることがどれだけ難しいかを喩えを使って説いてくださっています。
天から糸を垂らして、海の底に沈んでいる針の穴にその糸が通るぐらい、
人間として生まれることは難しいというのです。
天まで行かなくても、上空200メートルのところから糸を垂らして、風に吹かれ、
ようやく海面についたらそこには波があり、
海流がある中を海の底まで沈んでいって、
たまたまそこにある針の穴に糸が通る、そんな確率です。
目の前の針の穴に糸を通すだけでも大変です。
30センチ上から糸を垂らして針の穴に糸を通そうとしても恐らく何時間かかってもできないでしょう。
それが天から糸を垂らして海底の針の穴に糸を通すのですから、ほぼ不可能だと言えます。
でも可能性0ではありません。
人間として生まれるのは、それほどに難しいという喩えです。
そして人間として生まれて更に仏教のみ教えと出会うことは本当に難しいといいます。
考えてみますと、隣近所を見回して、「仏教」という言葉を知っている人は大勢います。
「阿弥陀さま」、「念仏」、「極楽浄土」という言葉は殆どの人が知識として知っています。
でもその教えを信じている人がどれだけいるかとなりますと、殆どいなくなるのではないでしょうか。
せっかく人間として生まれてきているのに、そして今ようやく解脱するチャンスを得たのに、
今の機会を逃せば次にいつ解脱できるかわからないのに。
それに一度地獄や餓鬼道に落ちたら抜け出すのが大変です。
地獄は苦しみばかりの世界ですから、
苦しみ続ける中で善い行いはできません。
自分が苦しくてたまらない時に、人に施したりする余裕はないはずです。
人間でも、自分が苦しい時には他人のことを構っていられないことでしょう。
餓鬼道もお腹が減ってたまらんときに善い行いなんてできません。
動物もそうでしょう。
動物は自分の欲望を満たすことだけで精一杯です。
自ら善い行いはできません。
修羅も戦いに明け暮れている訳ですから、それどころではありません。
だから一度そういう世界に行きましたら、はい上がってくるのが大変です。
ここでは、永遠ではないけれども、永遠に近いほどの時間がかかると書かれています。
仏教の教えを学んでいても、ある程度修行が進んでいても、
解脱できずに次に何かに生まれ変わったら、前世の記憶が失われます。
「ここまでできたから、その続きを…」というわけにはいきません。
今こうして人間として生まれてきて、仏教のみ教えと出会い、
そのみ教えを信じることができるのは、
決してこのたび生まれてきた数十年の間に善い行いをし、
善いご縁に恵まれただけではないのです。
前世、前前世、ずっと昔から余程に善い行いをし、ようやく人間に生まれて、
ようやく仏教のみ教えに出会い、ようやくそのみ教えを信じることができたのです。
決して当たり前のことではありません。
ようやく極楽へ往生することができる舞台まで登って来たのです。
機は熟しました。
このチャンスを逃せば次にいつ解脱できるかわかりません。
だから最後の文章「かようのことを折りに順いことによりて思うべきなり」と説かれるのです。
いつ死ぬか分からない人生です。
人間として生まれてくることは本当に大変なこと、仏教と出会い、念仏と出会うことは大変なことなのだ。
それが今ようやく往生するチャンスが訪れてきたのだ。
今念仏せねば!ということを、折りにふれて思い出しなさいよ、と説かれるのです。
「凡夫」と言う言葉があります。
これは単に「平凡」という意味ではありません。
「輪廻する者」という意味です。
ですから、大学の先生も偉いお坊さんもみんな凡夫です。
その凡夫の特徴は、「忘れる」ということです。
凡夫は輪廻していますが、前世の記憶はすべて失われます。
だから同じ過ちを繰り返し、何度も何度も輪廻を繰り返すのです。
今の一生の間でも大切なことをたくさん忘れます。
どんなに恩のある人に「このご恩は一生忘れません!」と思っていても、
年月が経つと恩があることぐらいは覚えているけれども同じ思いは持続できません。
段々薄れていきます。
戦争の怖さを強く味わって、「戦争なんて嫌だ!」と誰もが思うのに、戦争は無くなりません。
それと同じように「お念仏の教えは有り難い!」とどんなに感動しても
日常生活を繰り返すうちにお念仏のことを忘れてしまうのです。
だから、折々に「これがラストチャンスなんだ!このチャンスを逃せば二度と往生するチャンスは巡ってこないかも知れない!」と
自分に言い聞かせてお念仏をお称えなさい
と法然上人はおっしゃるのです。
宝くじで一千万円当たって銀行にそれを取りに行くのを忘れる人は誰もいません。
でも輪廻の呪縛からようやく逃れて往生できるというのに、
お念仏を忘れる人は大勢います。
よくよく注意しなくてはならない、
とお互い肝に銘じましょう。
後篇第十九章 孝養父母
(本文)
孝養(きょうよう)の心を持て、父母(ちちはは)を重くし思わん人は、まず阿弥陀仏(あみだほとけ)に預け参らすべし。我が身の人となりて、往生を願い念仏することは、一重(ひとえ)に我が父母(ちちはは)の養いたてたればこそあれ。我が念仏し候う功徳(くどく)を哀れみて、我が父母を極楽へ迎えさせおわしまして、罪をも滅しましませと思わば、必ず必ず迎え取らせおわしまさんずるなり。
(現代語訳)
孝行の心をもって、父母を大切に思う人は、まず阿弥陀仏にお任せするのがよいでしょう。「自分が一人前になって、往生を願い、念仏することは、、ひとえに父母が私を養育してくれたからこそなのです。私が念仏する功徳を心からお喜びになって、父母を極楽へとお迎え下さり、その罪を滅して下さい」と願うならば、必ず必ずご両親を迎え取って下さるでしょう。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布師会刊)
(解説)
今回の御法語は非常に短く、平易なわかりやすい文章です。
この御法語は、法然上人には珍しく、「孝養(きょうよう)」がテーマです。
孝養の下に父母と書いて、「きょうようぶも」と読みます。
普通の読み方ではこうようふぼですが、仏教の読み方ではきょうようぶもです。
いずれにしましても、意味はいわゆる親孝行のことです。
法然上人は阿弥陀さまのご恩については多く語られますが、親の恩について語られることはそう多くはありません。
我々のような者であっても南無阿弥陀仏と称えて阿弥陀さまにお任せしておれば、この苦しみ迷いの娑婆世界から絶対の幸せの世界である極楽浄土へと救い取って下さるご恩に酬いなくてはならない、ということです。
それとは異なり、今回は親の恩についてです。
読んで参ります。
「親孝行の心をもって、両親を大事に思う人は、まず両親を阿弥陀様にお預けする、阿弥陀さまにお任せするしてこのように考えてみるのです。私がこうやって人間として生まれ、往生を願ってお念仏を称えることができるのは、ひとえに両親が育ててくれたからこそのことなのだ。だから阿弥陀さま、どうぞ私がお念仏を称えた功徳にお慈悲を垂れ給い、両親を極楽へお迎えいただき両親が今まで重ねてきた罪も滅して下さいと願うのです。そうすれば阿弥陀さまは必ず両親を極楽へ迎え取って下さるでしょう」ということです。
大乗仏教には「回向(えこう)」という教えがあります。
回し向けると書いてえこうと読みますが、何を回し向けるのかというと、功徳を回し向けるのです。
ですからまず自分がお念仏をお称えして、阿弥陀さまから功徳をいただくことが大切です。何もしないで人任せにしているのを回向とは言いません。
ここでは、「自分はお念仏の教えと出会って、お念仏を称えるご縁に恵まれたから間違いなく往生させてもらえるだろう。でも両親はお念仏の教えも知らず、仏教の教えに出会うこともなく亡くなっていった。自分にとっては良い両親であったけれども、もしかしたら地獄や餓鬼道に墜ちているかもわからない。阿弥陀さま、どうか私同様両親も極楽へ往生させて下さい。阿弥陀さまに両親をお任せします」と心を運んでお念仏を称えるのです。
私はよくお通夜の時に「みなさん、亡き方を阿弥陀さまにお任せしてご一緒にお念仏を称えましょう。阿弥陀さま、○○さんをよろしくお願いしますという思いでお念仏をお称えして極楽へお送りいたしましょう」と申し上げます。
両親とは限りませんが、念仏信者はどなたをお送りする時も、このように回向します。
ここでは極楽へ往生していない人を「極楽へ往生させて下さい」と回向しますが、我々のご先祖はお念仏を称えてこられましたから、すでに極楽におられます。
ですから、極楽におられるのに「極楽へ往生させて下さい」と廻向する必要はありません。
我々が行っている法事や月参りは何のためにやっているのでしょうか。
極楽へ往生した人は、そこで修行なさいます。
阿弥陀さまの元で修行し、悟り開いて仏になるまで、阿弥陀さまにお育ていただくのです。このように仏になることを「成仏」と申します。
「往生」は極楽に生まれることです。
「往生」と「成仏」は混同して使われることがありますが、意味は異なります。
極楽浄土へ「往生」して、そこで修行して「成仏」するのです。
その極楽で修行なさっている方に、「私が積んだ僅かな功徳ですが、修行が一歩でも進むようにお使いください」と回向するのです。
私が積んだ功徳は少なくても、阿弥陀さまが介在してくださいますから、大きな功徳となります。
これを「追善回向(ついぜんえこう)」といいます。
往生を願う回向も往生した方の修行を応援する回向もどちらも大切です。
生きている間に親孝行することはもちろん大切ですが、生きている間にできることには限界があります。
所詮欲望を満たして差し上げることぐらいしかできません。
よく親を介護される方がおっしゃいます。
「尽くしてやりたいけど自分もしんどいからついつい腹を立ててしまうんです」
なかなか本当に良いことはできない私たちです。
亡くなってから「苦しいところにいるなら極楽へ往生してよ。極楽にいるなら早く仏になってね」と回向することは、この世で孝行するのに比較にならないほど大切な孝行です。
「孝行したい時に親はなし」といいますが、決してそんなことはありません。
亡くなってからも、いくらでも孝行することができるのです。
後篇第十八章 深信因果
(本文)
十重(じゅうじゅう)を持(たも)ちて十念を称えよ。四十八軽(きょう)を守りて四十八願を頼むは心に深く冀(こいねご)う所なり。おおよそいずれの行(ぎょう)を専(もは)らにすとも、心に戒行(かいぎょう)を持(たも)ちて浮嚢(ふのう)を守るが如くにし、身(み)の威儀に油鉢(ゆはつ)を傾(かたぶ)けずば行(ぎょう)として成就せずということなし。願として円満せずということなし。しかるを我ら或いは四重を犯し、或いは十悪を行ず。彼も犯しこれも行ず。一人(いちにん)として真(まこと)の戒行を具(ぐ)したる者はなし。諸悪莫作(しょあくまくさ)、諸善奉行(しょぜんぶぎょう)は三世(さんぜ)の諸仏の通戒なり。善を修(しゅ)する者は善趣(ぜんしゅ)の報を得(え)、悪を行(ぎょう)ずる者は悪道の果を感ずという、この因果(いんが)の道理を聞けども聞かざるがごとし。初めていうに能(あた)わず。然(しか)れども分(ぶん)に順(したが)いて悪業(あくごう)を留(とど)めよ。縁に触れて念仏を行じ往生を期(ご)すべし。
(現代語訳)
十重禁戒を保って十念を称えなさい。四十八軽戒を守って、四十八願を頼みとすることは、心に深く願うところです。
およそどのような修行に専心するにしても、心に戒の行を保つには、〔水の中で〕浮き袋を手放さないかのようにし、身の振る舞い〔を正す〕には、油で満ちた鉢を傾けないほどの注意を払うようにします。
そうすれば、いかなる行も成就しないことはなく、いかなる願も叶わないことはありません。
けれども我々は、あるときには四重罪を犯し、またあるときには十悪を行います。あれも犯し、これも行います。誰一人、真に戒の行を保つ者はありません。
「諸の悪を作すこと莫れ、諸の善を奉行せよ」とは、過去・現在・未来の三世のすべての仏が共通してお教えになる戒であります。「善を修める者は善趣の報いを得、悪を犯す者は悪道の果を受ける」という、この因果の道理を聞いても、まるで聞いていないかのようであります。それは改めて言うまでもないことです。
けれども、出来る範囲で悪業をとどめなさい。折りにふれて、念仏を修め、往生を願いなさい。
(解説)
仏教には「戒」というものがあります。
「仏教徒としての習慣」という意味です。
その戒をお授けした方につくお名前が戒名です。
法輪寺では20年に一回「授戒会」という、戒をお授けする作法を行っています。
そのように、本来生きている間に授戒会を受けて、戒名をいただいておくべきです。
キリスト教では洗礼を受けると、クリスチャンネームというものがつきます。
それと同じように、仏教徒としてのお名前を「戒名」と呼ぶのです。
しかし、生前に授戒会を受けることができない人がほとんどでしょう。
ですから枕経の時に、授戒をごく簡略にした作法を行って、お戒名をお授けしているのが現状です。
戒の基本的なものはお釈迦さまが定めてくださいました。
お釈迦さまはお坊さん用の戒と、一般の方用の戒に分けられました。
お坊さん用の戒はたくさんあるのですが、一般の方用の戒は5つだけ定められました。
五戒といいいます。
一つ目は、自分が生きるため以外の殺生を避け、むしろあらゆる生き物を慈しみ大切にしなさい、といいます。
二つ目、人の物を盗まず、むしろあらゆる物を自分の物と同様に大切にしましょう。
三つ目、嘘をつくことをやめ、むしろ誠実に生きていきましょう。
四つ目、夫婦間以外の淫らな行為、不倫などはやめ、むしろ男女互いに敬い大事にしましょう。
そして五つ目、自分を見失うほどにお酒を飲んではいけませんよ。という5つです。
戒というものには色々あり、宗派によって異なります。
浄土宗では法然上人が天台宗、比叡山で授戒を受けておられますので、戒に関しては天台宗と全く同じ戒を受け継いでいます。
そして、一般の方にもお坊さんと同じ戒をお授けしています。
浄土宗の戒は十重四十八軽戒といいます。
一行目の頭に「十重」とあります。
そして一行目の真ん中に「四十八軽」とあります。
「十重四十八軽戒」です。
つまり、十の重い戒と、四十八の軽い戒があるわけです。
浄土宗の教えは「極楽浄土への往生を願って南無阿弥陀仏と称える者は阿弥陀さまのお導きによって極楽浄土へ迎え取っていただける」という教えです。
ですから極悪人でも往生することができる、と説かれます。
ただ、誰でも彼でも往生できるわけではもちろんありません。
「私は今まで繰り返し悪いことをしてきた。本当ならば地獄に行っても仕方ない。でも阿弥陀さまはこんな私でもお救い下さるという。阿弥陀さま、どうかお助け下さい」と心からお念仏をお称えする人は往生できると説きます。
それを自分の都合のよいように、誤解をする人がでてきました。
「いくら悪いことをしてもいいんだ。最後に南無阿弥陀仏って称えればいいんだから」という人が出てきました。
更には「戒を守って念仏を称えるのは阿弥陀さまの力を信じていない証拠だ。阿弥陀さまはどんな者でもお救い下さるのだから、積極的に悪いことをしたったらいいのだ。それが阿弥陀さまを信じているということだ」という人まででてきました。
そうすると当然他の宗派の人たちから非難を受けることになります。そしてその矛先は法然上人に向いていきます。
そこで法然上人は「浄土宗の教えはそういうものではありませんよ。これが正しい浄土宗の教えなんですよ」と比叡山にお手紙を出されます。
それを「登山状」といいまして、その一部が今回ご紹介する、御法語後編第十八章なのです。
一つ一つの語句が難しいので、内容をかいつまんで申し上げることに致します。
「まず仏教には戒というものがあり、浄土宗も決して例外ではないのだ。できるならば、戒を守り通してお念仏を称えるにこしたことはない。戒をしっかり守って正しく修行すれば、どんな行でもどんな願でも成就するのだ。しかし私達は戒をしっかりと守りきれない存在ではありませんか」というのです。
仏教では「体の行い」「口の行い」「心の行い」の三つを同じようにみます。
つまり、ナイフを持って人を殺すことと、「お前なんか死んでしまえ」と口で言うこと、それから心の中で「あんな人死んでしまえばいい」と思うことは同じ「殺生」という行為なのです。
私達は「心で思うだけなら罪がない」と思いますがそうではありません。
そういう厳密な意味で戒を守ることは非常に難しいんです。
法然上人も一生涯戒を守り、周りの人たちからは「法然上人はきっちり戒を守る方だ」と尊敬されていました。
しかしご本人はご自分の心の中をジッとご覧になって、「とても戒を守りきれない」と自覚なさってたのです。
「お釈迦さまの時代にはすぐれた指導者がおられたから、しっかり戒を守る人も多くいた。しかし、今の時代(つまり鎌倉時代)に本当の意味で戒を守れる人なんているのか、誰もいないじゃないか。しかし仏教ではそもそも、悪い行いをやめましょう、善い行いをしましょう。それが仏教なんだ、と昔から言われている。それがすべての仏さまに共通する教えである。善い行いをする人は善いところに生まれ、悪い行いをする人は命が尽きたら悪いところに生まれる。こういう因果の道理は誰もが知っているが、実際にできなければ意味がないではないか。善い行いをしようにもできない、悪い行いしかできなければどうしようもないではないか。しかし自分の分相応に悪い行いをやめていきましょう。そして縁に触れてお念仏を称えていきましょうよ。」とおっしゃるのです。
つまり、「どうせ戒なんて守れない。善い行いなんてできないのだから、戒なんて無視すればいい」というのではないのです。
「私は戒なんて守れない」、でも自分の分相応に守ろうとするのです。
守ろうとしても実際には守りきれないかもしれません。
そこで「普通なら戒の一つも守れない、救われようのない私を阿弥陀さまはお救い下さる。どうぞお救い下さい、南無阿弥陀仏」と阿弥陀仏にすがればよいのです。
「いくら悪いことをしてもいい」というのと、「したくはないけれども悪いことをしてしまう」というのでは大きく違うのです。
ただ、「いくら悪いことしてもいい」というのは行き過ぎです。
私たちはそういう人がいたら、「それは救われないよ」と思ってしまいます。
しかしよく考えてみると、これは現在の我々がやっていることではないでしょうか。
「ウチの宗派は念仏を称えておけばいいらしい。だから楽なんですよ。何してもいいんです。念仏を称えるだけだから」などと言っているのはこれと同じです。
戒なんて無視してしまっています。
私なども妻帯していますし、肉も魚も食べます。お酒も多少飲みます。それでも念仏で救われることが当たり前だと思っていたならば、この人たちと同じです。
本当は守らなければならない戒であるが、世間や周りのこと、そして誘惑に勝てずに悪い行いをしてしまう。
でも阿弥陀さまがお救い下さるのだ」とその有り難さを再確認すべきです。
この御法語を改めてじっくり読んでゾッとしました。
「これは私に説かれた教えだ」と。
後篇第十七章 百万遍
(本文)
百萬遍のこと。仏の願(がん)にては候わねども、小阿弥陀経にもしは一日もしは二日乃至七日念仏申す人、極楽に生(しょう)ずると説かれて候えば、七日念仏申すべきにて候。その七日のほどの数は百萬遍に当たり候うよし、人師(にんじ)釈(しゃく)して候えば百萬遍は七日申すべきにて候えども、耐(た)え候わざらん人は、八日九日などにも申され候えかし。さればとて百萬遍申さざらん人の生まるまじきにては候わず。一念十念にても生まれ候うなり。一念十念にても生まれ候うほどの念仏と思い候う嬉しさに、百萬遍の功徳を重ぬるにて候うなり。
(現代語訳)
百万遍について。
阿弥陀仏の本願にはありませんが、『阿弥陀経』に、「もしくは一日、もしくは二日、あるいは七日まで、念仏を称える人は極楽に生まれる」と説かれていますので、七日間念仏を称えるべきです。
その七日ほども〔念仏の〕数が百万遍に相当すると、ある高僧は解釈しておられます。ですから、百万遍は七日で称えるべきですが、それが出来ない人は、八日や九日などでもお称えになって下さい。
だからといって、百万遍の念仏を称えない人は往生できない、というわけではありません。一念や十念でも生まれるのです。一念や十念でも生まれるほどの念仏だと思ううれしさに、〔おのずと〕百万遍念仏の功徳を重ねることになるのです。
(解説)
「百万遍念仏」という信仰があります。
中国でできた、お念仏の数量信仰です。
つまりたくさんお念仏を称えればそれだけ功徳が増す、というもので、「百万遍もの数の念仏を称えれば間違いないだろう」というわけです。
それが日本にも入ってきて広まりました。
法然上人の周りにも、実際に百万遍念仏を行う人がおられたようで、法然上人も百万遍念仏について言及なさっています。
「百万遍のこと、仏の願にては候わねども」とあります。
仏の願ではないのですね。
仏とはここではもちろん阿弥陀さまのことです。
阿弥陀さまの願は四十八ありまして、その中でも第十八願には「南無阿弥陀仏と称える者を極楽浄土に迎え取ろう」と誓って下さっています。
つまり「百万遍念仏を称えないと極楽には迎え取らない」とはおっしゃってません。
だから「仏の願にては候わねども」とおっしゃるのです。
「小阿弥陀経にもしは一日、もしは二日、乃至七日念仏申す人、極楽に生ずると説かれて候えば、七日念仏申すべきにて候」とあります。
小阿弥陀経といいますのは、いわゆる『阿弥陀経』のことです。
そこに「一日乃至七日念仏を申す人は極楽に往生する」と記されています。
もちろんお念仏というのは毎日、そして一生涯称えていくものですが、毎日お念仏を称えていますと私達には怠け心が出て参ります。
だんだん有り難味がなくなってくる、やる気が起こらなくなってくる。
そういうときに集中的にお念仏をお称えするのです。
これを「別時」といいます。
七日の別時、即ち七日間びっしりお念仏を称えた、その数が丁度百万遍に当たるというのです。
だから百万遍念仏は七日間で称えるというのが本義だけれども、七日で称えきれなければ八日、九日とかけて称えてもいいですよというのです。
実際には七日間で百万遍称えるのは難しいです。
一日に十四万遍以上称えないといけないですから相当に難しいことです。
法然上人でも一日に大体六、七万遍ですから、相当な数です。
寝てる暇も殆どないぐらいでしょう。
だから七日間で無理ならば、八日、九日と日延べしても構いませんというのです。
「しかし、百万遍称えないと往生できないのではないのですよ」とおっしゃっています。
「一遍、十遍の念仏でもちゃんと往生できますよ。一遍、十遍の念仏でも往生できる、その嬉しさに思わず百万遍という数が積もり、その功徳も重なっていくのですよ」とおっしゃるのです。
中国から百万遍という、「数」のみが伝わってきましたので「百万遍念仏しないと往生できない」と思う人が多かっのでしょう。
そこで法然上人は「違いますよ。一遍、十遍の念仏でもちゃんと往生できますよ」とお説きくださいました。
しかし根拠がないからといって百万遍念仏を否定するようなこともなさいません。
昔の人が「たった一遍、十遍のお念仏でさえも往生させていただける。何と有り難いことだ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と、その信仰の結果百万遍という数になったのですから、それはそれで真似をしたらいいのですよ、と考えておられたようです。