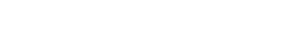前篇第二十三章 一枚起請文①
(本文)
唐土(もろこし)我が朝(ちょう)に、諸々(もろもろ)の智者達の沙汰(さた)し申さるる、観念(かんねん)の念にもあらず。又学問をして、念の心(こころ)を覚りて申す念仏にもあらず。ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生するぞと思いとりて申す外には別の子細(しさい)候(そうら)わず。但し三心(さんじん)・四修(ししゅ)と申すことの候(そうろ)うは、皆(みな)決定(けつじょう)して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思う中(うち)に籠(こ)もり候(そうろ)うなり。この外(ほか)に奥(おく)深(ふか)きことを存ぜば、二尊(にそん)の哀れみに外(はず)れ、本願に漏(も)れ候(そうろ)うべし。念仏を信ぜん人は、たとえ一代(だい)の法をよくよく学すとも、一文知(いちもんふち)の愚鈍の身になして、尼入道(あまにゅうどう)の無智の輩(ともがら)に同じうして、智者の振る舞いをせずしてただ一向(いっこう)に念仏すべし。
証(しょう)の為に両手印(りょうしゅいん)を以(もっ)てす。
浄土宗の安心(あんじん)起行、この一紙(いっし)に至極(しごく)せり。源空(げんくう)が所存(しょぞん)この外(ほか)に全く別義(べつぎ)を存(ぞん)ぜず。滅後(めつご)の邪義(じゃぎ)を防がんが為(ため)に所存(しょぞん)を記(しる)し畢(おわ)んぬ。
建暦(けんりゃく)二年正月二十三日
大師在御判
(現代語訳)
(浄土宗の念仏は、)中国や日本において、多くの智慧ある学僧たちが議論なさっている、仏を観想(かんそう)によって見ようとする念仏ではありません。また仏典を学び、念仏の意味を理解した上で称える念仏でもありません。
ただ、極楽に往生するためには南無阿弥陀仏と称えて、疑いなく往生するのだと思い定めて称える他に、特別の細かい条件もありません。
ただし三心・四修ということがありますが、それらはみな、「必ず南無阿弥陀仏と称えることによって往生できるのだ」と思う中におさまっているのです。
この他に奥の深いことを(私が)心に秘めているとすれば、釈尊と阿弥陀仏の慈悲を蒙(こうむ)ることができず、本願の救いからもれてしまうでしょう。
念仏を信じる人は、たとえ釈尊が生涯に説かれた教えを十分に学んでも、(自分を)一文字も知らない愚者とみなして、尼入道の中の無知な人々と同じ立場に立って、智者のようにふるまわず、ただひたすら念仏すべきです。
証のために両手印を押します。
浄土宗の安心・起行がこの一枚の紙に言い尽くされています。(私)源空の考えは、これ以外にまったく特別なことはございません。私亡き後の誤った理解を防ぐために、思うところを記し終わりました。
建暦二年(一二一二年)一月二十三日
源空 花押
(解説)
この一枚起請文は浄土宗で最もよく読まれるご法語であり、法然上人の代表的なご法語です。
この一枚起請文は法然上人がお亡くなりになる寸前に書かれたものですが、同じ内容のものをもっと以前から何人かのお弟子さんには託されていたようです。
ただ、内容は同じですが文章に多少の異動があります。
私たちが拝読する、この一枚起請文は法然上人がお亡くなりになる、わずか二日前に書かれました。
ご病状が思わしくなく、誰から見ても「先は長くない」という状況です。
長年身の回りのお世話をされていた勢観房源智上人は意を決して、
「法然上人、最後に浄土宗の肝要を残して下さい」と頼まれました。
法然上人は愛弟子からの願いに応えて病床から体を起こして筆を執られました。
それが一枚起請文です。
一枚起請文の最後に、「建暦二年正月二十三日」とあります。
建暦二年とは西暦1212年です。
この日に今の知恩院にて一枚起請文が書かれたのですが、その二日後、二十五日に法然上人は往生されました。
つまり法然上人のご命日は1212年の1月25日なのです。
先だっての2011年には法然上人の800回忌が行われました。
「証の為に両手印を以てす」とありますように、一枚起請文には文章の上に両手形が押されています。
この源智上人に授けられた一枚起請文が大本山黒谷金戒光明寺に残されています。
毎年4月23日、24日に法然上人のご法事、「御忌(ぎょき)」を行います。
京都では1月のご命日ではお参りになる方が寒くてお越しになりにいということで、ご命日から3ヶ月遅らせて法要を行っています。
その黒谷での御忌法要の際に一枚起請文が公開されます。
一度お参りされてご覧になって下さい。
さて、一枚起請文の「起請文」という言葉の意味です。
「起請文」とは神仏に誓って私が申し上げることに嘘偽りありませんと書く文をいいます。江戸時代になりますと、庶民も軽い感覚で起請文を書きました。
「起請文」歌舞伎や落語にも出て参ります。
遊女などが「年期が明けたらあなたの元に嫁ぎます」などと約束するようなものも伝えられます。
中世には武士などが起請文を残しています。
そこには「梵天、帝釈天に誓って私が申し上げることに嘘偽りございません。もし嘘であるならば、梵天、帝釈天から罰を受けても構いません」などと書かれています。
法然上人は「阿弥陀さまとお釈迦様に誓って嘘偽りありません」と誓っておられます。
さて本文に入ります。
「唐土我が朝に諸々の智者たちの沙汰し申さるる観念の念にもあらず」
「唐土」は中国、「我が朝」は日本です。
「中国や日本の偉いお坊さん達がこれこそすべきだとおっしゃっている観念の念ではありません」ということです。
「観念の念」とは、観相とか観仏、観法ともいう、仏を念じて心に仏を現す」修行です。「仏さまに会いたい」と思って念じれば、いつでも目の前に仏さまと会うことができる、「極楽の様子を観たい」と思って念じればいつでも目を開けていても閉じていても目の前に極楽を観ることができる、というものです。
口で言うのは簡単ですが、難行中の難行です。
しかし、今現在これができるという人はいません。
法然上人の時代でも殆どいませんでした。
もっと昔はできる人もたくさんいたのでしょう、時代が下るにつれて人々の能力が衰えて、観念の念をできる人がいなくなってしまったのです。
そのような「観念の念」ではありませんということです。
「また学問をして念の心をさとりて申す念仏にもあらず」
「学問をして念仏の意味内容をしっかりと理解して申せという念仏でもありません」ということです。
「ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生するぞと思いとりて申す外には別の子細候わず」
「ただ極楽浄土へ往生するためには声に出して南無阿弥陀仏と称え、お念仏によって間違いなく往生するんだと思い定めて念仏申す以外に細かいことはありません」ということです。
法然上人は「私が実践し、皆さんにお勧めしているのはごく限られた能力の高い人しかできない難しい修行や学問ではありません。ただ南無阿弥陀仏と申せば往生間違いなしと信じて念仏を称える以外に何もないのです」とおっしゃっているのです。
「ただし三心四修と申すことの候は、皆決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候なり」
「三心」とは、念仏称える者が極楽へ往生するために必ず具えておかなくてはならない三つの心です。
「お念仏を称えればよい」とだけ教えられたら、人によっては自分勝手な思いで称えることもあるでしょう。
大嫌いな人を思い浮かべて「あの人が不幸になりますように」と思ってお念仏を称える人がいるかも知れません。
しかしそんなお念仏で極楽へ往けるはずがありません。
人によっては「病気を治して下さい」「孫が大学に合格しますように」「宝くじが当たりますように」と願ってお念仏を称える人もいるでしょう。
しかしお念仏は極楽へ往生するための行です。
この世は苦しみ迷いの世界で、悩みの絶えない世界ですが、お念仏を称えていれば、命尽きた後には、阿弥陀仏が必ず絶対的な幸せの世界である極楽浄土へ迎え取ってくださいます。
だからお念仏を称えるに当たって思いの方向を定めておかなくてはなりません。
それを説かれたのが三心です。
難しいものではありません。
「本気で阿弥陀さまを信じて往生したいと願う」という三つの心なのです。
極楽へ往くための行がお念仏です。
ですから、極楽へ往きたいと願って称えるのです。
四修とは「念仏者がどういう生活を送るか」ということについて説かれたものです。
三心を具えたお念仏を称えればよいと聞いて「阿弥陀さま、どうか極楽へ往生させて下さい、南無阿弥陀仏」と称え、それを継続していくのです。
「これでもう往生間違いなし。後はもう称える必要もない」というのではいけません。
やはり継続しなくてはなりません。
そのために四つの指針を立てて下さったのです。
それが四修です。
一つ目は「阿弥陀さまや菩薩さまを敬う」ということです。
三心を具えてお念仏を称える者が阿弥陀さまや菩薩さまをないがしろにするはずがありません。
二つ目は「お念仏一筋に」ということです。
もちろん初詣に神社に行ったり知り合いの結婚式に教会に行くことを禁止しているのではありません。
「往生のため」にはお念仏だけでいいのだと思い定めるのです。
般若心経がよいと聞いたら般若心経を称え、お題目がよいと聞いたら南無妙法蓮華経と称え、真言がよいと聞いたら陀羅尼を称えるというようなことではないということです。
お念仏一本に絞るのです。
三つ目は「毎日お念仏を称える」ということです。
お念仏がありがたいと思っても、称えることを止めてしまうと信心も失います。
毎日のお念仏の回数を決めるのもよいでしょう。
一日○○遍と決めてそれを日課として実行するのです。
四つ目は「一生涯お念仏を称え続ける」ということです。
途中で止めてしまうと信仰が信仰でなくなります。
以上が四修です。
この三心も四修も大切です。
必ず必要なことです。
ですから先の文でも
「念仏を信じて称える以外に何もないとは言っても、理屈としては三心や四修という大事なことはある。
しかしそれも間違いなく南無阿弥陀仏で往生できると思う中に籠もっているのですよ。」と仰るのです。
三心や四修という言葉を知っているとか、理屈を知っているということは往生とは関係有りません。
南無阿弥陀仏と称えていれば間違いなく阿弥陀さまがお迎え下さって、極楽へ迎え取って下さるのだと信じてお念仏を称え続ける中にはしっかりと三心と四修がこもっているということなのです。
「この外に奥深きことを存ぜば、二尊のあわれみに外れ、本願に漏れ候うべし。」
「もしこれ以外に奥深いことを私が知っているのであれば、阿弥陀さまとお釈迦様のお慈悲から外れ、阿弥陀さまの本願から漏れてしまうでしょう」ということです。
法然上人は比叡山でご修行されている時には「智慧第一の法然房」と呼ばれていました。学問も修行も必死でされた、超優等生なのです。
ですが法然上人ご自身は「このような学問や難しい修行をいくら続けても、私の能力では悟りになど到底至ることはできない」と気づかれ、今までの学問も修行の功徳も地位も名誉も一切棄てて阿弥陀さまにお任せしてのお念仏生活を始められました。
ですから「学問も難しい修行も一切必要ない。ただ往生したいと願って阿弥陀さまをお慕いして南無阿弥陀仏と称えるだけである。これ以外に何もない」というのが法然上人の実感なのです。
しかし聞く側は「法然上人は、私たちのような愚かな者には南無阿弥陀仏だけでいいと言うけれど、ご自身は智慧第一の法然房だから、もっと奥深い何かをご存じで、愚かな我々には教えて下さらないんだ」などと言う人もいたのでしょう。
だから法然上人は「いや違う。もし私がこれ以上奥深い何かを知っていて、皆さんに伝えないというのであれば、阿弥陀さまやお釈迦様に私が見放されても構いません!」と誓われたのです。
ここが一枚起請文の起請文たる所以です。
先ほど、起請文とは神仏に誓って「私が申し上げることに嘘偽りありません」と表明する文章であると申しました。
一枚起請文は法然上人が阿弥陀さまとお釈迦様に誓って、「本当にこれだけで往生できるのです」と表明された文なのです。
前篇第二十二章 無常迅速
(原文)
それ朝(あした)に開くる栄花(えいが)は夕べの風に散りやすく、夕べに結ぶ命露(めいろ)は朝(あした)の日に消えやすし。これを知らずして、常に栄えんことを思い、これを覚らずして久しくあらんことを思う。しかる間、無常(むじょう)の風一度(ひとたび)吹きて有為(うい)の露永く消えぬれば、これを広野(こうや)に捨てこれを遠き山に送る。屍(かばね)はついに苔(こけ)の下に埋(うず)もれ、魂は独り旅の空(そら)に迷う。妻子眷属(けんぞく)は家にあれども伴(ともな)わず、七珍萬宝(しっちんまんぼう)は蔵に満てれども益(やく)もなし。ただ身に従(したご)うものは後悔の涙なり。ついに閻魔(えんま)の庁に至りぬれば、罪の浅深(せんじん)を定め、業(ごう)の軽重(きょうじゅう)を考えらる。法王(ほうおう)罪人に問うて曰(いわ)く、汝(なんじ)仏法流布の世に生まれて、何ぞ修行せずしていたづらに帰り来たるやと。その時には我ら如何(いかが)答えんとする。速やかに出要(しゅつよう)を求めてむなしく三途(さんず)に帰ることなかれ。
(現代語訳)
そもそも朝に咲く繁栄の花は夕方の風に散りやすく、夕方に結ぶ生命の露は翌朝の陽に消えやすい。これを知らずに常に繁栄することを求め、これをわきまえずにいつまでも生きていることを願うのです。
そうしている間に、一度無上の風が吹いて、はかない露のような命が永久に消えてしまうと、遺骸を広野に捨て、あるいは遠くの山に葬送します。屍は終に苔の下に埋もれ、魂はひとり、旅の空に彷徨います。妻子や親族が家にいても連れ添ってはくれません。金銀財宝が蔵に満ちていても何の役にも立ちません。ただ我が身につき随うものは、後悔の涙だけであります。
ついに閻魔大王の庁舎に着くと、(生前に犯した)罪の深さが鑑定され、善悪の行為の重さが裁かれます。大王が罪人に尋ねて言うには、「お前は仏法が流布している世に生まれながら、どうして何の修行もせず、空しく(ここに)戻ってきたのか」と。その時に我々は一体どう答えようというのでしょうか。
速やかに、輪廻を脱する要道を求めなさい。空しく三途に戻ってはなりません。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
このご法語のテーマは「無常」です。
無常とは、あらゆるものは変化するということです。
あらゆるものは変化し、形あるものはかならずいつか壊れる。
生きとし生けるものは一瞬一瞬に老いてゆき、病にもなりいつか必ず死にます。
それもいつ死ぬかわからないのです。
こんなことは誰でも知っていることです。
頭の中では誰もが当たり前のこととして、わかっていることです。
でもそれを考えると辛いものですから、普段はできるだけ考えないようにします。
死が迫ってきたとしても、死ぬということを考えることは縁起が悪いことだと、目を背けます。
しかし、どれだけ死を見ないようにしようとしても、嫌がっても、必ず誰もに死は訪れます。
法然上人は「必ずいつか命は尽きるのだから、のんびりしていてはいけませんよ、今お念仏を称えなくてはなりませんよ、死んでから後悔しても遅いですよ」とおっしゃるのです。
では本文を見て参りましょう。
「それ朝に開くる栄花は夕べの風に散りやすく、夕べに結ぶ命露は朝の日に消えやすし」
「朝に開いた花も夕方に風が吹けば簡単に散ってしまい、夕方に降りた露も朝の日の光によって蒸発してしまいます」
朝に開いた花は「栄える者」を表します。
どれだけ権勢を誇った者もそのままであり続けることは不可能です。
有名な平家物語には、当時「平家にあらずば人にあらず」とまで言われ、権勢を誇っていた平家が滅びていく様を語っています。
「沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす」と書かれています。
私たちも調子の良いとき、楽しいときは「その状態がいつまでも続く」と思い、また思おうとします。
しかしそれが続くことはあり得ません。
あり得ないのにそれがわからず、あの時はあんなに楽しかったのに」といつまでも良い状態の頃を思い、今を嘆くのです。
夕べに結ぶ命露は「人の命の儚さ」を表します。
生きていれば老いるのが当たり前、病になるのも当たり前です。
そして死ぬのは当たり前です。
でも老いることを認めず「アンチエイジング」などと言って、少しでも老いを先延ばしにしようとします。
しかしどれだけ抵抗しても確実に老いは進みます。
それを認めずに「少し前まではあんなに体の調子がよかったのに…」と思い、病になれば「なぜ私だけがこんな目に遭わなくてはならないの…」と嘆くのです。
「これを知らずして常に栄えんことを思い、これを覚らずして久しくあらんことを思う」「この無常の道理を知らずに常に栄えていようと思い、無常の道理を覚らないからいつまでも生きていようと思う」ということです。
「しかる間、無常の風ひとたび吹きて、有為の露永く消えぬれば、これを広野に捨てこれを遠き山に送る」
「そうこうしている間に、無常という名の風が一度吹けば、人間としての命は簡単に消え、遺体は広野に捨てられ、遠い山へと送られる」
今は死ねば遺体を火葬にするのが当たり前ですが、少し前までは土葬も残っていました。
もっと前は、遺体をそのまま野山など一定の場所に遺体を棄てていました。
京都には「西院」という場所がありますが、元々は賽の河原の「賽」であったところを、「さい」という音に西院という漢字を当てたのだそうです。
あの辺りまでが洛内で、あれより西は洛外でした。
嵐山の辺り、化野(あだしの)などは正に死体の捨て場だったそうです。
東山でも蹴上辺りは死体を棄てる場所だったと聞きます。
各地方にそういう場所があったようです。
「屍はついに苔の下に埋もれ魂は独り旅の空に迷う」
「屍はとうとう苔の下に埋もれ、魂だけが独り旅の空に迷う」
「妻子眷属は家にあれども伴わず、七珍萬宝は蔵に満てれども益もなし」
「妻や子、家族が家にいても一緒に逝くくとはできず、どんな宝が蔵を満たしていたとしても何の役にも立たないのだ」ということです。
「ただ身に従う者は後悔の涙なり」
「ただこの身には後悔の涙のみが残る」
「ついに閻魔の庁に至りぬれば罪の浅深を定め、業の軽重を考えらる」
「ついに閻魔大王のところに行けば、大王が罪の浅い深いを定め、業が軽いか重いかを考えて下さる」
閻魔大王は譬えです。
仏教では悪いことをする者は当然地獄に往き、欲深い者は餓鬼に往きます。
それは閻魔大王が判断するのではなしに、自然の摂理として業によって行き先が決まるのです。
「法王罪人に問うて曰く、汝仏法流布の世に生まれて何ぞ修行せずして徒に帰り来たるやと」
私たちは罪人なのです。
何の罪の意識もないのに煩悩があるだけで、知らず知らずの中に罪が積もっていきます。
罪の意識がないから余計にたちが悪いのです。
改善しようともしませんし、指摘されても「誰だってやっているじゃないか」と開き直ってしまいます。
また、気づいたところで自分の力ではどうにもなりません。
そういう私たちに閻魔大王が罪人に尋ねてこう言うのです。
「お前はこれだけ仏教が広まっている時代に生まれてきたのになぜ何の修行もせずにのこのここんなところに帰ってきたのか!」
「その時には我ら如何答えんとする」
「その時にどう答えるのか」
「速やかに出要を求めて虚しく三途に帰ることなかれ」
「さっさと苦しみ迷いの世を逃れることを求めて虚しく三途に帰ってくることがないようにしなくてはいけませんよ!」
三途とは「地獄・餓鬼・畜生」です。
「三途に帰る」とあります。
私たちは三途から来たから三途に帰るのです。
地獄か餓鬼か畜生にいて、そこで多少なりとも善いことをして、ようやく人間として生まれ、ようやく仏教の教え、お念仏の教えに出会ったのです。
それを「念仏なんて陰気くさいことしてられない」などと言ってお念仏を称えないようでは救われようがありません。
今おかれている自分の状況をしっかりと見つめ、今お念仏を称えなくてはならないことに気づかねばなりません。
そうしないで地獄に堕ちてから後悔しても遅いのです。今が称える時です。
非常に厳しく、また身につまされるお言葉です。
法然上人はやきもきしていらっしゃることでしょう。
「のんびりしている場合じゃない!今称えよ!」と。
前篇第二十一章 精進
(本文)
或いは金谷(きんこく)の花をもてあそびて、遅々(ちち)たる春の日を虚しく暮らし、或いは南楼(なんろう)に月をあざけりて漫々(まんまん)たる秋の夜(よ)をいたずらに明かす。或いは千里の雲にはせて、山のかせぎをとりて歳(とし)を送り、或いは万里の波に浮かびて、海のいろくずを獲りて日を重ね、或いは厳寒に氷を凌(しの)ぎて世路(せろ)を渡り、或いは炎天に汗をのごいて利養(りよう)を求め、或いは妻子眷属(けんぞく)に纏(まと)われて、恩愛(おんない)の絆(きずな)切り難し。或いは執敵怨類(しゅうてきおんるい)に会いて、瞋恚(しんに)の炎(ほむら)止むことなし。総じてかくの如くして、昼夜朝暮(ちゅうやちょうぼ)、行住坐臥(ぎょうじゅうざが)、時として止むことなし。ただ欲しきままにあくまで三途(さんず)八難(はちなん)の業(ごう)を重ぬ。しかれば或る文(もん)には一人(いちにん)一日の中(うち)に八億四(し)千の念あり、念々の中の所作皆これ三途(さんず)の業(ごう)と言えり。かくの如くして、昨日もいたづらに暮れぬ。今日もまた虚しく明けぬ。今幾(いく)たびか暮らし、幾(いく)たびか明かさんとする。
(現代語訳)
ある時は(荊州)金谷園(きんこくえん)の花を慰みとしてはのどかな春の日を空しく過ごし、ある時は(武昌県)南楼閣で月を詩に詠んでは長い夜をいたずらに明かすのです。
ある時は千里の雲の彼方まで走っていっては山の鹿を捕らえて年月を送り、ある時は万里の波間を漂っては海の魚を捕らえて月日を重ね、ある時は炎天下に汗を拭いながら財物を求め、ある時は妻子や親族にまとわり付かれて情愛の絆は断ちがたいのです。ある時は仇敵に出会って怒りの炎の消えることがありません。
すべてこのようにして、昼夜朝暮、立ち居起き臥し、少しの間も止むことがないのです。ただ勝手気ままに、どこまでも三途八難を招く悪業を重ねてしまいます。
ですから、ある経文には、「人間には、一日に八億四千の思いがわき起こる。その思いの中で行うことは、みな三途へ堕ちる悪業である」とあります。
このようにして昨日も空しく夜を迎えました。このうえ、いくたび夜を迎え、いくたび朝を迎えるのでしょうか。
(解説)
法然上人の教えは「誰もが救われる教え」です。
当時、救われないと諦めていた人々が「私も救われる」と感激し、瞬く間に広がりました。
多くの人に教えが広まることはありがたいことですが、法然上人がおっしゃることがそのまま伝わるのではなく、自分勝手な解釈をする者が多く出てきました。
例えば「念仏称える者は救われるが、それ以外の修行をしている者は救われない」という者、「念仏を称えてさえいれば何をしてもいい。どんな悪いことをしても救われるのだから」という者が多く現れて、間違った教えを巷で触れ回ったのです。
今まで法然上人の浄土宗を、天台宗の一派としかみていなかった比叡山も「それはおかしい」と考え出しました。
そこで法然上人は「浄土宗の教えはちゃんと仏教にのっとった教えですよ」ということを比叡山に伝えるために、お弟子の聖覚(せいかく)という方に文章を書かせ、手紙として比叡山に送りました。
この手紙は相当な長文です。
「比叡山に登る」という意味で「登山状(とざんじょう)」と呼ばれています。
今回のご法語は、その「登山状(とざんじょう)」の一節です。
「登山状(とざんじょう)」には色々なことが書かれていますが、今回のご法語は「私たちの生き方や今の生活」について説かれ、そのままでいいのですか?と問われているのです。
本文を見て参ります。
「あるいは金谷(きんこく)の花をもてあそびて遅々たる春の日を虚しく暮らし」
金谷(きんこく)といいますのは、昔中国に金谷園(きんこくえん)という立派な庭園があったそうです。
その庭園の持ち主、大金持ちが花を愛でて優雅に暮らす姿を「虚しく暮らし」つまり「無駄に」過ごしているとおっしゃっているのです。
「あるいは南楼(なんろう)に月をあざけりて、漫々たる秋の夜をいたずらに明かす」
これも中国晋の時代、ある将軍が南楼(なんろう)という大層立派な建物を建てて、風流に月見をしている姿が描かれています。
それを「いたずらに明かす」つまりこれも無駄に過ごしていると説かれるのです。
ここまでは大金持ちや風流人についてのことですが、ここからは労働者、私たちのことについておっしゃっています。
「あるいは千里の雲にはせて山のかせぎをとりて年を送り」
山のかせぎというのは鹿のことです。
鹿をとって過ごしている、これは猟師さんです。
「あるいは万里の波に浮かびて海のいろくずを取りて日を重ね」
こちらは海の漁師さんです。
海のいろくずは魚です。
「あるいは厳寒に氷を凌ぎて世路(せろ)を渡り」
厳寒の中を働き働き世間を渡っていく人です。
「あるいは炎天に汗をのごいて利養(りよう)を求め」
炎天下の中一生懸命働いて利益を求める人です。
「あるいは妻子眷属(けんぞく)に纏(まと)われて恩愛(おんない)の絆切り難し」
「あるいは妻子や一族の者達に頼られて情愛の絆を断ち切ることもできない」ということです。
「あるいは執敵怨類(しゅうてきおんるい)に会いて瞋恚(しんに)の炎(ほむら)止むことなし」
「時には大嫌いな人と会って瞋(いか)りの炎を燃やす」
「総じてかくの如くして昼夜朝暮(ちゅうやちょうぼ)行住坐臥(ぎょうじゅうざが)時として止むことなし」
「すべてこのようにして昼も夜も朝も夕暮れも、いつでもどこでもどんな時も、一瞬たりとも心を悩まさない時はない」
「ただ欲しきままにあくまで三途八難(さんずはちなん)の業(ごう)を重ぬ」
「ただ心の赴くままにどこまでも地獄(じごく)、餓鬼(がき)、畜生(ちくしょう)行きの行いを重ねていく」
「しかれば或る文には一人一日(いちにんいちにち)の中(うち)に八億四千の念あり」
私たちは朝から晩まで一つのことをジッと考え続けているわけではありません。
浄土菩薩経というお経には、人が一人過ごすのに八億四千の心の動きがあると記されています。
「念々の中の所作、皆これ三途(さんず)の業(ごう)といえり」
「一瞬一瞬の心の行いはすべて地獄・餓鬼・畜生行きの行いばかりである」というのです。
「かくの如くして、昨日もいたずらに暮れぬ。今日もまた虚しく明けぬ」
「このようにして昨日も無駄に暮れていった。今日もまたこうやって虚しく明けていく」
「今幾たびか暮らし、幾たびか明かさんとする」
「これから何度このような日々を送るのですか」ということです。
非常に厳しい内容ですね。
しかしよく見ますと、そんなに悪いことは書かれていません。
人殺しをしたとか、人のものを盗んだとか、人を騙したという人はこのご法語には出てきません。
普通の人々です。
最初のお金持ちにしても、お金の力で人に嫌がらせをしたということではありません。
風流人といっても、月見をしているというだけで、決して悪いことをしたということは書かれていないのです。
また、労働者は鹿を捕ったり、魚を獲らなければ生きていけないのです。
寒い中、あるいは炎天下に一生懸命働く人、家族仲良く暮らす人、時には嫌いな相手と会って、腹を立てるということがあっても、その程度です。
正に私たちの現状ですね。
私たちは特別な善人ではなくても、どちらかといいますと善良な市民ですよね。
人から後ろ指を指されるようなことはしていないつもりです。
ところが、私たちの行いすべてが地獄・餓鬼・畜生という、恐ろしいところに生まれなくてはならないほどの悪い行いだというのです。
その原因は煩悩にあります。
普通に生きているつもりでも、私たちの行いは、ほぼ煩悩による行いです。
自分を生かそう、生かそうと思って必要以上にものを欲しがり、自分を生かそうという余り、自分にとって不都合な人に腹を立てるのです。
そういう行いを続けている私たちは知らず知らずの中に、地獄・餓鬼・畜生行きの行い、罪が積もっていくのです。
「誰だってやっていることじゃないか!」と腹を立てても仕方がありません。
何の悪いことをしたつもりがなくても悪い業(ごう)が積み重なっていきます。
まるで「お医者さんに罹ったことがない」と言っている人の体の中で、知らない間に病気が進行していくかのようです。
それなのに気づかず、対処をしないようでは、救われようがありません。
そんな私たちが今できることといったらお念仏を置いて他にはありません。
普通に暮らしていて何の自覚もないままに地獄・餓鬼・畜生に生まれているようではあまりにも悲しいではありませんか。
今気づいて今なすべきお念仏を称えなくてはならないのです。
前篇第二十章 難修観法
(原文)
近来(ちかごろ)の行人(ぎょうにん)、観法(かんぼう)をなすことなかれ。仏像を観(かん)ずとも、運慶(うんけい)康慶(こうけい)が造(つく)りたる仏(ほとけ)ほどだにも観(かん)じ現すべからず。極楽の荘厳(しょうごん)を観(かん)ずとも櫻梅桃李(ようばいとうり)の花果(けか)ほども観(かん)じ現(さんこと難(かた)かるべし。彼(か)の仏(ほとけ)今(いま)現に世に在(ましま)して成仏(じょうぶつ)し給(たま)えり。当(まさ)に知るべし本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)虚(むな)しからざることを。衆生(しゅじょう)称念(しょうねん)すれば必ず往生を得(う)の釈を信じて、深く本願を頼みて、一向(いっこう)に名号(みょうごう)を称(とな)うべし。名号(みょうごう)を称(とな)うれば三心(さんじん)自(おの)ずから具足(ぐそく)するなり。
(現代語訳)
今の時代の仏道修行者は、観想(かんそう)の行法(ぎょうほう)を行ってはなりません。仏の姿を観想(かんそう)しても、運慶(うんけい)や康慶(こうけい)が造った仏像ほども、ありありと想い画くことはできません。極楽の荘厳(しょうごん)を想い画いても、(この世の)桜、梅、桃、李(すもも)の花や果実ほども、ありありと想い画くことは困難でしょう。
「かの(阿弥陀)仏はいま現在、(極楽)世界にあって、仏となっておられる。阿弥陀仏が立てられた、深重(じんじゅう)なる誓願(第十八願)が実を結んでいることを、当然わきまえるべきである。衆生が称名念仏すれば必ず往生できる」という(善導大師の)解釈を信じ、深く本願を頼みとして、ひたすらに(阿弥陀仏の)名号を称えるべきです。名号を称えれば三心が自ずと具わるのです。『法然上人のお言葉』(総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
念仏といいますと「南無阿弥陀仏と称えること」というのが、今では当たり前ですが、実は念仏には色んな種類があります。
法然上人の時代には、声に出す「称名念仏」は主流ではありませんでした。
「念仏」は「仏を念じる」と書きますように、「心に仏を映し出す」という修行法を主に「念仏」といったのです。
「心に仏を映し出す」といいますと、何となく仏さまをイメージする程度のことかと思われるかも知れませんが、そんな簡単なことではありません。
目を開けていても閉じていても、いつでもどこでも「阿弥陀さまと会いたい」と思えば目の前にありありと阿弥陀さまが目の前に現れ、「極楽を観たい」と思えばいつでも目の前に極楽の情景を観ることができるというものです。
これを観法(かんぼう)とか、観相(かんそう)念仏とか、観念(かんねん)の念と申します。
口で言うのは簡単ですが、非常に高度な修行です。
それにそれが出来たらもう修行が完成して、悟りに至ることができるのかというとそうではありません。
まだ修行の過程なのです。
恐らく今現在この観法(がんぼう)ができる人はいないでしょう。
法然上人の時代にも殆どいませんでした。
法然上人は観法をしたいと思ってされたわけではありませんが、晩年称名念仏をしている内にできるようになられました。
しかし法然上人の時代であってもごく一部の修行者にしかできませんでした。
もちろんお釈迦さまの時代には多くの修行者ができました。
時代を経るに従って、どんどん人々の宗教的な能力が衰えてきて、できなくなってきました。
それにも関わらず修行者は、みんな観法をしようとします。
法然上人も比叡山に於いて観法の修行を続けられました。
修行者達はできもしない観法をずっと続け、亡くなっていきます。
悟りに至ることなしに、修行半ばで命が尽きると元の木阿弥です。
8割できたから死んだら続きをするわけにはいきません。
死ねばまた輪廻して、どこかに生まれ変わって仏教と出会うことができるかさえもわかりません。
法然上人は、「多くの修行者達は一生懸命修行をしている。けれども悟りどころか観法もできないじゃないか。私もできずに死んでいくのか…」と悩まれました。
そして苦しみ続け、称名念仏の道と出会われたのです。
観法をする修行は自力の修行です。
自分が悟りに向かって上がっていく方法です。
修行をして自分を高めていくのです。
方や称名念仏は自分が上がっていく教えではありません。
自分はそのまま、低いままです。
「自分の力では到底救われない。いや、このままでは地獄に行くしかない」という自分の器に気づき、阿弥陀さまにすがって「南無阿弥陀仏」と称えたならば、自分が上がるのではなく、阿弥陀さまが私たちの処に降りてきて、寄り添って下さり救って下さるのです。自分が上がるのではなく阿弥陀さまがすくい上げて下さるのです。
この阿弥陀さまの力を他力といいます。
お釈迦さまは末世(まっせ)の凡夫(ぼんぶ)のためにお念仏をお説き下さいました。
末世の凡夫は観法ではなく称名念仏をせよと。
観法をする力がないのにいつまでも観法をしていたら、どれだけ時間が経っても悟りの世界からはほど遠いということになります。
その辺りをふまえていただき、本文をご覧いただきたいと思います。
「近来の行人、観法をなすことなかれ。」「今の修行者は観法をすることはないですよ。」ということです。
末世の凡夫には観法ではないのです。
「仏像を観ずとも、運慶、康慶が造りたる仏ほどだにも観じあらわすべからず。」
観法の修行段階で、いきなり仏さまを観ようとしても絶対観ることはできませんので、まず仏像を観て、それを心に映し出そうとするのです。しかし、私たちの能力からいくと、仏像を観ても所詮仏像を超えることはできません。ましてや運慶や康慶といった鎌倉時代の超一流仏師が造る仏像を超えるほどの力は決してないということです。
「極楽の荘厳を観ずとも、桜梅桃李の花果ほども観じあらわさんこと難かるべし。」
「極楽の様子を観ようとしても所詮桜や梅、桃、すももなどの美しさを超えることはできません。」
極楽の美しさはこの世の美しさとは比べものにならないほど美しいはずです。
それなのにこの世の桜や梅、桃、すももの美しささえも超えることができないほどの力しかないではないか、ということです。
その私たちのために阿弥陀さまはおられます。
「彼の仏今現にましまして成仏したまえり。正に知るべし。本誓の重願虚しからざることを。衆生称念すれば必ず往生を得の釈を信じて、深く本願を頼みて一向に名号を称うべし」
阿弥陀さまは今現在極楽浄土におられて仏となっておられます。
決して昔の話ではないんです。
今現在、今こうしている間も阿弥陀さまは「我が名を呼ぶ者を救うぞ。頼む、称えてくれ。」と願って下さっています。
決して阿弥陀さまの本願は虚しいものではない、「救うことができなかったら仏にならないと誓われたのにちゃんと仏になっておられるのだから。人々が称名念仏を称えれば必ず往生できるという言葉を信じて、深く本願を頼りに一筋に南無阿弥陀仏と称えよ」ということです。
「名号を称うれば三心自ずから具足するなり。」
「南無阿弥陀仏と称えれば心も自然とついてきますよ」ということです。
「お念仏と言いますが、中々難しいですわ」とよくおっしゃいますが、本来の修行、観法と比べたらそんなことは言えないでしょう。
「私救われたいんです。」という人に「そうですか。では観法をしましょう」と言われたらもう救われることを諦めざるを得ません。
法然上人の時代はそうだったのです。
だから称名念仏の教えがすぐに広まったのです。
救われないと諦めている人のところに阿弥陀さまがそっと寄り添って下さって、「そうかそうか、救われたいか。ならば私の名前をお呼び。救ってやるから」と言って下さっているのです。
救いを諦めている人からすると、「そんな簡単に救われるんですか!」という思いでしょう。
お念仏が簡単か難しいかは「救われたいかどうか」にかかっているのです。
前篇第十九章 乗仏本願
(原文)
他力本願に乗(じょう)ずるに二つあり、乗(じょう)ぜざるに二つあり。乗(じょう)ぜざるに二つというは、一つには罪を作るとき乗(じょう)ぜず。その故は、かくの如く罪を作れば念仏申すとも往生不定(ふじょう)なりと思うときに乗(じょう)ぜず。二つには道心(どうしん)の起こるとき乗(じょう)ぜず。その故は、同じく念仏申すとも、かくの如く道心(どうしん)ありて申さんずる念仏にてこそ往生はせんずれ。無道心(むどうしん)にては念仏すとも叶うべからずと、道心(どうしん)を先(さき)として本願を次に思うとき乗(じょう)ぜざるなり。次に本願に乗(じょう)ずるに二つの様(よう)というは、一つには罪作るとき乗(じょう)ずるなり。その故はかくの如く罪を作れば、決定(けつじょう)して地獄に堕(お)つべし。然(しか)るに本願の名号(みょうごう)を称(とな)うれば、決定(けつじょう)往生せんことの嬉しさよと喜ぶときに乗(じょう)ずるなり。二つには道心(どうしん)起こるとき乗(じょう)ずるなり。その故は、この道心(どうしん)にて往生すべからず。これ程の道心(どうしん)は無始(むし)よりこのかた起これども、未(いま)だ生死(しょうじ)を離れず。故に道心(どうしん)の有無を論ぜず、造罪(ぞうざい)の軽重(きょうじゅう)を言わず、ただ本願の称名(しょうみょう)を念々相続(ねんねんそうぞく)せん力に依りてぞ往生は遂(と)ぐべきと思うときに、他力本願に乗(じょう)ずるなり。
(現代語訳)
(阿弥陀仏の)他力本願に乗じる場合に二つあり、乗じない場合に二つがあります。
「乗じない場合に二つ」とは、第一に、罪を犯す時に乗じません。そのわけは、「このように罪を犯せば、念仏を称えても往生は確かでない」と思う時には乗じないからです。
第二に、菩提心が起こる時に乗じません。そのわけは、「同じように念仏を称えても、このように菩提心があって称える念仏によってこそ、往生できるであろう。菩提心がなくては念仏しても叶うはずがない」と(自らの)菩提心を優先させ、(仏の)本願を二の次に思う時には乗じないからです。
次に、本願に乗じる場合の二つのありようとは、第一に、罪を犯す時に乗じます。
そのわけは、「このように罪を犯せば、必ず地獄に堕ちるだろう。けれども、本願の名号を称えれば、必ず往生できるとは何と喜ばしいことか」と喜ぶ時には乗じるからです。
第二に、菩提心が起こる時に乗じるのです。そのわけは、「この菩提心によっては往生できない。この程度の菩提心は、遠い過去から今まで(何度も)起こしてきたが、いまだ私は迷いの境涯を離れてはいない。だから菩提心の有無に関わらず、犯した罪の軽さ重さを問わず、ただ本願の称名念仏を絶え間なく続ける力によってこそ、往生は遂げることができる」と思う時には他力本願に乗じるからです。
『法然上人のお言葉』(総本山知恩院布教師会刊)
仏教には「自力の仏教」と「他力の仏教」があります。
自力の仏教とは「修行や難しい学問をして、自分自身を高めて最終的に覚りを得よう」という教えです。
つまり「自分の力で覚りを開こう」という教えです。
その「自分の力」を「自力」といいます。
片や「他力の仏教」とは、どういうものか。
難しい修行や学問などできないどころか日々煩悩により悪い行いばかりを繰り返して、到底覚りなど覚束ないと自覚した者を、阿弥陀仏という仏さまが見るに見かねて、「私の名前を呼ぶ者を救ってやろう」と言って下さいました。
それを信じて南無阿弥陀仏と称えるならば、阿弥陀さまの力によって初めて極楽浄土へ救いとって頂けるという教えです。
その「阿弥陀さまの力」を「他力」といいます。
このように申しますと、それなりに「そういうものか」とご理解いただけると思うのですが、完全に「他力」というものをご理解いただくことはとても難しいのです。
分かったようでわからないのが「他力」ではないでしょうか。
なぜわかりにくいのかと言いますと、「自分の力も認めたい」という心が誰しもあるからです。
「阿弥陀さまの力によって救われる」と言いながら、「しかし私の力だって少しは役に立っている」と思いたいのですね。
ここに二人の信仰者がいるとしましょう。
一人は家でお念仏を称えています。
そしてもう一人は西国霊場をすべて回ってお念仏を称えているとします。
西国霊場を回ってお念仏を称える人は、「私は家でお念仏を称えている人よりも少しレベルが高い」と思ったりします。
西国霊場を回っても極楽浄土へ往生できないのに、南無阿弥陀仏と称える者を救うと言って下さっているのに、私の努力で少しは近づいたような気になるものです。
それでは他力を理解したとは言い難いですね。
私達は自分の力では往生できません。
往生するのに自分の力は少しも役に立ちません。
阿弥陀さまの力によって初めて往生できるのです。
もちろん霊場巡りをすることが悪いはずはありません。
仏菩薩に対する敬いの心は、とても尊いことです。
ただ、その「私の努力」によって極楽へ往生するのだ、という心は慢心です。
尊いことをする時も注意しないと、ついつい強い「我」が出てくるものです。
また、自分は罪深いのだと思うが余り「南無阿弥陀仏で往生できるはずはない。そんな簡単に救われるはずがない」と阿弥陀さまを信じることができない人も往生できません。
先の「自力」を頼る人、後の自分を卑下して阿弥陀さまの救いの力を疑う人は共に往生できません。
しかしこういう人が多い。
そこで今日の御法語があるのです。
少しややこしい御法語で、何気なく読むと「さっきこうかいてあったのに次は逆のことが書いてある」と思うかもしれません。
ですから少し丁寧にお読み下さい。
「他力本願に乗ずるに二つあり、乗ぜざるに二つあり」
「阿弥陀さまの本願の力で往生できるのに二つのパターンがある。
また往生できないのに二つのパターンがある。」
「乗ぜざるに二つというは、一つには罪を造るとき乗ぜず。」
「往生できない二つのパターンの内、一つは罪を造ると往生できません。」
罪を造る人は往生できないといいます。
しかし念仏の教えは罪を造る者でも往生させていただけるという教えですよね。
「どうしてだろう?」と思いつつ読み進めることにします。
「その故は、かくの如く罪を造れば、念仏申すとも往生不定なりと思う時に乗ぜず」
「なぜならば、このように罪を造っていたら念仏を称えていても往生なんてできないと思ってしまう場合には往生できません」
先ほど申し上げたことですね。
自分が罪深いと思うが余りに阿弥陀さまの力さえも疑ってしまうようではダメです。
「二つには道心の起こる時乗ぜず。」
「二つ目は道心が起こる場合は往生できません。」
道心というのは「必ず覚りを開くぞ」という強い心です。
ですから決して悪い心ではありません。
むしろ善い心です。
しかし道心がある人はダメだというのです。
なぜか?と思いつつ読み進めていきます。
「その故は、同じく念仏申すとも、かくのごとく道心ありて申さんずる念仏にてこそ、往生はせんずれ。無道心にては念仏すつも叶うべからずと、道心を先として、本願を次に思う時乗ぜざるなり」
「なぜならば、同じように念仏を申していても、私のように道心があって申す念仏によってこそ、往生できるのだ。道心がなければ念仏していても往生なんてできっこないと、道心を優先して阿弥陀さまの本願を次に思ってしまうようでは往生できません」ということです。
先に申し上げた西国霊場を巡る人がこのパターンですね。
自分が「悟るぞ」という強い心を持っているからこそ往生できるのだと、自力を頼ってしまうのです。
阿弥陀さまの力よりも自分の力を頼る、あるいは阿弥陀さまの力で救われるのだけれども、自分の力も加わってこそ往生は叶うというように他力を信じ切れないのではダメです。
「次に、本願に乗ずるに二つの様というは、一つには罪造る時乗ずるなり。」
「次に阿弥陀さまの本願によって往生できるのに二つのパターンがあるという内の一つは、罪を造る場合は往生できます」
前半では罪を造る人は、自分の罪深さを自覚する余り、阿弥陀さまでも私など救うことはできないと阿弥陀さまの力を疑うからダメだと書かれていました。
しかし今度は罪を造る人が往生できるとあります。恐る恐る読み進めて参ります。
「その故は、かくの如く罪を造れば、決定して地獄に堕つべし。しかるに、本願の名号を称うれば、決定往生せんことの嬉しさよと喜ぶ時に乗ずるなり」
「なぜならば、このように罪を造っていたら、間違いなく地獄に堕ちるであろう。しかしながら、阿弥陀さまの本願である南無阿弥陀仏のお名号を称えていたら、間違いなく往生できるということが嬉しいなあ、と喜ぶ場合は往生できます。」ということです。
日々罪を造る私達は、そのままでは到底極楽往生など覚束ない者です。
地獄行き間違いないなのです。
しかし、そんな私が南無阿弥陀仏と称えて阿弥陀さまにすがれば間違いなく往生できるのです。
自力では100%往生できない者が他力によって100%往生させていただけるのですから、こんな有り難いことはありません。
それをしっかりと分かって念仏を称える者は大丈夫ですよということですね。
「二つには道心起こる時乗ずるなり」
「二つ目は道心が起こる場合は往生できます」
先ほどは道心が起こる人は自力に頼って他力を侮るから往生できないとされたのが、今度は往生できるとあります。「おや?」と思いつつ読んでいきます。
「その故は、この道心にて往生すべからず。これ程の道心は無始よりこのかた起これども、未だ生死を離れず。故に、道心の有無を論ぜず、造罪の軽重を言わず、ただ本願の称名を念々相続せん力に依りてぞ、往生は遂ぐべきと思う時に、他力本願に乗ずるなり」
「なぜならば、この道心で往生するのではない。この程度の道心は過去に輪廻を繰り返す内に起こったこともあるであろうが、未だに輪廻しているではないか。だから道心の有無は関係ないのだ、罪の軽い重いも関係ないのだ、ただ阿弥陀さまの本願である称名念仏をずっと続けていくことによってのみ、往生できるのだと思う場合に阿弥陀さまの本願によって往生できるのだ」
無始というのは、始まりのない昔という意味で、前世、前前世、ずーと昔ということです。この程度の道心は何度も輪廻を繰り返す中で起こしたこともあるだろう。
でもまだ人間として輪廻の輪の中で苦しんでいるじゃないか。
そんな私が起こす程度の道心なんて何の足しにもならないではないか、という自覚をした上で、阿弥陀さまにすがるしかないと気づいた人は往生できるのです。
阿弥陀さまは、「わが名を呼ぶ者を救う」と言って下さっています。
ただそれだけです。
なのにこちら側が勝手に「私の罪ではダメだ」とか、「あの人と比べたら私の方が頑張ってる」と他人と比較して上だとか下だとか言っているのです。
阿弥陀さまからご覧になれば、ドングリの背比べです。
何の違いもないのです。
「ただすがれよ」と言って下さっている、それを素直に信じていくのです。
このことを私はいつも大きな川を渡るという比喩を以て説明します。
大きな川があるとします。その川は濁流です。
こちらの岸は食べる物もないし、そのことで争いが絶えない世界です。
でも向こう岸は楽園です。向こうに渡れば助かるのです。
自力の人は体を鍛えて向こう岸に渡ろうとします。
でも実際に渡れる人は殆どいません。途中で溺れてしまいます。
私達はどうかといいますと、背中に籠を背負わされ、次々に重い石が積まれています。
背中にたくさんの石を抱えたままでは泳ぐどころか水に入ったらたちまちに沈んでしまいます。
途方に暮れていると、阿弥陀さまが見るに見かねて大きな舟を用意して下さいました。
どんな大きな石を背負っていようと、どんなに重い石を抱えていようとも阿弥陀さまの舟に乗れば必ず向こう岸に渡していただけます。
阿弥陀さまは「早く乗れよ。必ず向こうに渡してやるから。」と呼びかけて下さいます。その声に応えて阿弥陀さまの舟に素直に乗れば必ずや向こう岸へ渡り、幸せに過ごすことができるのです。
しかしある人は、「私はみんなよりたくさんの重い石を背負っているから、阿弥陀さまの舟に乗ったらきっと舟が沈んでしまう」と言って阿弥陀さまの舟に乗ろうとしません。
阿弥陀さまも舟に乗らない人は向こう岸へ渡すことはできません。
これはまるで「私のような罪深い者は絶対に救われない」と言ってお念仏を称えない人のようではありませんか。
せっかく阿弥陀さまが必ず救うと言って下さっているのにこちら側がその声を信じることができないのであればどうしようもありません。
またある人は、背中に積もった石を一つずつ放って籠を軽くしようとしています。
でも放った先からまた石は積まれていきます。
ところが本人は石がどんどん積まれていることに気づいていません。
阿弥陀さまは「お前も重い石を背負っているな。この舟に乗らないと自分で泳いだら沈んでしまうぞ」と言って下さっています。
でもこの人はそんな声に耳を傾けず、「大丈夫大丈夫。私は何も背負っていないし体をいつも鍛えている。だから泳いで向こうへ渡れるさ」と言います。
しかし実際には重い石を背負っているのですぐに溺れてしまいます。
これはまるで西国霊場を巡って自分が偉くなったような気がしている人のようではありませんか。
阿弥陀さまはただ「わが名を呼ぶ者を救う」とおっしゃっているのですから、それを信じて称えるのみです。
こちら側の浅はかな計らいで、罪が軽いとか深いとか、道心があるとかないとかを無駄に悩んで阿弥陀さまを信じることができないようでは話になりません。
私達は自分の力では決して救われることはないですが、阿弥陀さまの力、即ち他力によってのみ救われるのだということにしっかりと思いを定めねばなりません。