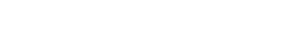前篇第二十七章 親縁
(本文)
善導(ぜんどう)の三縁(さんねん)の中(うち)の親縁(しんねん)を釈し給(たも)うに、衆生(しゅじょう)仏(ほとけ)を礼(らい)すれば、仏これを見給(みたも)う。衆生仏を称(とな)うれば、仏これを聞き給う。衆生仏を念ずれば、仏も衆生を念じ給う。故(かるがゆえ)に阿弥陀仏の三業(さんごう)と行者(ぎょうじゃ)の三業と、かれこれ一つになりて、仏も衆生も親子の如(ごと)くなる故(ゆえ)に、親縁(しんねん)と名付くと候(そうら)いぬれば、御手(おんて)に数珠(じゅず)を持たせ給いて候わば、仏これを御覧候うべし。御心(おんこころ)に念仏申すぞかしと思(おぼ)し召(め)し候わば、仏も行者を念じ給うべし。されば、仏に見(まみ)え参らせ念ぜられ参らする御身(おんみ)にて渡らせ給い候わんずるなり。さは候へども、常に御舌(おんした)の働くべきにて候うなり。三業(さんごう)相応のためにて候うべし。三業とは、身(み)と口(くち)と意(こころ)とを申し候うなり。しかも仏の本願の称名(しょうみょう)なるが故に、声(こえ)を本体とは思(おぼ)し召(め)すべきにて候。さて我が耳に聞こゆる程申し候は、高声(こうしょう)の念仏の中(うち)にて候なり。
(現代語訳)
善導大師が三縁(さんねん)の中の親縁(しんねん)を解釈されたところに、「衆生が〔阿弥陀〕仏を礼拝すれば、仏はこれをごらんになる。衆生が仏〔の名号〕を称えれば、仏はこれをお聞きになる。衆生が仏を念ずれば、仏も衆生をお念じになる。それゆえ阿弥陀仏の三業(さんごう)と行者(ぎょうじゃ)の三業とが、それぞれに一致して、仏も衆生も親子のようになるので、親縁と名づける」とありますので、御手で数珠を繰っておられるならば、仏はこれをごらんになるでしょう。心に「念仏を称えるのだ」とお思いになれば、仏も行者もお念(おも)い下さるでしょう。
それゆえ仏にごらんいただき、お念(おも)いいただく身とおなりになるでしょう。
そうは申しましても、常に舌をはたらかさねばなりません。三業を一致させるためであります。三業とは身体と口と意(こころ)と〔の行為〕を申すのです。しかも〔阿弥陀〕仏の本願である称名念仏なのですから、声に出すことを根本とお思いになるべきであります。
さてその場合、自分の耳に聞こえる程度に称えれば、高声(こうしょう)の念仏のうちに入るのです。
(解説)
「三縁(さんえん・さんねん)」とは、浄土宗の高祖(こうそ)善導大師(ぜんどうだいし)が、「私たちと阿弥陀さまはどういう関係なのか」ということを三つに分けて説いて下さったものです。
一つ目は「親縁(しんえん・しんねん)」です。
阿弥陀さまと私たちはまるで親子のような関係なのだということで、親縁といいます。
二つ目は近縁(ごんえん・ごんねん)」です。
お念仏を称える者には、常に阿弥陀さまが寄り添って下さるということです。
目には見えませんが、お念仏を称えていると目の前に、すぐ近くに阿弥陀さまが居て下さるというのです。
だから近い縁と書いて近縁といいます。
三つ目は増上縁といいます。
お念仏を称える者の臨終の時に、私たちが犯してきた数え切れないほどの罪を滅して、必ず阿弥陀さまが多くの菩薩さまを引き連れてお迎えに来てくださり、そして極楽へ導いてくださいます。
これを増上縁といいます。
この御法語はその三縁の中の特に親縁についてお説き下さったものです。
私たちは毎日多くの行いをしています。
これを業(ごう)といいます。
業はどこで起こすかというと、体と口と心で起こします。
懺悔偈(さんげげ)には、「我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋痴 従身語意之所生 一切我今皆懺悔」とあります。
「私が昔から造ってきた数々の悪い行いは、皆貪瞋痴という煩悩によるものである。これらは、身語意から生じたものである。これらの罪をすべて懺悔いたします」ということです。
ここでいう身とは体です。
語とは言葉です。
意とは心です。
身口意(しんくい)ともいいます。
身業(しんごう)、口業(くごう)、意業(いごう)の三つを三業といいます。
私たちの三業をあみださまに向ければ、阿弥陀さまも三業で応えてくださるといいます。
本文を見て参りましょう。
「善導の三縁の中の親縁を釈し給うに、衆生仏を礼すれば、仏これを見給う。衆生仏を称うれば、仏これを聞き給う。衆生仏を念ずれば、仏も衆生を念じ給う」
「善導大師がお説き下さった三縁の内の親縁がどのように説かれているかというと、人々が阿弥陀さまに礼拝、体で敬いを表せば阿弥陀さまはこれを見て下さる」これは身業です。
「人々が念仏を称えれば阿弥陀さまはこれを聞いてくださる」これは口業です。
「人々が阿弥陀さまのことを思えば、阿弥陀さまも人々のことを思ってくださる」これは意業です。
「故に阿弥陀仏の三業と行者の三業とかれこれ一つになりて、仏も衆生も親子の如くなるゆえに、親縁と名付くと候いぬれば、御手に数珠を持たせ給いて候わば、仏これをご覧候うべし。御心に念仏申すぞかしと思し召し候わば、仏も行者を念じ給うべし」
「だから阿弥陀さまの三業と我々の三業とが一つになって、阿弥陀さまも私たちも親子のようになるから親縁と名付けるとおっしゃるのだから、手に数珠を持っておれば、阿弥陀さまはこれをご覧くださることでしょう。心にお念仏を申していると思っていると、阿弥陀さまもあなたを思ってくださることでしょう」
数珠はお念仏を数える道具です。
お念仏を数えなかったら、数珠を持っていても意味がありません。
ですから、数珠を持つときは必ずお念仏を称える時なのです。
そうやって数珠を繰っていれば、その行為を阿弥陀さまはご覧くださるのです。
そして阿弥陀さまを思えば阿弥陀さまもあなたを思ってくださいます。
「されば、仏に見え参らせ念ぜられ参らする御身にて渡らせ給い候わんずるなり」
「そんな風に阿弥陀さまにご覧いただき、思っていただくような御身でいらっしゃるのです」
私たちは普段煩悩のままに過ごしています。
好き勝手に過ごしていると言ってもいいでしょう。
先ほどの懺悔偈のように、数々の悪業を積み重ねている私たちです。
これも私と言えます。
しかし、阿弥陀さまに心を寄せれば、阿弥陀さまがご覧くださり、思ってくださるような私でもあるわけです。
これも私です。
同じ私でも随分違います。
あっちこっちとフラフラしている私であるけれど、阿弥陀さまに身と口と心を向けていけば、阿弥陀さまにも身と口と心を向けていただけるようにもなれます。
そんな私になりたいものです。
「さは候えども、常に御舌の働くべきにて候うなり。三業相応のためにて候うべし。三業とは、身と口と意とを申し候うなり」
「そうは言ってもやはり舌が動くべきです。三業が整うことが大切です。三業とは身と口と意です」
数珠を持ち、心に阿弥陀さまを思って、身業と意業が阿弥陀さまに向いても、やはり舌が動く、つまり声を出さねばなりません。
「しかも仏の本願の称名なるが故に、声を本体とは思し召すべきにて候」
「しかも阿弥陀さまの本願は称名であるから、声を出すのが本来です」
よく私は心の中でお念仏を称えていますとおっしゃる方がおられます。
しかし阿弥陀さまの本願は「名を称えよ」です。
「名を称えよ」ということは声を出すべきです。
心の中でお念仏を称えると言っても、一瞬しかできません。
続けることは大変に困難です。
しばらく心の中でお念仏を称えればわかります。
気がつけば全く違うことを考えている私たちです。阿弥陀さまはこのような私たち、心の弱い私たちをよくご存じです。
だから心で称えよとはおっしゃいません。
わが名を称えよなのです。声に出して称えていても心は相変わらず乱れます。
でも称えていると、また心が戻ってくる場所があります。
心の中で称えていれば、心が彷徨ったまま帰って来ることができません。
声を出してこそ戻って来ることができるのです。
「さて我が耳に聞こゆる程申し候うは、高声の念仏の中にて候うなり」
「さて、自分の耳に聞こえるほどの声で申す念仏は高声の念仏の内に入ります」
どの程度の声で称えればよいかというと、「我が耳に聞こえるほど」でじゅうぶんなのですということです。
みんなで称える時は大きな声で称えた方がよいでしょう。
その方がお互いの励みになります。しかし一人で称える時は、我が耳に聞こえるほどでじゅうぶんなのです。
これが日常的なお念仏です。「なむあみだぶ」と口ずさみつつ日常生活を送るのです。
しかし電車の中などでは、我が耳に聞こえるほどでも抵抗があるでしょう。
そんなとき、私は「舌が動く程度」に称えています。
隣の人は気づきません。
でも称えています。
心に思っているだけではありません。
必ず舌が動いています。
これは重要です。
舌が動いていないとやはり乱れます。
舌が動いていると、大きな声で称えている時と同じように、心が乱れてもまた「乱れていたな」と気づきます。
舌が動いていなければ、それさえも気づかないままになってしまいます。
声を出すこと自体が重要なことです。
嫌いな人のことをずっと「嫌いだ、嫌いだ」と言い続けると益々嫌いになります。
大嫌いな人のことも「好きだ、好きだ」と言っていると、少しはましになってくるようです。
少しぐらい嫌いな人なら「好きだ、好きだ」と言っている内に好きになるかも知れません。
夫婦でお互いの愚痴や悪口を他人に言っていると、憎しみ合うようになるといいます。
色々不満はあっても「好きだ、好きだ」と言っていれば、それなりに心が通じ合うとも言えるかも知れません。
ですから、常に「南無阿弥陀仏」と称えていれば、心はあっちに行ったりこっちに行ったりどうしようもない私ですが、また戻って来ることができます。
お念仏に引っ張られるのです。
声がリードして心がついて行くのです。
声を出すことが大切です。
前篇第二十六章 光明摂取
(本文)
観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)に曰(いわ)く、一々の光明(こうみょう)遍(あまね)く十方(じっぽう)の世界を照らして、念仏の衆生を摂取(せっしゅ)して捨て給わず。これは光明ただ念仏の衆生を照らして、余の一切の行人(ぎょうにん)をば照らさずというなり。但し余の行(ぎょう)をしても極楽を願わば仏光照らして摂取(せっしゅ)し給うべし。いかがただ念仏の者ばかりを選びて照らし給えるや。善導和尚釈して曰く、弥陀の身色(しんじき)は金山(こんせん)の如し、相好(そうごう)の光明十方(じっぽう)を照らす、ただ念仏の者のみありて光摂(こうしょう)を蒙(こうむ)る、正に知るべし本願最も強きを。念仏はこれ弥陀の本願の行(ぎょう)なるが故に、成仏の光明返りて本地(ほんじ)の誓(願を照らし給うなり。余行(よぎょう)はこれ本願にあらざるが故に、弥陀の光明嫌いて照らし給わざるなり。今極楽を求めん人は本願の念仏を行(ぎょう)じて、摂取(せっしゅ)の光に照らされんと思(おぼ)し召(め)すべし。これにつけても念仏大切に候。よくよく申させ給うべし。
(現代語訳)
『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』には、「阿弥陀仏の一つ一つの光明は、遍く十方の世界を照らし、念仏を称える衆生を救い取って、捨てることがない」とあります。これは、光明が念仏を称える衆生だけを照らして、他の一切の行者を照らさないということです。
ただし、他の行を修めても極楽を願うならば、仏の光が照らして救済されてもよいはずです。どうして、ただ念仏する者だけを選んで、照らされるのでしょうか。
善導和尚は解釈して言われます。「阿弥陀仏の身体の色は黄金の山のようである。(一つ一つの)相好から放たれる光明はあらゆる方角の世界を照らす。ただ念仏を称える者だけが光明の救いをいただく。(阿弥陀仏の)本願のはたらきが最も強力だと理解すべきである」と。
念仏は阿弥陀仏の本願の行であるので、成仏された後の光明が、ひるがえって、成仏される以前の念仏往生の誓願を照らされるのです。他の行は本願ではないので、阿弥陀仏の光明は(これを)選び捨てて照らされないのです。
今、極楽を求める人は、本願の念仏を修めて、救いの光に照らされようとお思いになってください。このことからしても念仏は大切です。よくよくお称えになってください。
(『法然上人のお言葉』総本山知恩院布教師会刊)
(解説)
阿弥陀さまが「救ってやろう、救ってやろう」と願ってくださるみ心を「お慈悲」と申します。
そのお慈悲はよく光に譬えられます。
「光明」などといいます。
浄土宗の阿弥陀仏像は、後ろに舟形の光背が施されています。
この光背はお慈悲を表します。
罪の重い者は重い石を背負っているようなものだから、自分では向こう岸、つまり極楽になど行けないわけです。
しかし、阿弥陀さまの大きな慈悲の船に乗れば、どんな重い罪を背負った者でも必ず向こう岸、極楽浄土へと届けてくださるというのです。
舟形の光背はそのことを表します。
浄土真宗の阿弥陀仏像には光が四方八方に放たれていることを表す光背になっています。この浄土真宗の光背は光明を表します。
光明ですから、こちらもお慈悲を表現しているのです。
阿弥陀さまのお慈悲の光は常にあらゆるところを照らしてくださっているということです。
阿弥陀さまはいつもお慈悲の光を放って、「救ってやろう」と願ってくださっています。その中で「南無阿弥陀仏」と念仏を称える者を極楽へ迎え取ってくださるのです。
しかしこういう反論があるかも知れません。
「救ってやりたいと願うならば、念仏を称えようが称えまいが救ってやればいいじゃないか。なぜ念仏を称える者だけというような心の狭いことを言うのか」と。
仏教では因果の法則を説きます。
原因があって結果がある。
それも「自業自得」というように、自分がした行いが自分に返ってくるのです。
だから何もしない者には何も返ってはきません。
何もしない者を救うことは阿弥陀さまにもできません。
本当はそれぞれが善い行いを続ければよいのです。
そして難しい修行をして、功徳を積めばよいのです。
功徳を積んで覚りを開けばいいわけです。
しかしそれができない者ばかりだと阿弥陀さまは思われたのです。
「煩悩による行いばかりを繰り返す者は自業自得の道理によって、地獄や餓鬼に墜ちるしかないではないか。どうすればよいか。難しいことをせよと言っても無理であろう。でも私の名前ぐらいなら呼べるであろう。そうだ、私の名前に私が行った功徳を収め込んでやろう。そうすれば因果の道理を崩すことなく救うことができるぞ」
そして「我が名を称える者を極楽へ迎え取ってやろう」という「本願」を建ててくださったのです。
「南無阿弥陀仏と称える」という「因」を起こせば、本願によって「極楽へ往生する」という「果」が出るのです。
だから南無阿弥陀仏のお念仏は極楽へ往生するための専門の行です。
「往生行」といいます。方や座禅や瞑想、護摩を焚くなどの修行、殆どの修行は極楽へ往くための行ではありません。
これらの修行はこの世で覚りを開こうという修行です。
ですから目的が違うのです。
極楽へ往きたいならばお念仏でなくてはなりません。
この世で覚りを開こうというのなら、他の修行でなくてはなりません。
それぞれの行にはそれぞれの目的があります。
そういうことがこのご法語には説かれています。
「観無量寿経にいわく、一々の光明、遍く十方の世界を照らして念仏の衆生を摂取して捨て給わず」
観無量寿経とは浄土宗が大切にする三つのお経、浄土三部経の一つです。そこに記されている一文です。
日常勤行の中の摂益文です。
「光明遍照 十方世界念仏衆生 摂取不捨」です。
阿弥陀さまのお慈悲の光はあらゆるところを照らしてくださって、その中で念仏称える者を救いとって決して捨てられることがないという文です。
「これは光明ただ念仏の衆生を照らして余の一切の行人をば照らさずというなり」
これは阿弥陀さまのお慈悲の光は念仏称える者だけを照らして他の修行者を照らさないということです。
「但し余の行をしても、極楽を願わば、仏光照らして摂取し給うべし。いかが、ただ念仏の者ばかりを選びて照らし給えるや」
ただし他の行をしても極楽を願えばいいじゃないか、なぜ念仏の者だけが救われるんだ、という意味なのですが、不思議な文章です。
「どっちなんだ?」と言いたくなります。
私は以前からこの文章がよく分かりませんでした。
色んな方が訳されたものを見比べても、みんな悩んでおられたようで、バラバラです。
しかし数年前に仏教大学の先生に教えていただきました。
法然上人のご法語にはいくつかの種類があり、伝承によって同じものでも多少文章が異なるものがあります。
このご法語にも他の伝承があり、そこには「但し」の前に「世の人曰く」という言葉がありました。
これですっきりしました。
つまりこういうことです。
阿弥陀さまは念仏称える者だけを救いとってくださるのだけれど、世間では念仏以外の修行をしていても極楽に行きたいと願えば救ってくださるというではないか。
なぜ念仏者だけを選んで照らすというのか、ということです。
実は法然上人が浄土宗を開かれるまではどうすれば極楽へ往生できるのかがはっきりと示されていませんでした。
極楽へ往生したいと願っていればどんな修行をしていても救われると思っている人もいたんです。
しかし法然上人はお経の中に根拠を見つけられたのです。
本願です。
南無阿弥陀仏と称える者こそが往生できる。
ちゃんとお経に書いてあるではないか、ということです。
その問いに善導大師のお言葉を引用されて答えておられます。
「善導和尚釈して曰く、弥陀の身色は金山の如し、相好の光明十方を照らす。唯念仏の者のみありて光摂を蒙る。当に知るべし。本願最も強きを」
これは善導大師の『往生礼讃』の中の「三尊礼」にある一節です。
「善導大師が解釈しておっしゃるには、阿弥陀さまの体は金の山のようなものだ。お姿から光が十方を照らしてくださっている。ただ念仏を称える者だけが光を受けることができる。よく心得よ。本願は最も強いのである」ということです。
念仏を称える者が阿弥陀さまによって極楽へ迎え取っていただけるのは、阿弥陀さまの本願だからです。
念仏は阿弥陀さまのお名前を呼んでいるわけですが、本願がなければただ名前を呼んでいるというだけになります。
南無釈迦牟尼仏、南無観世音菩薩、南無大師遍照金剛など仏様や菩薩様、祖師様のお名前を呼ぶ、という行は色々あります。
でもそれは仏菩薩、祖師方を敬っているという意味であって、それだけで救われるというものではありません。
南無阿弥陀仏は阿弥陀さまご自身が、称えれば救うと約束してくださっているのですから、他のものとは全く異なるのです。
「念仏はこれ弥陀の本願の行なるがゆえに、成仏の光明かえりて本地の誓願を照らし給うなり」
「念仏は阿弥陀さまの本願の行であるから、仏となられた阿弥陀さまが照らす光は返って、昔阿弥陀さまが建てた本願を信じて念仏を称える者を照らしてくださるのである」
「余行はこれ本願にあらざるがゆえに、弥陀の光明嫌いて照らし給わざるなり」
「念仏以外の行は本願ではないから、本願ではないから阿弥陀さまは避けて照らされることがないのである」
「今極楽を求めん人は、本願の念仏を行じて、摂取の光に照らされんと思し召すべし」
「今極楽往生を願う者は、阿弥陀さまの本願である念仏を行じて、救いの光に照らされたいと思うべきである」
「これにつけても念仏大切に候。よくよく申させ給うべし」
「これにつけても念仏は大切です。しっかりお称えしなさいよ」
阪急電車に乗るのに「JRの切符が1万円分あるから乗せろ!」と言っても乗ることはできません。
阪急電車に乗ろうとすれば阪急電車の切符を買わなくてはいけません。
いくら1万円分だと言ってもだめです。
それと同じように、極楽へ往生したいならば南無阿弥陀仏のお念仏なのです。
もちろん他の行もお釈迦様が説かれたものですから、大きな功徳はあります。
でも往生することはできません。
「往生したいならば何を為すべきか」なのです。
前篇第二十五章 導師嘆徳
(本文)
しずかにおもんみれば、善導(ぜんどう)の観経の疏(かんぎょうのしょ)は、是(こ)れ西方(さいほう)の指南(しなん)、行者(ぎょうじゃ)の目足(もくそく)なり。しかれば則(すなわ)ち、西方(さいほう)の行人(ぎょうにん)必ずすべからく珍敬(ちんぎょう)すべし。就中(なかんずく)毎夜の夢の中(うち)に僧ありて玄義(げんぎ)を指授(しじゅ)せり。僧というは、恐らくはこれ弥陀(みだ)の応現(おうげん)なり。しからば言うべし、この疏(しょ)は弥陀(みだ)の伝説(でんぜつ)なりと。いかに況(いわ)んや、大唐(だいとう)に相伝(そうでん)して曰(いわ)く、善導(ぜんどう)はこれ弥陀(みだ)の化身(けしん)なりと。然(しか)らば言うべし、この文(もん)はこれ弥陀(みだ)の直説(じきせつ)なりと。すでにうつさんと思わん者は、専(もは)ら経法(きょうぼう)の如くせよと言えり。此の言葉、誠なるかな。仰(あお)ぎて本地(ほんじ)を尋ぬれば、四十八願の法王なり。十劫(じっこう)正覚(しょうがく)のとなえ、念仏にたのみあり。伏(ふ)して垂迹(すいじゃく)をとぶらえば、専修(せんじゅ)念仏の導師(どうし)なり。三昧(さんまい)正受(しょうじゅ)の言葉、往生に疑いなし。本迹(ほんじゃく)異なりといえども、化導(けどう)これ一(いつ)なり。ここに貧道(ひんどう)、昔此(こ)の典を披閲(ひえつ)してほぼ素意(そい)を覚れり。立ち所に余行を止(とど)めてここに念仏に帰す。それよりこの方(かた)今日(こんにち)に至るまで、自行(じぎょう)、化他(けた)ただ念仏を事とす。然(しか)る間、稀に津(しん)を問う者には示すに西方(さいほう)の通津(つうしん)を以(も)てし、たまたま行(ぎょう)を尋ぬる者には、教うるに念仏の別行(べつぎょう)を以(も)てす。これを信ずる者は多く、信ぜざる者は少なし。念仏を事(こと)とし、往生を冀(こいねが)わん人、あに此の書をゆるがせにすべけんや。
(現代語訳)
しずかに思いめぐらしますと、善導大師の『観経疏』は西方極楽への指針であり、念仏者の眼であり足であります。それゆえ西方を願う行者は、必ず尊び敬わなければなりません。
特に、毎夜の夢の中に僧侶が現れて、〔『観無量寿経』の〕奥深い教えを〔善導大師に〕教授したのです。僧侶というのは、おそらく阿弥陀仏の仮の姿でありましょう。それならば言うべきです。「この『観経疏』は阿弥陀仏から説き伝えられたものである」と。ましてや、偉大なる唐の国では、「善導大師は阿弥陀仏の生まれ変わりである」と伝えられています。それならば言うべきです。「この〔書の〕文言は阿弥陀仏の直説である」と。現に〔大師が自ら〕「書写しようと思う者は、専ら経典のように扱いなさい」と言っておられます。この言葉はまことにもっともです。
仰いで本の姿をたどれば、四十八願を〔立てられた〕法王(阿弥陀仏)であります。〔阿弥陀仏が〕十劫の昔に覚りを示されたことは、念仏が頼みとするに足る証拠です。ひれ伏して仮の姿をたどれば、専修念仏の導師(善導大師)であります。「三昧を体得した」というそのお言葉は、念仏往生に疑いがないとの証明です。本の姿と仮の姿との違いがあっても、教導される内容は一致しています。
そこで私法然は、以前にこの『観経疏』をよく読んで、ほぼ本旨を理解し、すぐさま他の修行をやめて、念仏に帰依しました。そのとき以来、今日に至るまで、自分の行も他者への教化も、ただ念仏のみに専念してきました。その間、まれに覚りへの渡し場を尋ねる者には、念仏という特別の行を教え諭しました。これを信じる者は多く、信じない者は少ないのです。〈以上、『選択集』より〉
念仏を専らにし、往生を求め願う人は、どうしてこの書物(『選択集』)をおろそかにできるでしょうか。できはしないのです。
(解説)
この御法語は、善導大師について法然上人が語られているところです。
浄土宗のお仏壇で、向かって右側にお祀りされているのが善導大師です。
法然上人は向かって左側です。
善導大師の方が上座にお祀りされているのです。
善導大師は中国の唐の時代に浄土宗のみ教えを完成された方です。
法然上人は、善導大師のみ教えによって浄土宗をたてたとおっしゃっています。
法然上人は比叡山で学ばれる中で、ご自分自身が救われるみ教えを探し求められました。智慧第一の法然房と言われた法然上人でしたが、比叡山の仏教の中にはご自分自身が救われる教えを見つけ出すことができませんでした。
15才で比叡山にお登りになり、43才まで28年間救われるみ教えを探し求めつづけられたのです。一口に28年間といっても、それは相当長い時間です。
1年2年探すだけでも大変です。
それを28年ですから、並大抵のことではありません。
「お釈迦さまが説かれたみ教えなのだから、どこかに必ず私が救われる教えがあるに違いない、ないはずがない!」という確信があったのでしょう。
そうでなかったら挫けていたに違いありません。
必ずあるという確信の元、五千巻余りの膨大な数のお経を何度も何度も読み返されたのです。
そしてとうとう善導大師の『観経疏(かんぎょうしょ)』という書物と出会われました。
その中に「南無阿弥陀佛と称える者はすべて救われる、なぜならそれは阿弥陀さまの本願だからなんだ」という一文を見つけられたのです。
今の私たちにとりましては南無阿弥陀佛と称える者が極楽浄土へ必ず往生するということは、耳にたこができるほど聞かされた、当たり前のことかもしれません。
しかし法然上人以前はそうではなかったのです。
その一文を見つけて、法然上人は涙を流して喜ばれたといいます。
善導大師は法然上人より500年ほど昔の方です。時代も国も違いますから、当然歴史的に対面されることはありませんでした。
しかし夢の中では何度もお会いになっていたといいます。
この夢のご対面につきましては、お伝記の中のお話しが有名です。
法然上人はあるとき夢をご覧になっていました。
夢の中で法然上人は山の中腹に立っておられました。
そこから遠くを眺めていると、美しい紫の雲があちらへ行ったりこちらへ行ったり飛び回っています。
その雲の中から美しいクジャクやオウムが飛び立っては下の河原で遊び、また雲に吸い込まれていきます。
「何とも美しくも不思議な光景だなあ」と法然上人が思っておられましたところ、その雲が法然上人の元に近づいてきて広がっていったのです。
辺り一面紫の雲に覆われました。
するとスーッと一人のお坊さんが現れました。
法然上人は驚いて「あなたはどなたさまですか?」と尋ねました。
するとそのお坊さんは「私は唐の善導です」とお答えになりました。
法然上人が「なぜ私のような者の前にお姿をお見せくださったのですか?」と尋ねますと、「それはあなたがお念仏のみ教えを広めることが尊いから私はあなたの元へ来たのです」と善導大師がお答えになり、夢から覚めたといいます。
その時の善導大師のお姿が、お仏壇のお姿です。
上半身は墨染め、下半身は金色です。
お体の真ん中ではっきりと色が変わっていますね?
このようなお姿を「半金色(はんこんじき)の善導大師」といいます。
金色は仏を表します。墨染めは凡夫を表します。
善導大師は唐の時代に長安の都で活躍されているときからすでに「善導大師は阿弥陀さまの化身だ、善導は弥陀の化身なり」と言われていました。
法然上人はそのことをよくご存知で、法然上人も善導大師を正しく阿弥陀さまの化身と崇めておられました。
善導大師は阿弥陀さまがこの世に姿を変えて現れてくださったのだ、だから善導大師がおっしゃることは阿弥陀さまがおっしゃることと同じなんだ、善導大師が書かれた書物は阿弥陀さまが説かれたのと同然なんだ、と理解されていました。
ですから半金色の善導大師像は、阿弥陀さまを表す金色と、人間善導に姿を変えておられたことを表す墨染めになっているのです。
私は何度か善導大師のご遺跡をたずねて中国へ行きましたが、中国にある善導大師のお像はもちろん半金色ではありません。
私たちは法然上人を通して善導大師を崇めますから、半金色の善導大師像は日本の浄土宗独特のものです。
日本全国何処へ行っても殆どの浄土宗寺院には半金色の善導大師像がお祀りされていますし、お檀家さんのお家のお仏壇には半金色の善導大師像がお祀りされています。
さて、本文を訳して参ります。
「心を落ち着けて考えてみるに、善導大師の『観経の疏』は西方極楽浄土への道しるべとなる書であり、念仏者には大切なものである。から西方極楽浄土へ生まれたいと念仏を称える者は必ずこの『観経の疏』を大切にしなくてはならない」
「とりわけ『観経の疏』には「毎晩の夢に僧侶が出てきて深い教えを伝えて下さった。おそらくその僧侶は阿弥陀様が姿を変えて夢に現れて下さったのだろう。そうであるなら、この『観経の疏』は阿弥陀さまが善導大師に伝えたものであろう。ましてや中国では善導大師は阿弥陀さまの生まれ変わりだと伝えられている。それならば、この『観経疏』は阿弥陀さまが自ら説いて下さった教えそのものだと。善導大師ご自身が「この観経の疏書き写そうと思う者はお釈迦様が説かれたお経と同じように扱うように」と書かれている。本当にその通りである」
「あおいで善導大師の本当のお姿を問えば、四十八願を建ててくださった阿弥陀さまである。はるか十劫の昔に建てられた願は念仏を称えることである。ひれ伏して阿弥陀仏がこの世に現れて下さったお姿を尋ねるならば、ひたすら念仏を称えるように導いて下さった善導大師である。三昧に達した方の言葉であるから極楽往生に疑いはない。元は阿弥陀さま、現れている姿は善導大師と違いはあっても、導いて下さる教えはただ一つである」
三昧というのは、いつでも極楽を見たいと思えば極楽を見ることができ、阿弥陀さまと遇いたいと思えば阿弥陀さまと会うことができるという、瞑想の境地です。
そのような境地に至る人は今となっては皆無ですが、善導大師はその三昧の境地に達しておられました。
よく「極楽って言っても見てきた人はいない」とか、「阿弥陀さまに会ってきた人はいない」などと言いますが、三昧の境地に達してらっしゃる方は何度も極楽を見、阿弥陀さまにお会いされているのです。
その三昧の境地に達しておられる善導大師がおっしゃるのだから、念仏で極楽へ往生することは疑いのないことだというのです。
「私はかつてこの『観経疏』を見て、念仏の教えを理解した。それ以来今までやってきた色んな修行を止め、念仏の信仰に入った。あれから今に至るまで、自分の行も人に勧めるものも念佛だけにしたのである。そのような中、救いを求めてくる人がいたら西方極楽浄土への往生を願うことを説き、そのためにはどんな行をすればよいのか尋ねる人があれば、念仏の行を教えた。これを信じる人は多く、信じない人は少ない。念仏に心を傾け、極楽往生を願う人は、どうしてこの選択本願念仏集をおろそかにできようか」
この御法語二十五章は『選択本願念仏集』について書かれたお伝記を抜粋したもので、『選択本願念仏集』にはこの『観経疏』について書かれています。
そういう大切なことが書かれているのだから、この『選択本願念仏集』を大切にせよと書かれているのです。
前篇第二十四章 別時念仏
(本文)
時々別時(べつじ)の念仏を修(しゅ)して、心をも身をも励まし調え進むべきなり。日々に六万遍七万遍を称えば、さても足りぬべきことにてあれども、人の心ざまは、いたく目慣れ耳慣れぬれば、いらいらと進む心少なく、明け暮れはそうそうとして、心閑(しず)かならぬようにてのみ、疎略(そりゃく)になりゆくなり。その心を進めんがためには、時々別時(べつじ)の念仏を修(しゅ)すべきなり。しかれば善導和尚(ぜんどうかしょう)も、懇(ねんご)ろに励まし、恵心(えしん)の先徳(せんとく)も詳しく教えられたり。道場をもひきつくろい花香(けこう)をも供え奉らんこと、ただ力の堪えたらんに随うべし。また我が身をも殊に清めて道場に入りて、或いは三時、或いは六時なんどに念仏すべし。もし同行など、数多(あまた)あらん時は、代る代わる入(い)りて、不断念仏にも修(しゅ)すべし。かようのことは、各々ように随いて、計らうべし。
(現代語訳)
時おり別時念仏を修めて、心身ともに奪い起こし、調え、誘うべきです。
毎日六万遍七万遍を称えるならば、それで充分でありましょうが、人の心のあり方は、たいそう見慣れ、聞き慣れてしまうと、せわしく、誘う心が少なく、毎日が忙しく、ただただ心が落ち着かないありさまとなって、念仏がおろそかになっていくものです。
そうした心を誘うためには、時おり別時念仏を修めるべきです。それゆえ善導和尚も心を込めて奨励され、徳ある先人、恵心僧都(えしんそうず)も詳しく教授されました。
道場を立派に整え、花や香をお供えすることは、ただ力の及ぶ範囲で結構です。また、自分の身体も、特に清潔にして道場に入り、ある場合には六時間、ある場合には十二時間というように念仏すべきです。もしも同行者などが多くある時には、交替で(道場に)入り、不断念仏としても修めるのがよいでしょう。こうしたことは、それぞれの事情に応じて取り計らうことです。
(解説)
浄土宗のお念仏は、「いつでもどこでもどんな時でも」できるという大きな特長があります。
他にいつでもどこでもどんな時でもすることができる仏道修行は殆どありません。
そして「南無阿弥陀仏」と称えるだけですから、非常に簡単です。
しかしそんな簡単なお念仏を、最初は「有り難い」と思って始めたのに、いつの間にかその有り難さを忘れて惰性になってしまうのです。
普通なら、一旦止めて休憩し、またちょっとずつやればよいということになるのかも知れません。
しかしお念仏は、一旦休憩してしまうとそのまま止まってしまうのです。
ではどうすればよいのでしょうか。
法然上人は、「時と場所を定めて集中的に、たっぷりとお念仏をしましょう」とおっしゃいます。
この「時と場所を定めて集中的にするお念仏」を別時(べつじ)といいます。
今日のご法語はその別時についてのお話しです。
「時々別時の念仏を修して、心をも身をも励まし調え進むべきなり」
「時々別時の念仏を行って、心も体も励ましていくべきですよ」
「日々に六万遍七万遍を唱えばさても足りぬべきことにてあれども、人の心ざまはいたく目慣れ耳慣れぬれば、いらいらと進む心少なく明け暮れは忽忽として心閑かならぬようにてのみ、疎略になりゆくなり。」
「毎日六万遍七万遍を唱えていたら、それで十分なようであるけれども、人の心は目も耳も非常に慣れやすいもので、段々と励んでいく心がなくなってきて、朝夕は慌ただしく心が乱れてきて念仏が雑になってくる」
「その心をすすめんためには時々別時の念仏を修すべきなり」
「そんな心を励ますためには時々別時の念仏を行うべきである」
「しかれば善導和尚もねんごろに励まし、恵心の先徳もくわしく教えられたり」
「そうであるから浄土宗の高祖である善導大師も別時念仏をするよう励まして下さっているし、比叡山の念仏の先駆者である恵心僧都源信和尚も詳しく別時念仏の作法を教えて下さっている」
「道場をもひきつくろい、花香をも供えたてまつらんこと、ただ力の堪えたらんに従うべし」
「道場もしっかりと調え、花やお香も供える。それは自分の分相応にすればよいですよ」
いつもと一緒のしつらえでしたら、心もいつもと変わりなくなってしまいます。別時は怠けてしまった心を励ますものですから、いつもと違う、いつもより厳かにする必要があります。ただ、それは贅沢にせよという意味ではなく、自分の身の丈に合ったものをすればよいのだということです。
「また我が身をも殊に清めて道場に入りて、或いは三時、或いは六時なんどに念仏すべし」
「また自分の体も特に清めて道場に入って、時には三時、時には六時に念仏するがよい」
普段のお念仏は、体が清かろうが汚れていようが、その身そのままで称えればよいのですが、別時の時は普段と違うということを意識するためにわざわざ沐浴清浄して道場に入るのです。
三時というのは半日十二時間を三つに分けてお勤めするという法要があります。
六時というのは一日二十四時間を六つに分けてお勤めするという法要です。
夕方4時、夜8時、夜中12時、未明4時、朝8時、昼12時の6回です。
それぞれの時間に合わせてお念仏を称えるのです。
「もし同行など数多あらん時は、代わる代わる入りて不断念仏にも修すべし。かようのことは各々ように随いて計らうべし」
「もし一緒にやろうという人がたくさんいるならば、交代交代に道場に入ってお念仏が絶えないように、不断念仏を行うのである。このようなことはそれぞれの環境や縁に随って行うのです」
浄土宗の大本山、百万遍知恩寺では毎年一月二十四日のお昼から二十五日のお昼まで、二十四時間の別時を行っています。
一月二十五日が法然上人の祥月命日ですのでそれに合わせてのお念仏をしています。
二十四時間のお念仏といっても、ずっと二十四時間お念仏し続けているわけではありません。
三時間ほどお念仏を称えては三十分ほど休憩してはまた道場に入るということを繰り返すのです。
それぞれが自分のペースでお念仏を称えては休憩するのです。
大勢いますので、道場では常にお念仏の声が絶えないということになります。
そういうものを不断念仏(ふだんねんぶつ)といいます。
法輪寺でも春と秋の年に二回、念仏会というものを行っています。
※残念ながら新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、令和2年、3年春現在は休止しています。
昼の二時から夜の十時までの八時間のお念仏です。
私たちはずっとお念仏を称えていますが、お参りに来られる方は好きな時間に来て、それぞれの都合がよい時間までお念仏をされてお帰りになります。
これも不断念仏であり、別時念仏です。
百萬遍の不断念仏にしても法輪寺の念仏会にしても、参加したらありがたいことがよくわかります。
特に夜です。
昼間は人の出入りが気になったりしますが、夜は周りが見えませんから、阿弥陀さまと向かい合わせになります。
阿弥陀さまと私の二人だけの世界になります。
それぞれが日頃生活する中で、悩みや苦しみを抱えています。そんな中、別時を行って阿弥陀さまと向かい合わせになると堪りません。
「ああ、阿弥陀さまはいつもいつも見守って下さっているんだなあ」とか「なんて情けない自分なんだろう」いう思いが込み上げてきて、阿弥陀さまの有り難さを再確認します。そうすると日頃のお念仏もまたやる気になってくるのです。
この有り難さはやってみなければわかりません。
やればすぐにわかります。
プロ野球の選手は毎日野球をしています。
昼間練習をして、夜試合をしているわけです。
それだけ野球をしているのに、シーズン前には必ずキャンプに行きます。
阪神タイガースなら、普段練習しているところは鳴尾浜や甲子園のグラウンドです。
そこで練習すればいいのに、わざわざシーズンオフには沖縄に行き、その後高知でキャンプします。
わざわざ場所を変えて二十四時間野球漬けにするわけです。
そうすることによって、普段では気づかなかった自分の弱点や課題が見つかって、あるいは弱点を克服してまた普段の練習に戻るわけです。
場所を変えて集中的に、更に野球をすることによって技術だけでなく心も励ますのです。
別時もそれと同様です。
普段からお念仏しているのに、わざわざ集中的にお念仏を行うことによって、更にお念仏を続けていく力になっていくのです。
別時は、お念仏を続けていくためにとても大切なことです。
前篇第二十三章一枚起請文②
一枚起請文は、どの一文をとっても大切なものばかりですが、この一文はその中でも一際大切な一文です。
「念仏を信ぜん人はたとい一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智の輩に同じうして、智者の振る舞いをせずしてただ一向に念仏すべし」
「念仏を信ぜん人」といいますのは、「信じる人は」ということです。
現代語の感覚ですと、なんとなく「信じない人」と理解しそうですが、そうではありません。
古語辞典で「ん」と引いてみると、否定の意味は一つもありません。
推量や婉曲などいくつかの意味がありますが、この場合は意志をあらわす助動詞です。
正確に訳すと「信じようという人は」となります。
ザッと訳しますと、「念仏を信じようという人は、たとえお釈迦さまが一生涯かけて説かれた釈迦一代の法を学び尽くしたとしても、阿弥陀さまからご覧になったらお経の一文知らない愚かな身と何ら変わりないのだから、学問をしていないが一生懸命阿弥陀さまにすがってお念仏を称える尼入道さん達と同じように、智者の振る舞いをせずにただひたすらお念仏を称えなさい」となります。
尼入道という言葉は現在ありませんので、解説いたします。
尼入道とは、当時戦で夫を亡くした女性が集まって相互扶助をし、夫の菩提を弔うために、自分自身の往生のためにひたすらお念仏を称えていた聖集団です。
完全に頭を剃り落とすのではなしに、途中まで剃り上げるという変わった髪型をしていたそうです。
今で言うおかっぱのような髪型と思われます。
この方々は正式な僧侶ではありません。で
すから仏教の学問などは全くしていないのです。
しかしひたすら阿弥陀さまにすがってお念仏を称えていたわけです。
極楽へ往生するためには学問は必要ありません。
どれだけ学問を重ねても悟りや往生には一歩も近づきません。
人間同士で勝ったとか負けたと比べているだけのことで、全く往生の役には立ちません。釈迦一代の法は膨大な教えですから、学び尽くすなど到底できませんが、たとえ学び尽くしたとしても、阿弥陀さまがご覧になればお経の一文知らない人と全く変わりがないのです。
だから、尼入道さん達をご覧なさいよというわけです。
彼女たちはお経なんて全く知らないけれど阿弥陀さまにすがってひたすらお念仏を称えているじゃないか、あの人達を見習いなさいとおっしゃるのです。
たまに、この一枚起請文は尼入道などの女性を差別しているのでは?という方がおられます。
なぜそうおっしゃるのかよく聞いてみますと、やはり「念仏を信ぜん人は」を「信じない人は」と訳しておられるようです。
「信じない人は」と訳すと後の意味が支離滅裂になるのですが、無理矢理意味を掴もうとすると、恐らくこのようになります。
「念仏を信じない人はたとえ釈迦一代の法を学び尽くしても愚かなままでしかない。
無智な尼入道達と同じようなものだ。
だから智者の振る舞いをせずにひたすらお念仏を称えなさい」という具合でしょうか。
これでは尼入道を差別したように聞こえます。
意味が全く変わってしまいますので、「信ぜん人」の訳し方にご注意ください。
智者の振る舞いというのは、疑いの心です。
ここでは仏教の学問について書かれていますが、考えてみますと一般に知識や経験があればあるほど信心が深くなるのかというと、決してそうは言えません。
逆に知識や経験があると「科学的に見たら極楽なんてあるはずがない」とか、「阿弥陀さまなんて信じるのは荒唐無稽だ」などと言うことになることが多いのです。
高々数十年の経験や、中途半端な科学によって目が曇ってしまいます。
学問も究めた人は「どれだけ学んでもおぼつかない」と愚かさを自覚するといいます。
湯川秀樹博士などはそうおっしゃっています。
しかし中途半端な者は自分が偉くなったように勘違いします。
どれだけの学問知識を積んでいようと経験を積んでいようと極楽へ往くためには一切関係ありません。
もちろん生活する上では知識や経験も必要でしょう。
しかし往生には役に立たないのです。
ですから、知識・経験という重い鎧を一旦脱いでみるのです。
どれだけ分厚い鎧をつけていても、阿弥陀さまの前に立てば鎧など着けていないのと何の変わりもありません。
ただ阿弥陀さまにすがる以外に方法はないと自覚して、智者の振る舞いをせずにひたすらお念仏を称えるのです。
「証のために両手印を以てす」
「私が書いた証しに両手型を押しておきましょう」
「浄土宗の安心起行この一紙に至極せり」
「浄土宗の教えをこの一枚の紙に書き尽くしました」
「源空が所存この外に全く別義を存ぜず」
源空とは法然上人です。法然房源空とおっしゃいます。
「私源空が知っているところはこの外に何もありません」
「滅後の邪義を防がんがために所存をしるしおわんぬ」
「私が死んだ後、間違った理解が出ることを防ぐためにこのように記しておきます」
実際法然上人のご生前から邪義が横行しました。
「念仏さえ称えていればどれだけ悪いことをしても構わないんだ」とか、「念仏以外の宗派の教えでは誰も救われないんだ」などと法然上人がおっしゃっていないことを、あたかもおっしゃったかのように言いふらし、あちこちで顰蹙を買いました。
その煽りを食らって法然上人は晩年讃岐へ島流しに遭っておられます。
配流からようやく都へ帰ってきましたが、体調を崩し建暦二年の一月二十五日にお亡くなりになりました。
ですから最後まで邪義を心配されたのです。
以上が一枚起請文です。
浄土宗で最も大切にする御法語です。
毎日拝読しましょう。