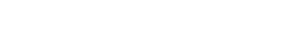前篇第十四章 専修念仏
(原文)
本願の念仏には独り立ちをせさせて助をささぬなり。助というは、知恵をも助にさし、持戒をも助にさし、道心をも助にさし、慈悲をも助にさすなり。善人は善人ながら念仏し、悪人は悪人ながら念仏して、ただ生まれつきのままにて念仏する人を、念仏に助ささぬとはいうなり。さりながら、悪を改め善人となりて念仏せん人は、仏の御心に叶うべし。叶わぬもの故に、とあらんかからんと思いて決定心起こらぬ人は、往生不定の人なるべし。
(現代語訳)
本願の念仏には独立をさせて、助けを差しはさみません。「助け」というのは、智慧をも助けとし、持戒をも助けとし、菩提心をも助けとし、慈悲をも助けとして差しはさむのです。
善人は善人のままで念仏し、悪人は悪人のままで念仏して、ただ生まれつきのままに念仏する人を、「念仏に助けを差しはさまない人」と言うのです。
しかしながら、悪を悔い改め、善人となって念仏する人は、阿弥陀仏の御心に適うでしょう。
(ただし)仏の御心に適わない自分であることから、「ああだろう、こうだろう」と心配して、「必ず往生できる」という思いの起こらない人は、往生の確実でない人なのです。
(解説)
法然上人は色々なお言葉を残されていますが、その中でもしょっちゅう仰っていたお言葉というものがあります。「常に仰せられけるお言葉」と呼ばれるもので、この御法語もその一つです。
まず全体的に申し上げますと、念仏というのはあまりに簡単ですので、何となく頼りなく思われるようです。念仏だけでは物足りないから般若心経も称えた方が功徳があるような気がするのです。しかし念仏は阿弥陀さまがご修行くださったすべての功徳を収め込んでくださった、極楽へ往生するためにはこの上ない行です。私たちが私たちの力で極楽へ往生するのではありません。私たちは極楽浄土への往生を願い、阿弥陀さまがご用意くださったお念仏を称えるだけです。阿弥陀さまのお力によって救われるのです。この阿弥陀さまのお力を他力といいます。いわゆる「他人まかせ」の他力ではありません。本来他力とは、阿弥陀さまのお力を限定していうものです。自分の力ではとても極楽へ往生することなど覚束ない私たちが念仏を称え、阿弥陀さまの力によって初めて往生するのです。どんなに罪深い身でも阿弥陀さまは必ず救って下さいます。そのことを踏まえ、本文を見ていきましょう。
「本願の念仏にはひとりだちをせさせて助をささぬなり。」
「阿弥陀さまの本願であるお念仏は、ひとりだちをしたものであって、補助が必要なものではないのだ。」
ここで助とは何かを具体的に挙げています。
知恵、持戒、道心、慈悲の四つです。私たちは知恵がある人の念仏の方がそうでない人の念仏よりも勝れているように思います。また、戒を守って生活を厳しく整えている人の念仏の方が勝れているように思います。「必ず悟りを開いて人々を救うぞ!」という強い決意を持った人の念仏の方が勝れているように思います。全ての人へ慈しむ人がいたならば、その人の念仏の方がそうでない人の念仏よりも勝れているように思います。しかしそうではありません。私たちは私たちが勝れているから救われるのではないのです。決して勝れた身ではない私たちが、阿弥陀さまの力でのみ救われるのです。
善人は善人のまま、悪人は悪人のまま、ただ生まれつきのままに念仏する人こそ、「念仏に助をささない人」というのです。その身そのままで阿弥陀さまはお救いくださるのです。
しかしこのように言いますと、必ず勘違いする人が出てきます。「念仏を称えれば救われるというなら、どんなに悪いことをしてもいいのか」という人です。もちろんそんなことはありません。本来仏教は「悪いことはやめましょう。善いことをしましょう。」というのが基本です。ただ、私たちには煩悩があるので善い行いがなかなかできません。善い行いができないだけでなく、煩悩による悪い行いが知らず知らずの内にも積み重なっていくのです。だからといって開き直ってはいけません。悪い行いをしたくないのにしてしまうのと、「どうせ悪い行いしかできないのだから、どんどん悪い行いをすればいい」と開き直るのでは大違いです。「悪を改め、善人となって念仏しようという人」が阿弥陀さまの御心に叶う人です。
また逆の勘違いもあります。自分を深く見つめる余りに、「私のような愚かな者は、阿弥陀さまの力でも往生などできない」と仏の力を疑ってしまうのです。私の力ではどうしようもないけれども阿弥陀さまの力は大きいのです。それを信じなくてはなりません。「どうせ私は愚かで、阿弥陀さまの御心になど叶わない」と、ああだこうだ思って往生決定の心が起こらない人は往生できないと書かれています。
阿弥陀さまの力を信じるということは、簡単なようで難しいのですね。こちら側の計らいを捨てて阿弥陀さまにお任せしていくのです。これだけのことをしっかりと信じることは昔から難しかったのでしょう。昔から勘違いする人が多かったのでしょう。だからこそ法然上人は、常に仰せられたのでありましょう。