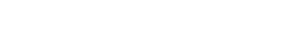前篇第二十九章 対治慢心
(本文)
まことしく念仏を行じてげにげにしき念仏者になりぬれば、よろずの人を見るに、皆我が心には劣りて浅ましく悪ければ、我が身の善きままに、我は由々(ゆゆ)しき念仏者にてあるものかな。誰々(たれたれ)にも勝れたりと思うなり。この心をばよくよく慎むべきことなり。
世も広く人も多ければ、山の奥、林の中に籠もり居て人にも知られぬ念仏者の貴くめでたきさすがに多くあるを、我が聞かず知らぬにてこそあれ。されば我ほどの念仏者よもあらじと思う僻事(ひがごと)なり。
この思いは大驕慢(だいきょうまん)にてあれば、即ち三心も隠るなり。
またそれを便りとして魔縁の来たりて往生を妨ぐるなり。これ我が身のいみじくて、罪業をも滅し極楽へも参ることならばこそあらめ。偏(ひとえ)に阿弥陀仏の願力(がんりき)にて煩悩(ぼんのう)をも除き、罪業(ぜいごう)をも消して、かたじけなく手ずから自ら極楽へ迎え取りて帰らせましますことなり。我が力にて往生することならばこそ、我賢しという慢心(まんしん)をば起こさめ。驕慢(きょうまん)の心だにも起こりぬれば、心行(しんぎょう)必ず誤る故に、立ち所に阿弥陀仏の願に背きぬるものにて、弥陀も諸仏も護念し給わず。さるままには悪鬼のためにも悩まさるるなり。返す返すも慎みて、驕慢(きょうまん)の心を起こすべからず。あなかしこ、あなかしこ。
(現代語訳)
まじめに念仏を行い、いかにもそれらしい念仏者になると、多くの人を見るにつけ、みな自分の心より劣り、あきれる程ひどいので、自分をよしとする思いにまかせて、「私はなんと立派な念仏者なのだろう。だれよりも上だ」と思うようになるのです。こうした心こそ、よくよく慎むべきなのです。
世間も広く、人も多いので、山の奥、林の中に隠れ住み、人にも知られていない念仏者で貴く素晴らしい方が、やはり多くいるのを、自分が聞かず、知らないだけのことなのです。
ですから「私ほどの念仏者はあるまい」と思うのは心得違いです。この思いは大変な思い上がりなので、つまりは三心も欠けることになるのです。またそれをよいことにして、悪魔が近づき、往生を妨げるのです。
この思い上がりも、自分が優れているために〔自力で〕罪業をも滅し、極楽にも往生できるというなら仕方ないかもしれませんが、ひとえに阿弥陀仏が、その本願の力によって〔念仏者の〕煩悩をも除き、罪業をも消して、もったいなくも自ら極楽へ迎え取って、お帰り下さるのです。
自分の力で往生するというならば、「私は勝れている」という慢心を起こしても仕方ないかもしれませんが、思い上がりの心が起こっただけで、心も行も必ず道を外れるので、たちまち阿弥陀仏の本願に背くことになり、阿弥陀仏も諸仏もお守り下さいません。そのままでは悪鬼にも悩まされるのです。
くれぐれも慎んで、思い上がりの心を起こしてはなりません。あなかしこ。あなかしこ。
(解説)
法然上人のご法語は、当然お念仏を勧めるものが多いのですが、今回のご法語は少し趣が違います。
お念仏を相当称えている人に対して「気をつけなくてはいけませんよ」と戒めておられるご法語です。
人間は絶えず人と比べて自分の位置を確認します。
初対面の人に対して、心の中では「私より年上かな」と思ったら敬語になり、「年下かな」と思えば少し偉そうになることもあるかもしれません。
誰を見ても誰と会っても絶えず自分より上か下かを考えて、自分の位置を定めるのです。普通の生活であれば、差し支えはないでしょう。
でもそれを仏の教えにまで持ち込むといけません。
お念仏を勧められて、最初は「ありがたいなあ」と思って称え出します。
そこからが問題です。
一所懸命称えている自分に気づいて、他人と比べるのです。
「あいつは俺より念仏が少ないなあ」と。
お念仏は阿弥陀さまと私の関係です。
他人と比べても仕方ありません。
救われがたい私を阿弥陀さまが救うと言って下さっているのに、人と比べて自分が偉くなっては何のことやらわからなくなります。
法然上人はそういう者を厳しく戒めておられます。
「まことしく念仏を行じて、げにげにしき念仏者になりぬれば、よろずの人を見るに、我が心には劣りて、浅ましく悪ければ我が身のよきままに我はゆゆしき念仏者にてあるものかな。誰々にも勝れたりと思うなり。この心をばよくよく慎むべきことなり」
「まじめにお念仏を称え、立派な念仏者になると、自分の他の多くの人をみて、みな自分の心より劣り、どうしようもなく悪くみえて、自分は良しとして、私は勝れた念仏者だなあ。他の誰よりも、あの人よりもこの人よりも勝れていると思う。こういう心こそよくよく慎むべきことですよ」
「世も広く人も多ければ、山の奥、林の中に籠もりいて、人にも知られぬ念仏者の、貴くめでたき、さすがに多くあるを、我が聞かず知らぬにてこそあれ」
「世間も広く人も多いので、山の奥林の中に籠もっていて、誰にも知られていない念仏者で貴くすばらしい方が多くいるのを自分が聞いたことがなく、知らないだけなのです」
「されば、我ほどの念仏者よもあらじと思う僻事なり」
「ですから、私ほどの念仏者はまさかいないと思うのはとんでもないことです」
「この思いは大驕慢にてあれば、即ち三心も欠くるなり」
「こういう思いはとんだ思い上がりなので、つまりは極楽へ往生するための心が欠けてしまいます」
お念仏は、ただ口に称えるだけではなく、本気で阿弥陀さまを信じて、本気で極楽往生を願って称えねばなりません。
それなのに「私は勝れた念仏者だなあ」などと思うのは、阿弥陀さまではなく自分を信じてしまっているわけです。
それではいけません。
「またそれを便りとして、魔縁の来たりて往生を妨ぐるなり」
「またそれをきっかけにして、悪い縁がやってきて、往生を妨げるのです」
魔縁について、最近大相撲などを見るにつけ思うところがあります。
相撲も一所懸命強くなりたいという一心で稽古をしている時には悪い縁はやって来ません。
しかし「俺はそこそこ強いなあ」と思って、他人と比べ出したら危ないです。
遊びを覚えてちょっと小遣い稼ぎをしようかと思い出すと危険です。
あっという間に魔縁がワッと集まってきます。
真面目にしていたときには寄りつかなかった悪い縁がドッとやってきます。
お念仏も同じです。
往生したいという一心でお念仏を称えていればよいものを、他人と比べ出したとたんに悪い縁が近づきます。
人の悪口を言う人が近づいてきたり、おべんちゃらを言う人が近づいてきて、結局はお念仏から離れてしまいます。
注意しなくてはなりません。
「これ我が身のいみじくて、罪業をも滅し、極楽へも参ることならばこそあらめ。ひとえに阿弥陀仏の願力にて煩悩をも除き、罪業をも消して、かたじけなく手ずから自ら極楽へ迎え取りて帰らせましますことなり」
「このような思い上がりも、自分の力で罪を消し、自分の力で極楽へ往くというのならば仕方のないことかもしれません。(しかしそうではなく)ひとえに阿弥陀さまの本願の力によって煩悩も除いていただき、罪も消していただき、もったいなくも自ら極楽へ迎え取ってお帰りになるのです」
「我が力にて往生することならばこそ、我賢しという慢心をば起こさめ。驕慢の心だにも起こりぬれば、心行必ず誤る故に、立ち所に阿弥陀仏の願に背きぬるものにて、弥陀も諸仏も護念し給わず」
「自分の力で往生するならば、私は勝れているという慢心を起こしても仕方がないのかも知れません。(しかしそうではないのだから)思い上がりの心が起こっただけで、極楽へ向かう心も行としてのお念仏も必ず道を外すことになるので、たちまち阿弥陀さまの本願に背くことになったら阿弥陀さまも他の仏さまも護りようがないでしょう」
「さるままには、悪鬼のためにも悩まさるるなり」
「そのままでは悪鬼に悩まされることになるでしょう」
「返す返すも慎みて、驕慢の心を起こすべからず。あなかしこ、あなかしこ」
「くれぐれも謹んで、思い上がりの心を起こしてはいけません。ああ恐れ多いことです」
そのそも「なむあみだぶつ」とは、「阿弥陀さま、お救い下さい、阿弥陀さま、助けてください!」という言葉です。
「助けてくれ!」という者が偉いはずがないですね。
阿弥陀さまは私たちが決して偉い者ではなく、救われがたい者であるから、わざわざお念仏をご用意くださったのです。
私たちが自分で苦しみから逃れることができるのであれば、お念仏なんて必要ないのです。自分で苦しみから逃れることなど到底できない我々であるから、阿弥陀さまは私たちに代わってご修行下さり、その修行の功徳をすべて南無阿弥陀仏の六文字に込めて下さったのです。
「私の名前なら称えることもできるであろう」とどんな力のない者でもできる行をご用意下さったのです。
それをお念仏の回数が多いだとか信心が深いなどと自惚れるなどというのはとんでもない誤りです。
この阿弥陀さまの力を他力といいます。
「私の力ではなく、阿弥陀仏の力でのみ救われる」というみ教えです。
この他力は、実は分かりやすいようで理解するのが難しい教えです。
大僧正と大学を出たての若い僧侶を比べたら、何となく大僧正のお念仏の方が貴いように思いませんか?
大僧正が称えても小僧が称えても救うのは阿弥陀仏ですから、違いなどあろうはずがありません。
確かに人徳も知識も人生経験も小僧と比べれば大僧正の方が勝れているのかも知れません。
しかし、ことお念仏に関しては人と比べて何にもなりません。
お念仏は阿弥陀さまと私一人の関係です。
この私が救われる唯一の教えであると受け止めて、決して自分に頼ることなく、阿弥陀さまの力、他力のみを信じてお念仏を称えるのです。
このご法語はお念仏をかなり称える人が陥りやすいところを法然上人がご注意下さっているわけですから、かなりレベルが高いのかも知れません。
ただ、わざわざこのようにおっしゃるということは、頻繁にこういう人がいたのでしょう。
私たちもよくよく注意せねばなりませんね。